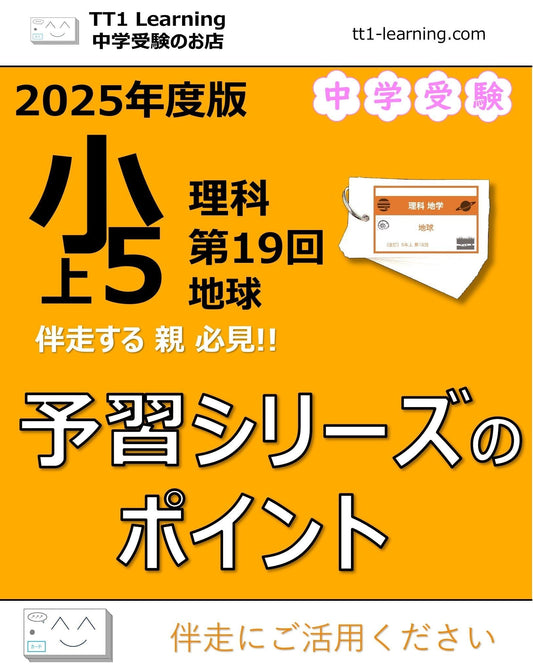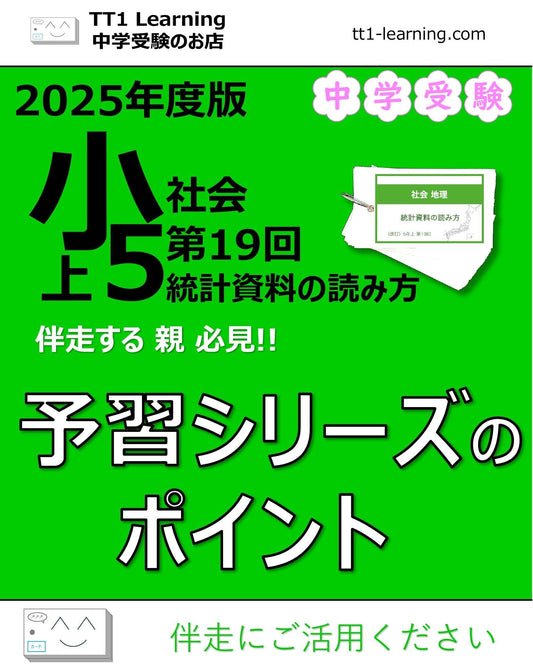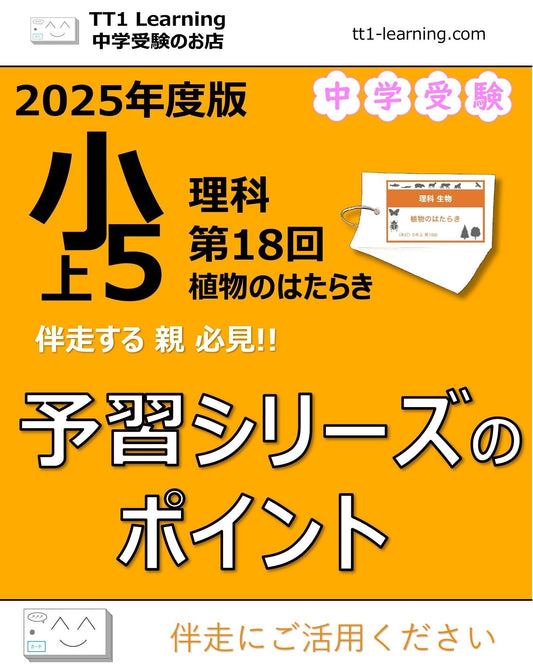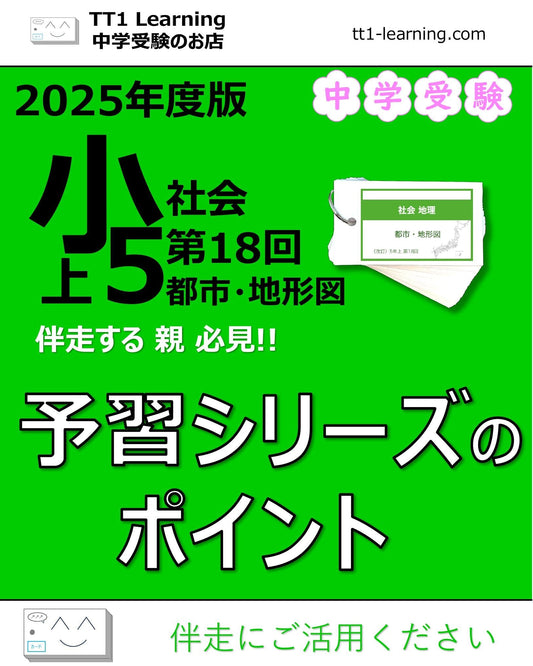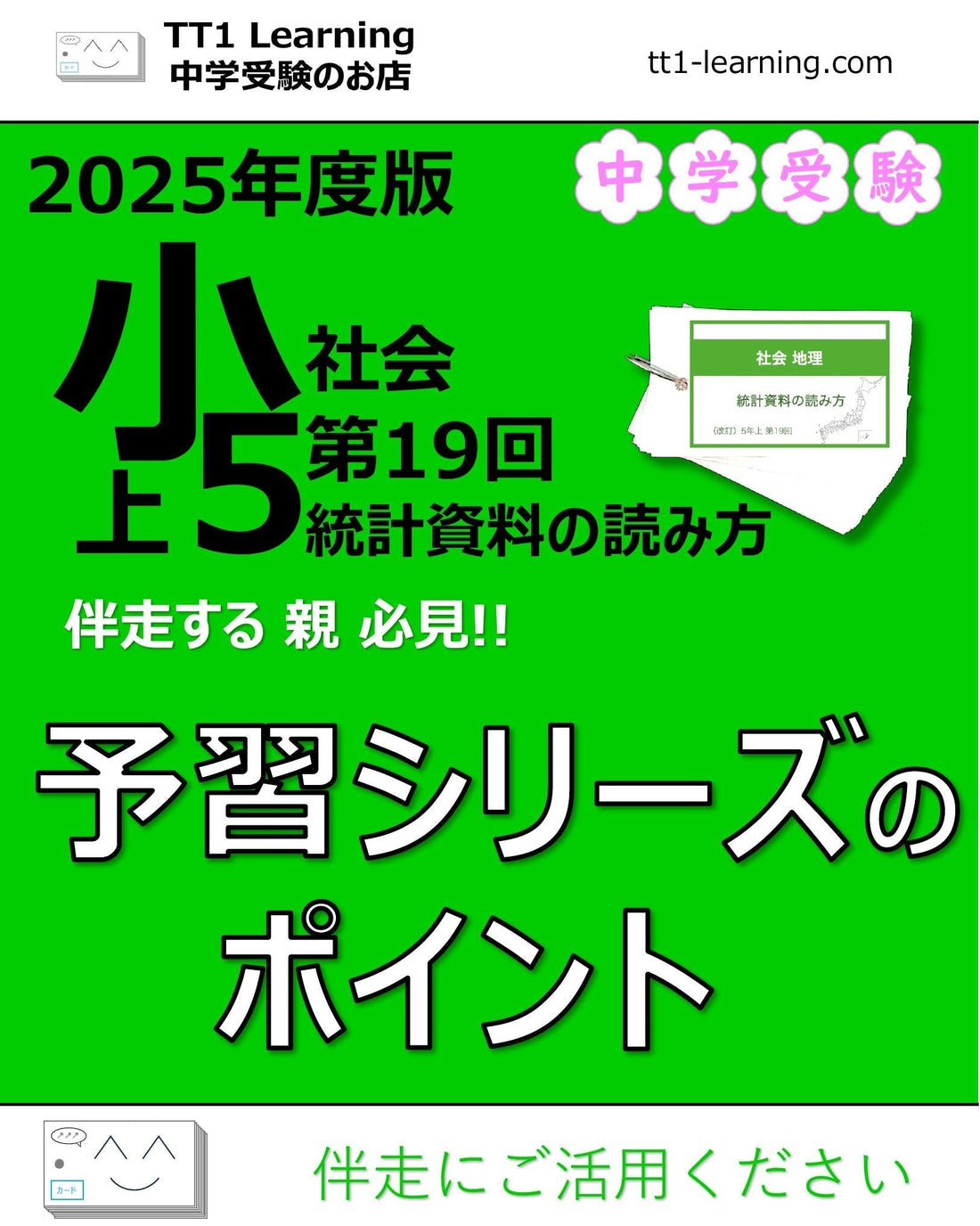
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 社会 第19回「統計資料の読み方」ポイントまとめ
共有
小5社会予習シリーズ第19回、上期最後の回です!
19回のテーマは「統計資料の読み方」
この単元では、グラフを正しく読み取り、そこから特徴や変化を見抜く力が問われます。
数字を暗記することよりも数字の背景にある理由を考えることが大切です。
本記事では、各テーマごとにポイントを整理し、保護者の方が伴走しやすいように解説します。
参考になりましたら幸いです!
単元の概要
-
グラフを読むポイント
グラフを読む基本スキルを身につける 折れ線、棒、円グラフなどの種類を理解し、横軸と縦軸が何を表しているかを読み取る力が重要です。
変化や極端な数字に注目 数字の増減には必ず背景があるため、なぜそうなったかを考えることがポイントです。 - テーマ別の統計資料
産業や人口の特徴を把握する 農業、工業、エネルギー、人口など多岐にわたるテーマについて、統計資料をよめるようにします。
グラフをよむ基本ポイント
- ポイント①グラフの種類
→折れ線グラフ(推移を見る)、棒グラフ(比較する)、円グラフ(構成比率を理解する)など、使われる目的が異なります。 - ポイント②グラフの軸の意味
→横軸は「時間」や「場所」、縦軸は「物量」や「金額」が多いです。特に、どちらが変化を示しているか意識します。 -
特徴の見極め
→大きな数字、小さな数字、急な増減に注目します。極端な値は試験で問われやすく、理由も考察しておくと有利です。

農業の統計資料
- 生産物の量・金額 × 都道府県
農業生産物の都道府県ランキングなどは頻出。
農業生産物がどこの都道府県に多いかは覚えておきましょう - 生産物の量・金額 × 時間推移
上記が「現在」の生産物に対して、時間経過とともに変化するグラフもよく出ます。
また、グラフの変化の理由もよく問われます。
例:1960年以降の高度経済成長期では農業の割合が減少し、工業化が進みました。また、オイルショックや震災による変化も考えられます。

工業の統計資料
工業統計も農業生産物と同じような形で出てくることが多いです。
- 工業生産物の量・金額 × 場所
場所により工業生産物が異なります。その理由を押さえておくことが大切!
→中京は自動車工業が盛ん。京浜工業地帯は化学工業や石油関連、阪神は重化学工業が盛んです - 工業生産物の量・金額 × 時間
日本が得意としてきた工業生産物の移り変わりも頻出です!
→戦前は繊維工業が盛んでした。戦後は金属や機械の割合が増加し、近年では情報通信機器や化学製品の生産も伸びています。
棒グラフや積み上げグラフで各産業の構成比率を見比べて、その製品が何かをわかるようにしておきましょう - 生産物の量・金額 × 工場の規模 大工場は工場数は少なくても生産額が非常に大きい点に注目。逆に中小工場は数は多いが生産額が小さい特徴があります。

エネルギーの統計資料
エネルギーは、生産物とは逆にどんな原料や手法を使っているか?という軸で出てきます。
また、ややこしいのは、手法としての発電方法、原料としての発電源などがある点。
何を意味するグラフなのかをしっかりと考えないとこんがらがってしまうので注意です。
- 発電方法別の割合 x 時間
水力、火力、原子力、再生可能エネルギー(風力・太陽光など)があり、震災後に原子力の割合が減り、火力発電が再度増え、再生可能エネルギーも少ないながらも上昇するというのが大きな特徴 - 発電源となる資源の割合 x 時間
石油、石炭、天然ガスなど、資源の使用割合も時代とともに変わります。高度経済成長期には石油依存が高まりましたが、現在は多様化しています。 - 発電源となる資源の量 見かけ上割合が減っていても、全体の量としては増えているケースもあります。単純に割合だけを見ず、量の推移にも注目が必要です。

人口の統計資料
人口のグラフは少し特殊です。
年齢 x 性別の人口の数のグラフは頻出です。
- 人口ピラミッド 年齢別の人口構成を表すグラフで、1950年は「富士山型」(出生率が高く高齢者が少ない)、1970年は「つり鐘型」、2020年は「つぼ型」(少子高齢化)と形が変わってきています。
- 都市別・都道府県別ランキング 都市別では東京23区、横浜、大阪、名古屋などが上位。都道府県別では東京、神奈川、大阪、愛知が多いです。特に横浜が大阪より人口が多い点は頻出ポイントです。
- 時系列の変化 経済成長や社会の変化に合わせて、都市部への人口集中(都市化)が進んでいます。

覚え方のコツ
- グラフは「何を」「どのように」表しているかを理解する 量・金額・割合・時間・場所の組み合わせをまず意識します。
- 数字の背景を一緒に考える なぜ増えたのか、なぜ減ったのかを親子で話し合うと理解が深まります。
- 特徴を言葉にして説明する練習 説明できるようになると試験でも強いです。
- 暗記カードを活用し、スキマ時間に復習 目にする回数が多いほど記憶は定着します。
まとめ
統計資料の読み方は、単なる暗記ではなく「考える力」を育む大切な単元です。グラフを一緒に見ながら、「なぜこうなったのか?」を問いかけることで、子どもの理解が飛躍的に深まります。親子でクイズ形式にして楽しく進めるのもおすすめです。ぜひ暗記カードや実際の資料を活用しながら、伴走してあげてください!
暗記カード紹介(おすすめ活用法)
- カード学習で視覚的に整理、反復できる
- 表裏の確認作業でアウトプット練習になります。
- クイズ形式で親子で楽しみながら学べる
- ゲーム感覚で取り組むとモチベーションアップにつながります。
- 漢字や地名確認にも効果的
- 読み方や書き方の習得にも役立ちます。
小5上期の予習シリーズのポイントの記事
社会
理科
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。