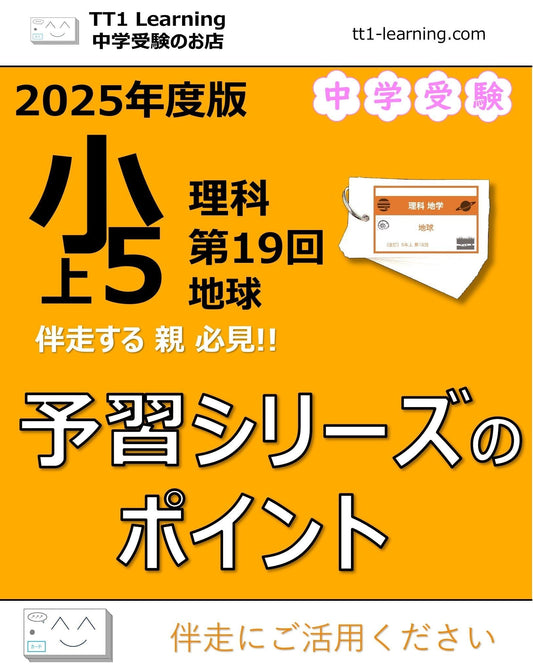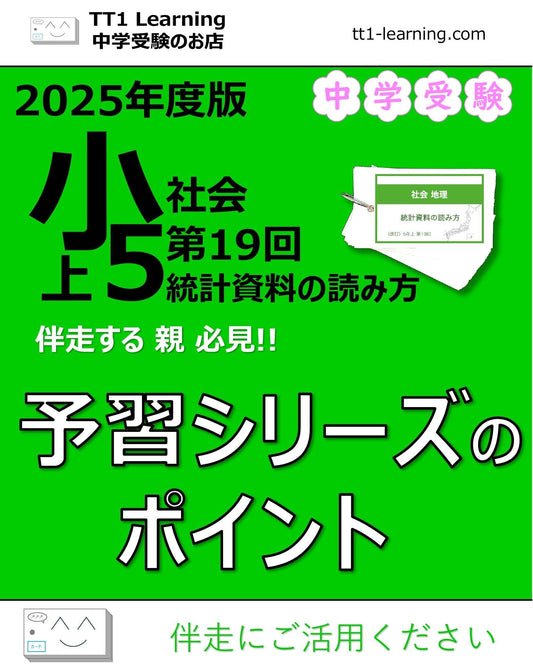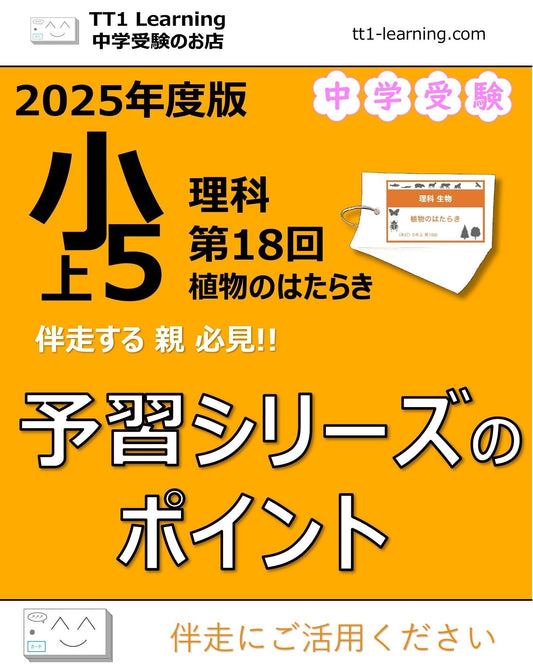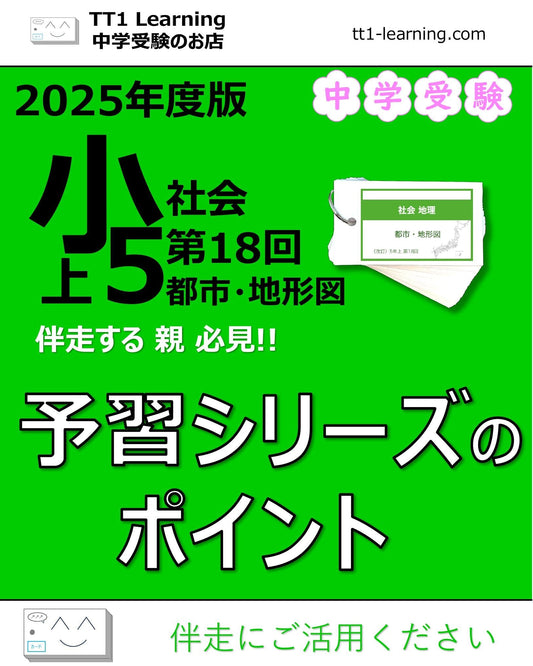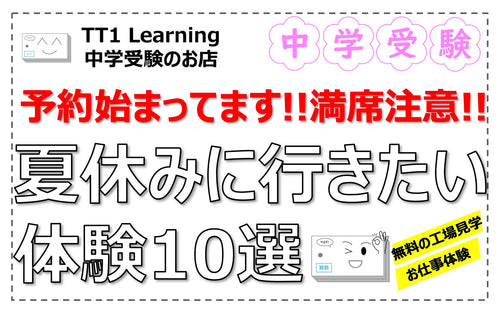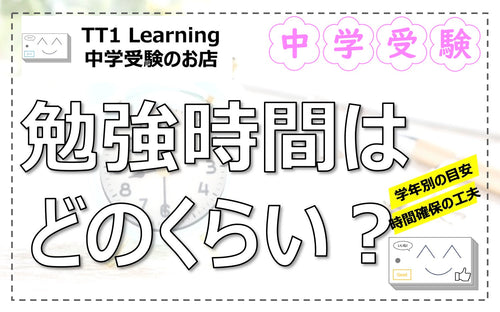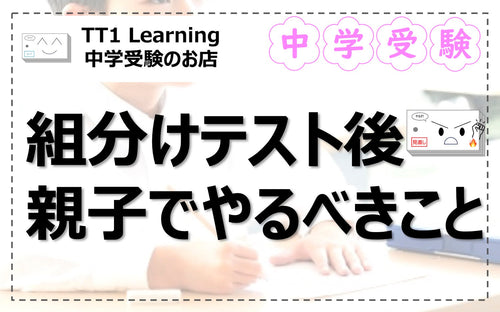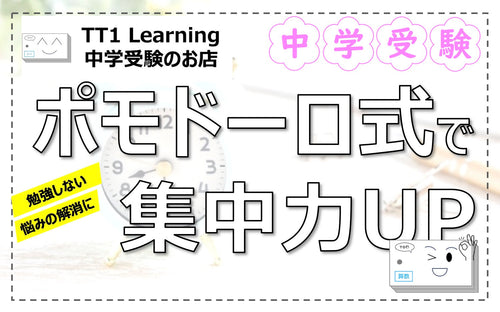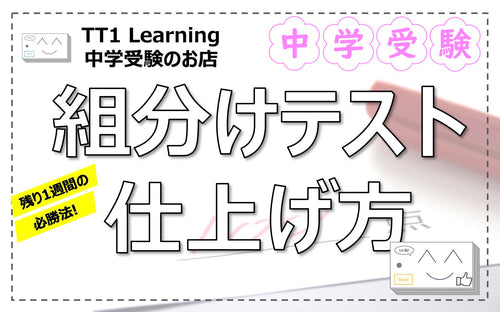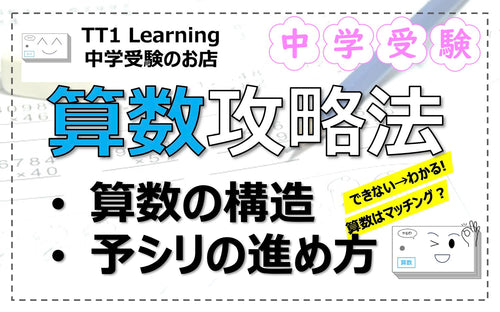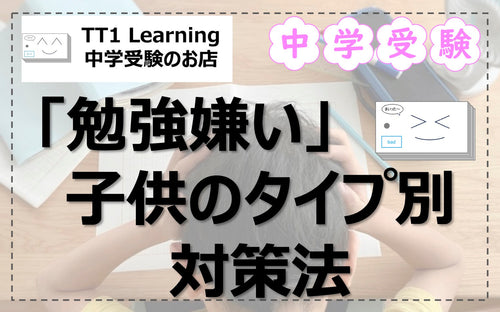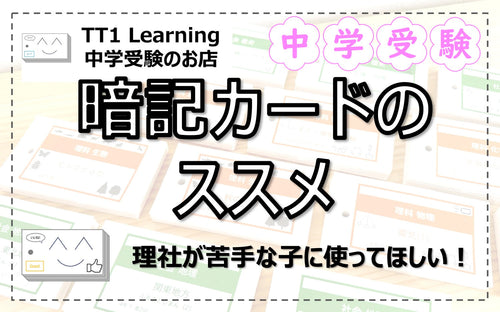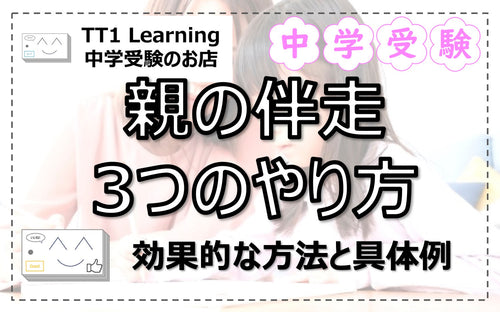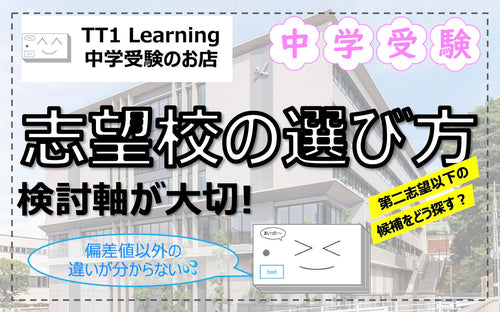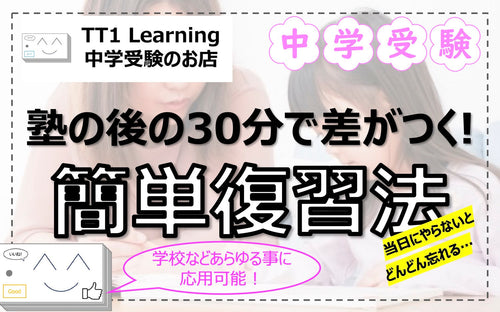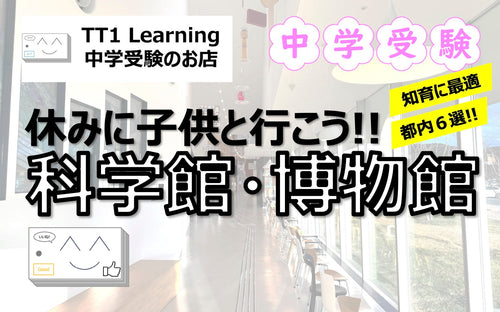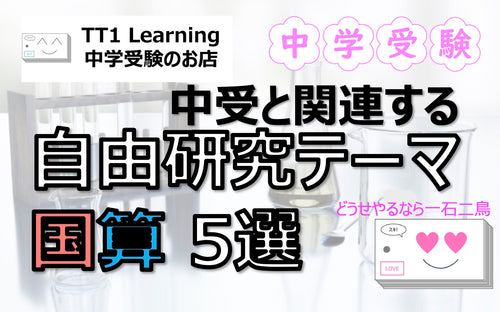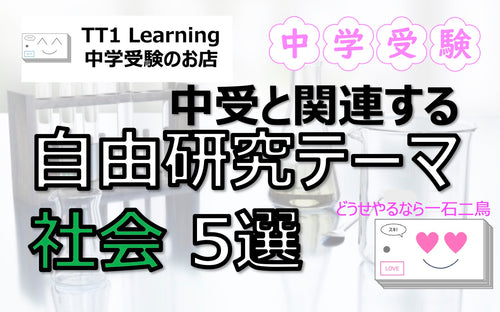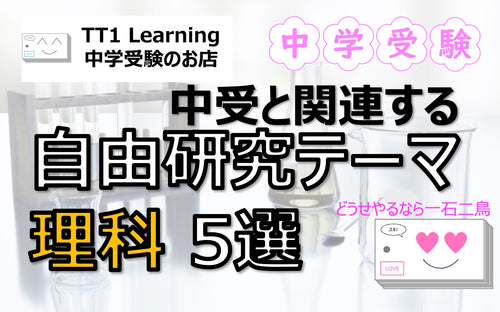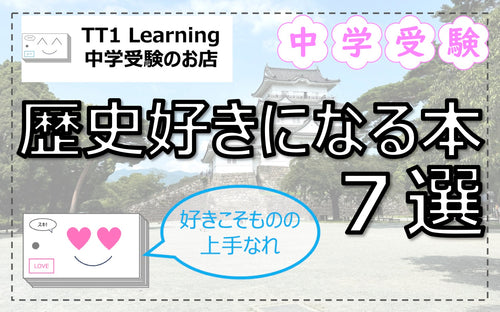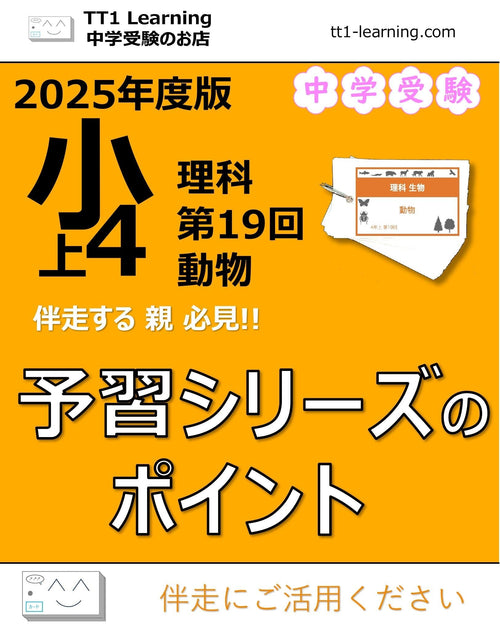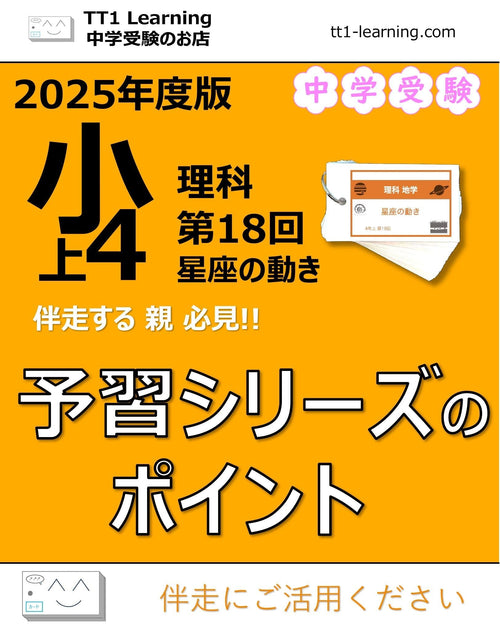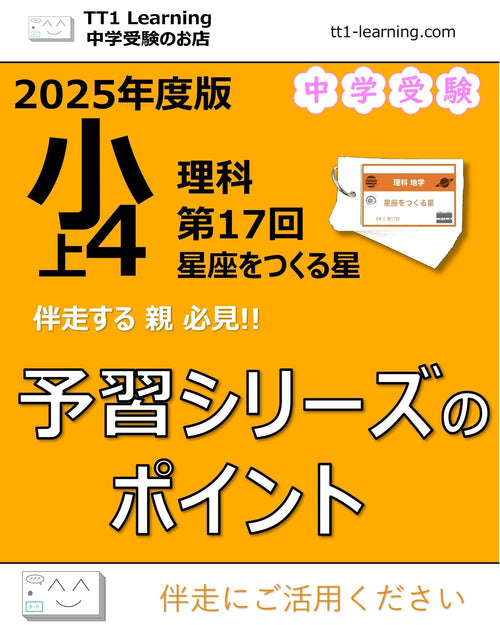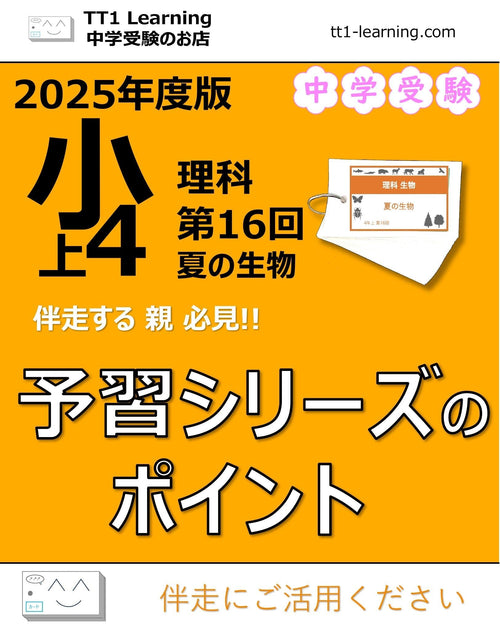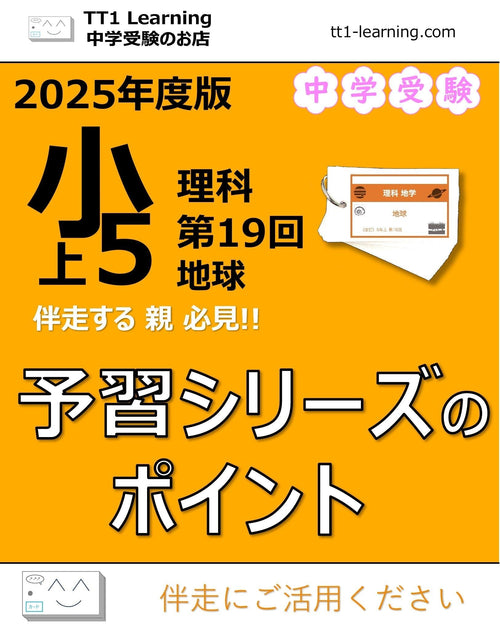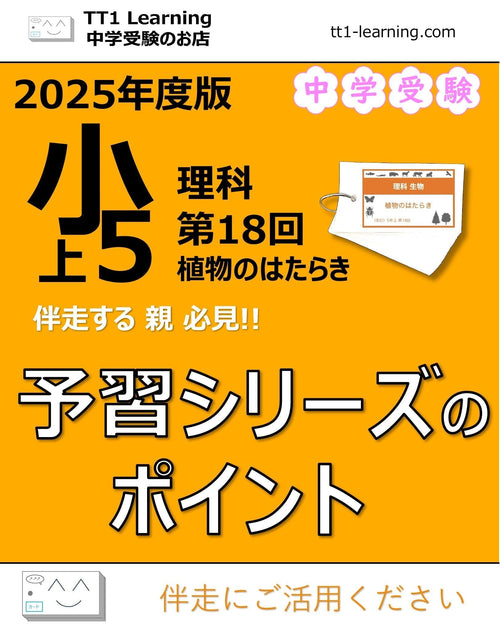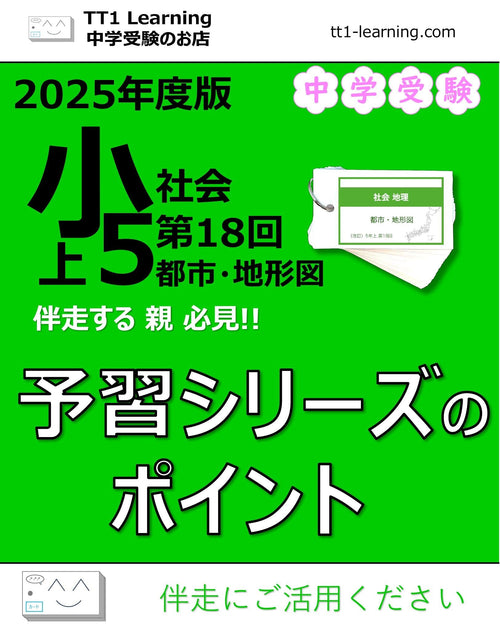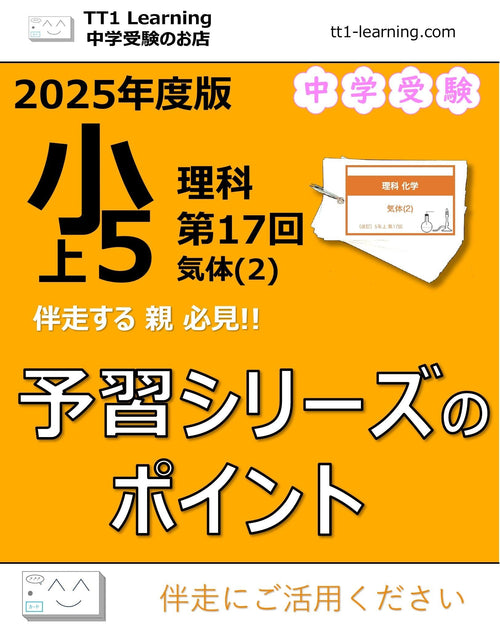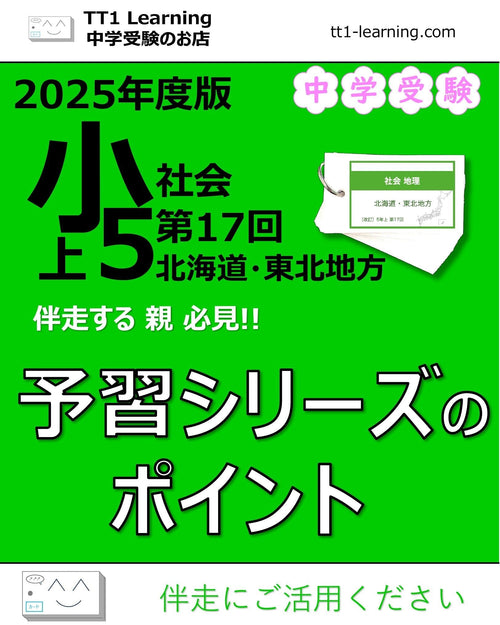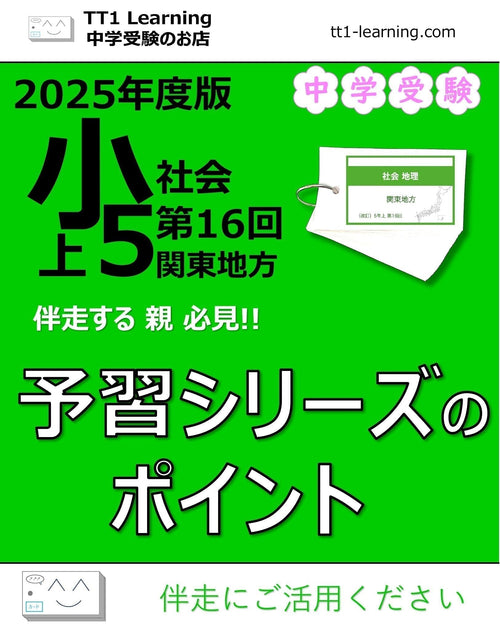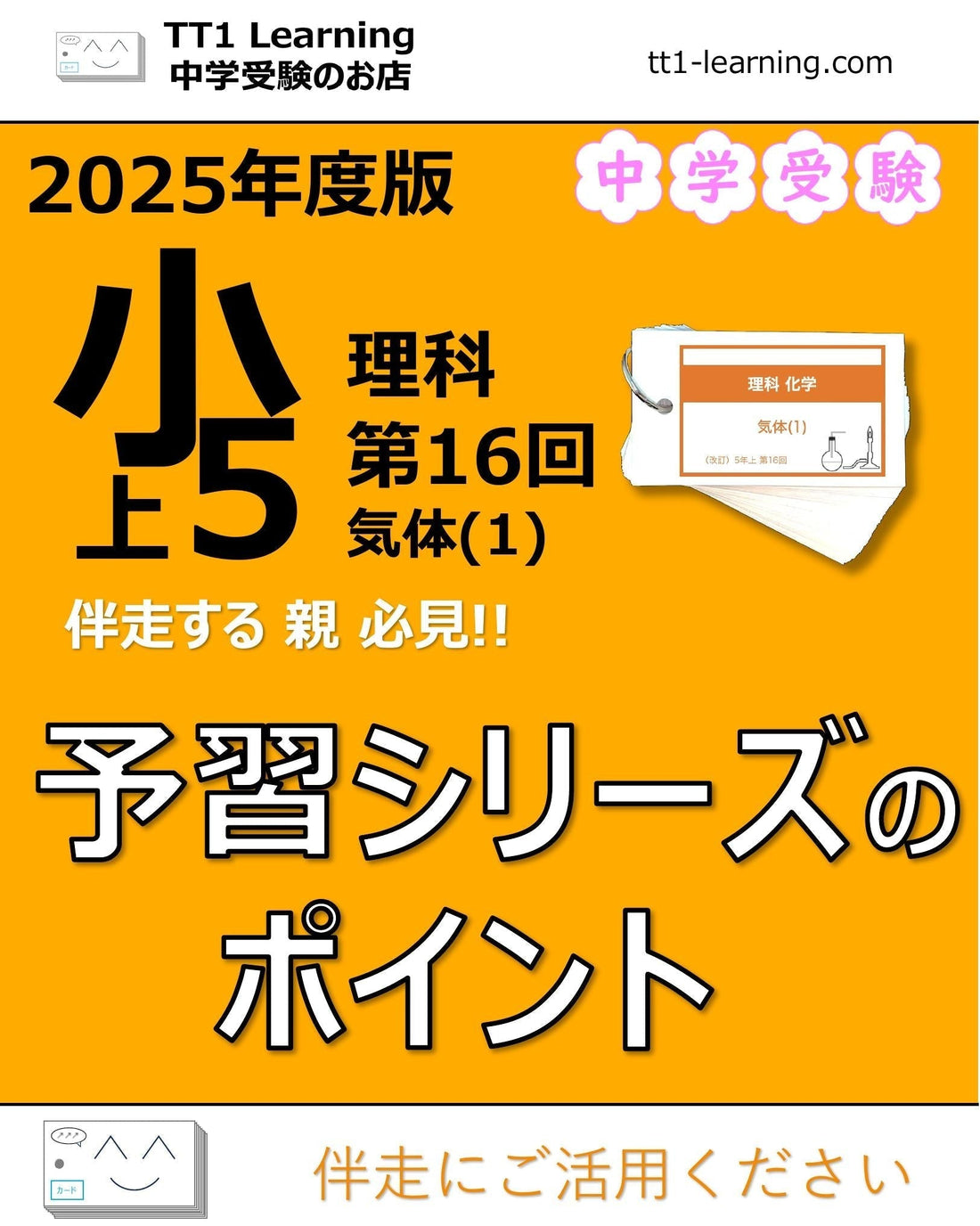
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第16回「気体(1)」ポイントまとめ
共有
今回のテーマは理科「気体(1)」の単元です。
気体は中学受験理科の中でも、出題頻度が高く、苦手意識を持つお子さんも多い分野です。しかし、一度「なぜそうなるのか」を理解して整理しておくと、化学の似たような単元は同じ考え方でクリアできるようになるので大きな得点源になりえます。
特に実験内容が絡むため、単なる暗記ではなく「性質を使い分けて理解する力」が求められます。
この単元は親御さんが一緒に確認してあげることで、お子さんの理解度がぐっと上がります。
暗記カードや表を作るなど、工夫を取り入れながら楽しく進めていきましょう!
単元の概要
- 身近な気体
空気はちっ素と酸素が主要。二酸化炭素は実は少ない。アルゴン、メタンなどの気体の特徴を押さえる
- 気体の集め方
水上置換法、上方置換法、下方置換法の3つ。水に溶けにくい場合は水上置換法
- 気体の性質・つくり方
水溶性、可燃性、においなどから何の期待であるか判別できるようにしておく
気体をどのように発生させるか、前後でどの物質ができるか、実験器具の使い方
1. 身の回りの気体と割合・特徴を理解する
まずは、空気の中に含まれる気体の割合を知るところからスタートしましょう。
- 窒素:78.08%
- 酸素:20.95%
- アルゴン:0.93%
- 二酸化炭素:0.04%
こうして見ると、二酸化炭素はごくわずかしか含まれていないことが分かります。
これは「二酸化炭素は地球温暖化の原因」と言われるので印象が強いですが、実際には空気中ではとても少ない成分です。
このギャップを知っておくと、問題文を読むときに引っかかりにくくなります。
さらに、各気体の特徴も整理しておきます。
- 窒素:タンパク質の材料になる、肥料の成分、硝酸の構成要素、窒素酸化物は酸性雨の原因にもなる。
- 酸素:生物の呼吸に必要、物を燃やすのを助ける(助燃性)。
- アルゴン:電球の中に使われる、不活性ガス。
- 二酸化炭素:石灰水を白くにごらせる、空気より重い、燃焼しない。
- 水素:非常に軽い、燃えると水ができる。
- アンモニア:独特の刺激臭がある、水に溶けやすい、アルカリ性。
- メタン:都市ガスの主成分、燃えると二酸化炭素と水になる、温室効果ガス。
- 一酸化炭素:不完全燃焼で発生、無色・無臭で有毒、空気より少し軽い。
- 塩化水素:刺激臭があり、水に溶けると塩酸になる。
- 二酸化硫黄:酸性雨の原因、大気汚染物質。
ちょっと量が多いですが、だんだんと覚えていきましょう!
2. 気体の集め方を使い分ける
気体を集める方法は3種類あります。
- 水上置換法:水に溶けにくい気体を集める方法。酸素、窒素、水素など。
- 上方置換法:水に溶けやすく、空気より軽い気体を集める方法。アンモニアなど。
- 下方置換法:水に溶けやすく、空気より重い気体を集める方法。二酸化炭素、塩化水素、二酸化硫黄など。

特に重要なのは、二酸化炭素が「水上置換法」と「下方置換法」の両方で集められることです。二酸化炭素は水に多少溶けます。一方で下方置換法では純度の高い二酸化炭素を集めることは難しいです。二酸化炭素を集める際に純度の高い場合は水上置換法、純度は求めない場合や二酸化炭素の発生量を測る場合は下方置換法を使うと覚えておくと良いですね。
問題で出されると混乱しやすいポイントなので、必ず押さえておきましょう。
どの気体がどの方法で集められるかを間違えやすいので、表にまとめると一目瞭然です。「水に溶けやすいか」「空気より重いか軽いか」を基準に整理しておくと、理解が深まります。
3. 性質から気体を見分ける練習
気体の性質は表で頭に入れましょう

気体の性質だけで、どの気体かを判別する問題がよく出ます。
例えば、
- 水に溶けない、助燃性がある → 酸素
- 水に溶けやすい、刺激臭、アルカリ性 → アンモニア
- 非常に軽く、燃えると水になる → 水素
表を何度も見返しながら、まずは特徴を覚え、その後「どの特徴を組み合わせるとどの気体になるのか」をお子さんと一緒にクイズ形式で確認してみるのがおすすめです。問題文に「水に溶ける」「刺激臭がある」「空気より重い」などのヒントがあれば、それらを手がかりに特定できます。
また、性質を単独で覚えるのではなく、実際の生活や実験と結びつけると記憶に残りやすいです。例えば、「アンモニアはトイレの掃除で鼻にツンとくるにおい」など、身近な体験とリンクさせると楽しく覚えられます。
4. 気体の作り方と反応の理解
理科の実験では、気体を作り出す方法も問われます。
- 酸素:過酸化水素水に二酸化マンガンを加えると酸素と水が発生します。
- 二酸化炭素:作り方は複数ありますが、以下の二つは覚えましょう
- 石灰石(炭酸カルシウム)に塩酸を加える → 二酸化炭素+水+塩化カルシウム。
- 炭酸水素ナトリウムを加熱 → 二酸化炭素+水+炭酸ナトリウム。
- 水素:金属(アルミニウムや亜鉛など)に塩酸や水酸化ナトリウム水溶液を加える → 水素+塩化金属。
- アンモニア:
- アンモニア水を加熱。
- 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを加熱。
- 塩化水素:濃塩酸を加熱。
- 二酸化硫黄:硫黄を燃焼させる。
大事なのは「どの物質から何ができるか」「副生成物は何か」「器具はどう使うか」をしっかり把握することです。器具の使い方も問題で問われるので、実験図を見ながら説明してあげるとイメージがつきやすいです。
これらの反応は一度に全部覚えるのは大変なので、1つずつ順番に進めましょう。「今日は酸素の作り方を完璧にする日!」と決めて、確認テストやカードを使いながら覚えると定着しやすいです。
確認テストと暗記カードの活用
どれだけ理解できたかを確認するには、アウトプットが欠かせません。お子さんと一緒に小テストを作ったり、暗記カードでチェックしたりするのがおすすめです。
当サイトの単元別暗記カードは、予習シリーズに合わせて作成されているので、使いやすく、効率よく進められると好評です。「自分でカードをめくりながら確認する」という行動が、単なる読み込みよりも記憶に残りやすいです。
また、「間違えたカードだけまとめてやる」「家族と一緒にクイズ形式で楽しむ」といった工夫で、モチベーションもアップします。「覚えたつもり」を防ぎ、確実に知識を定着させるためにぜひ活用してみてください。
お客様からの声も参考に掲載させてください!

まとめ
気体の単元は、一見難しそうに見えますが、ポイントを整理すれば得点源に変えられます。「覚えることが多い」と感じるお子さんも多いですが、表やカード、実験動画などを活用することで、楽しく理解を深めることができます。
最初から完璧を目指さなくて大丈夫です。小さな「できた!」を積み重ねることが大切です。そして、理解した後は繰り返しの演習で定着させましょう。親御さんと一緒に進めることで、お子さんの安心感とやる気も大きく変わります。
この夏、「気体」を得意単元に変えて、テストでも自信を持って解答できるようにしていきましょう。もし質問や感想があれば、ぜひコメントやお問い合わせで教えてください。一緒に頑張る皆さんを全力で応援しています!
小5上期の予習シリーズのポイントの記事
社会
理科
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。