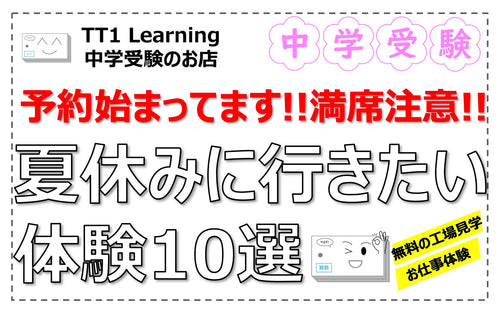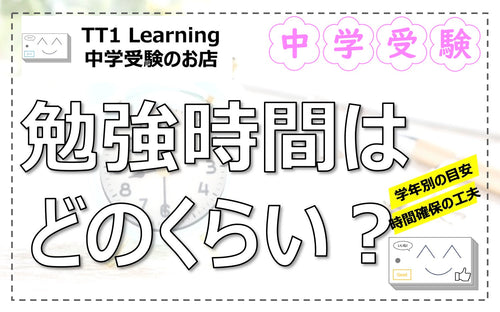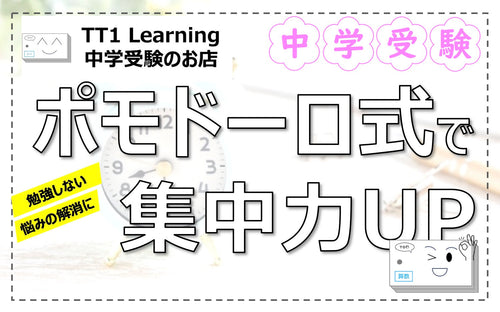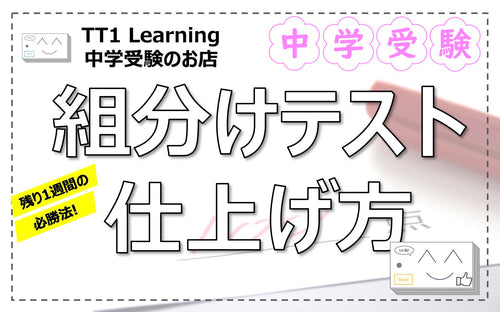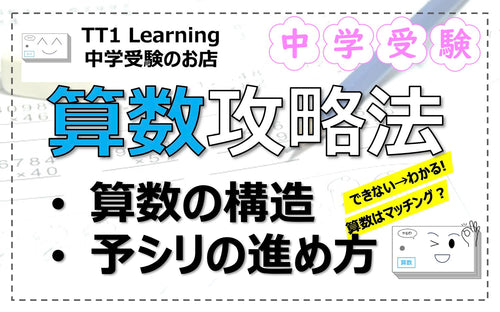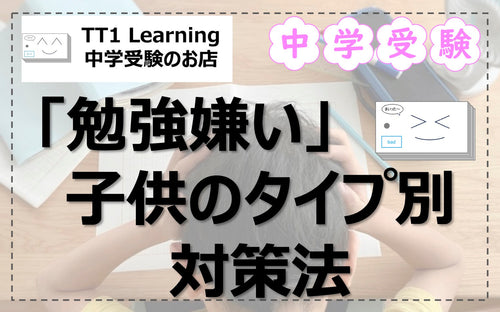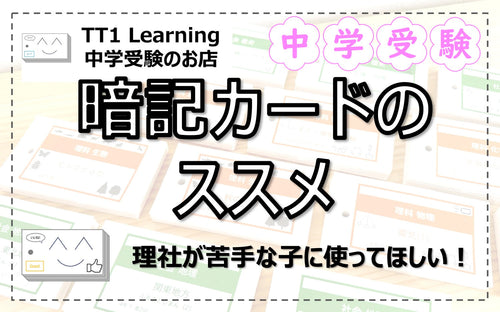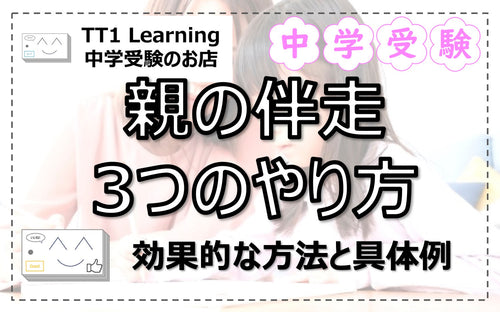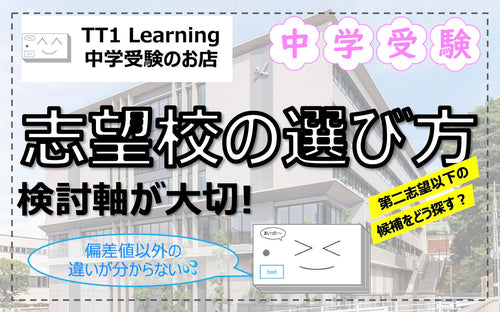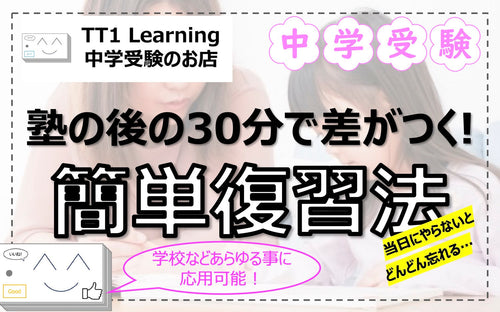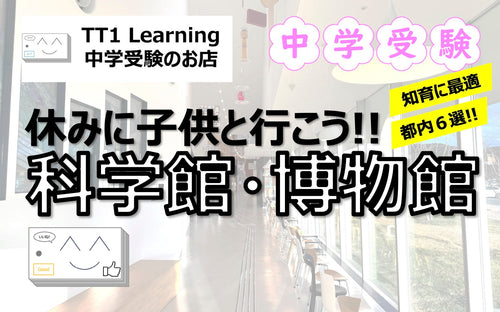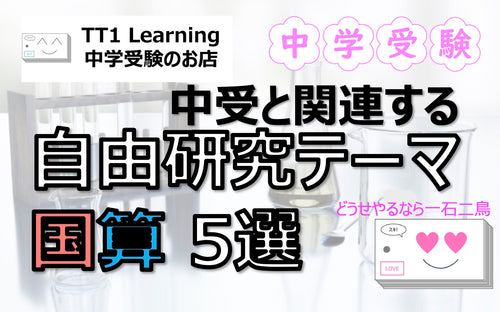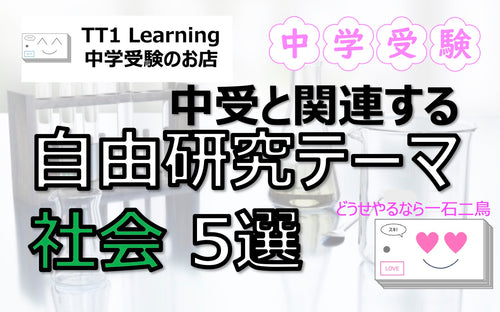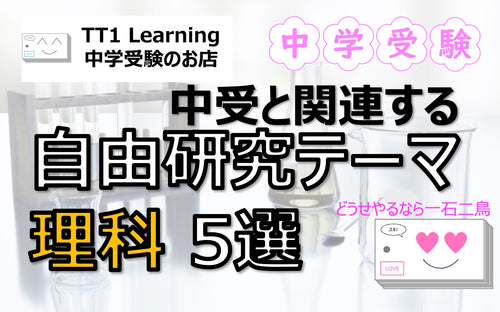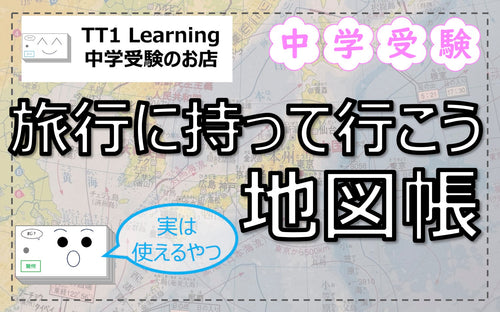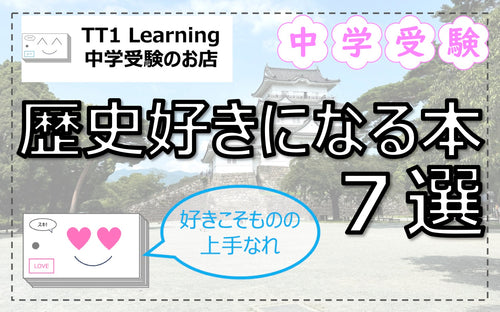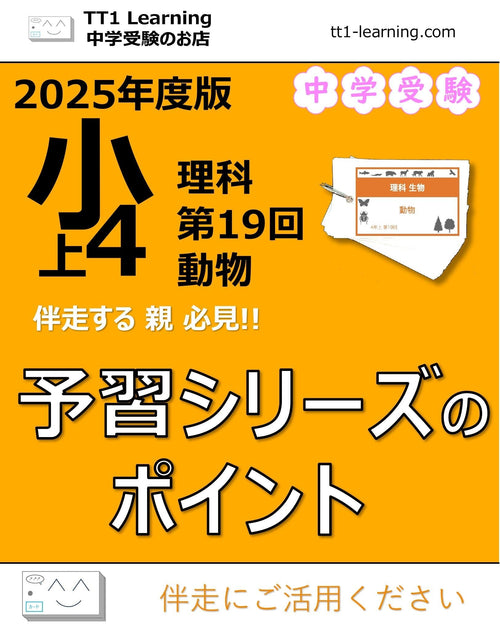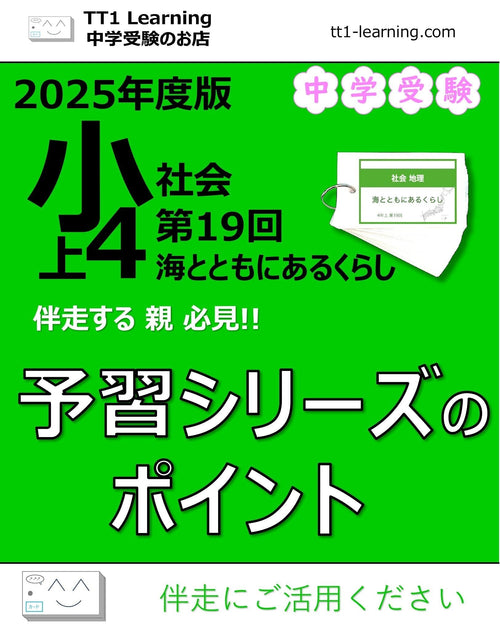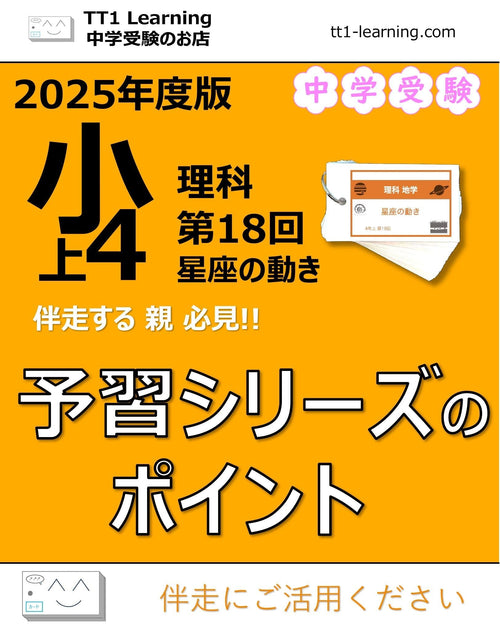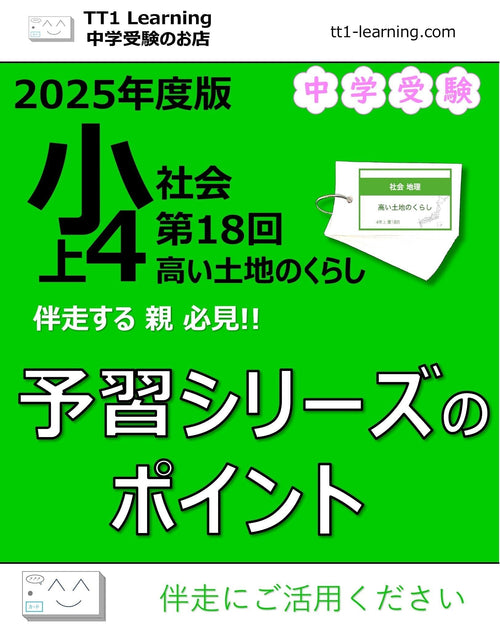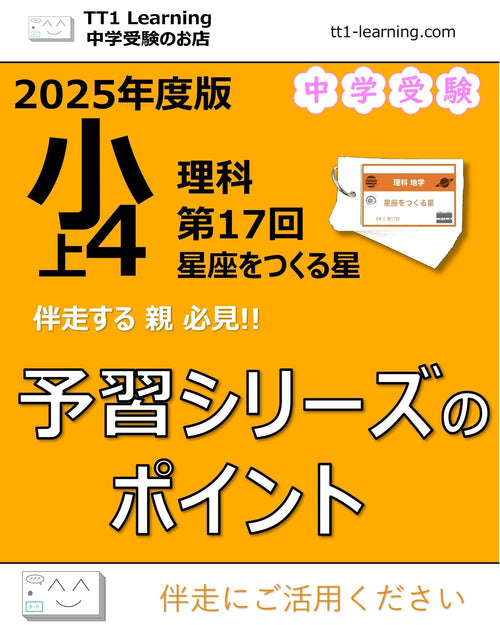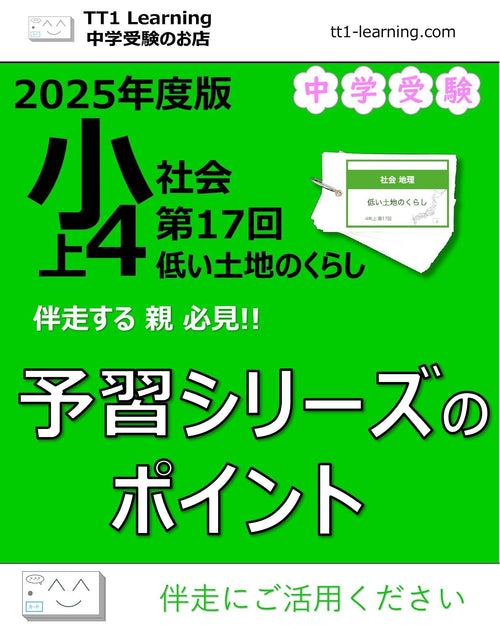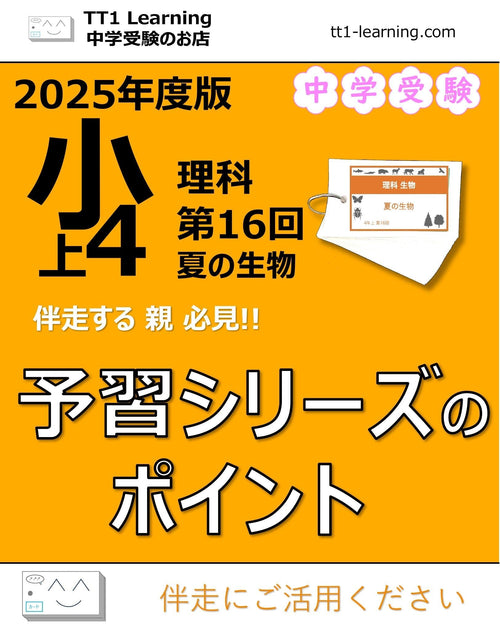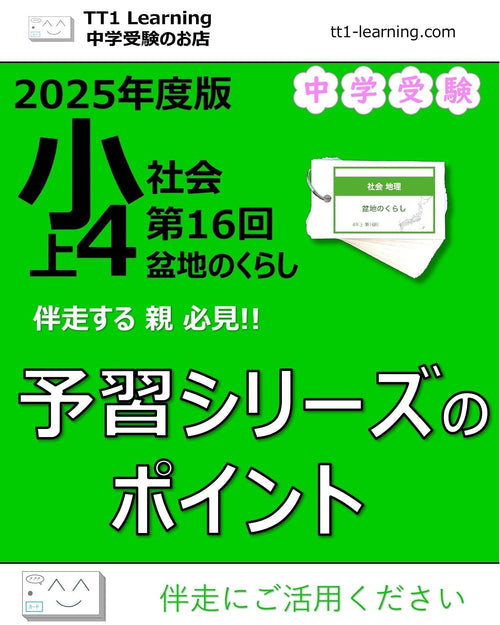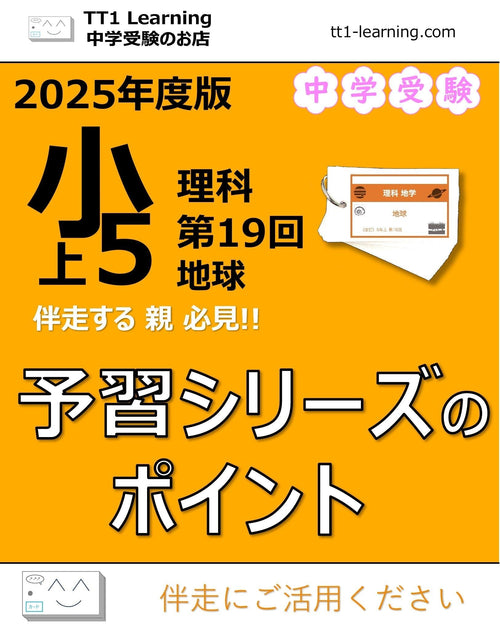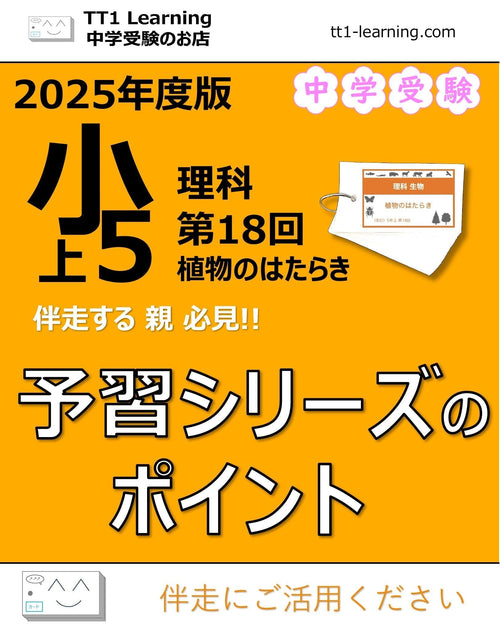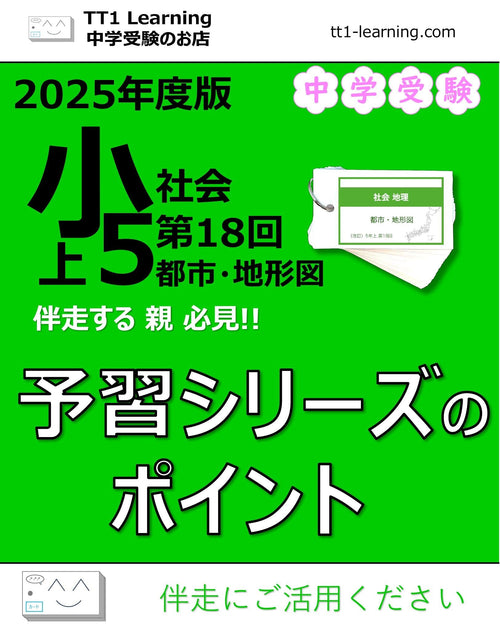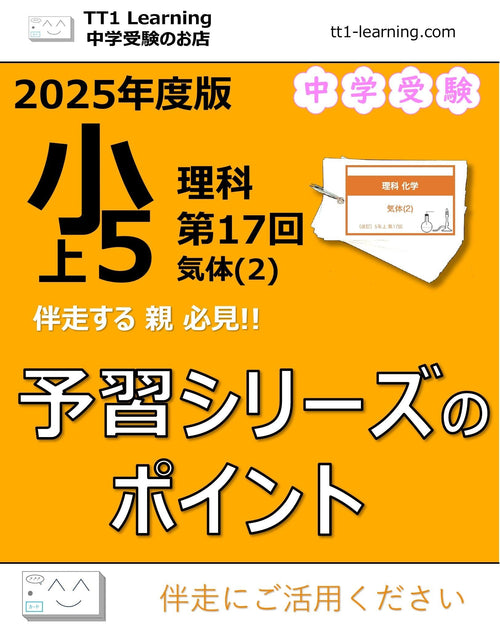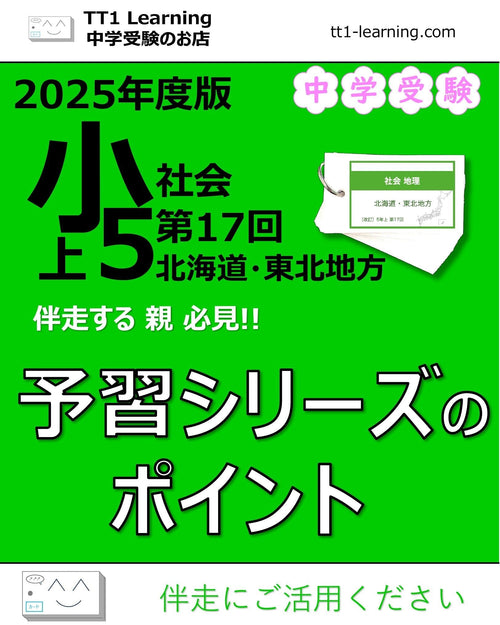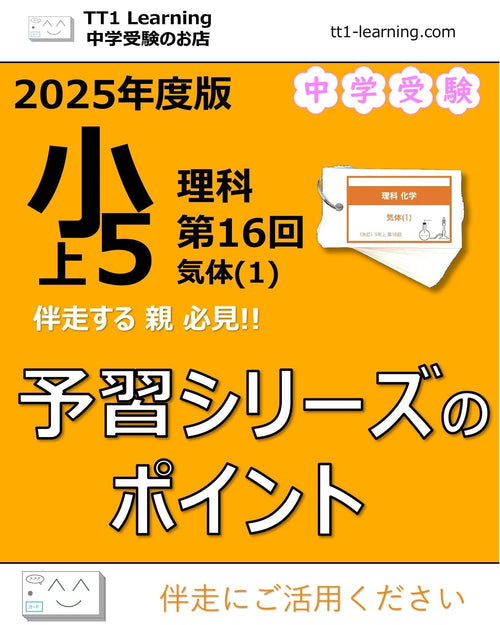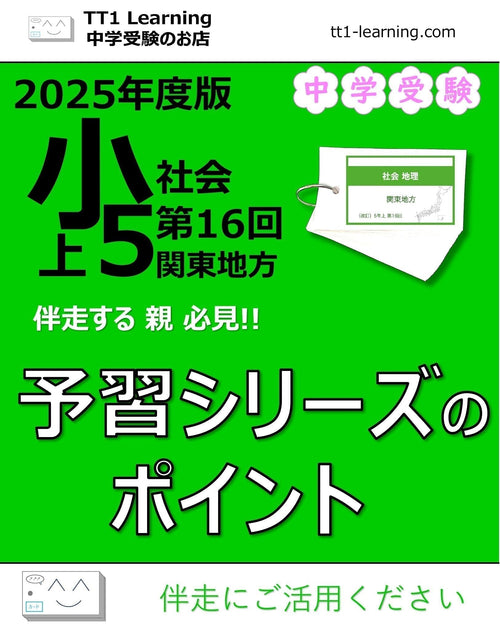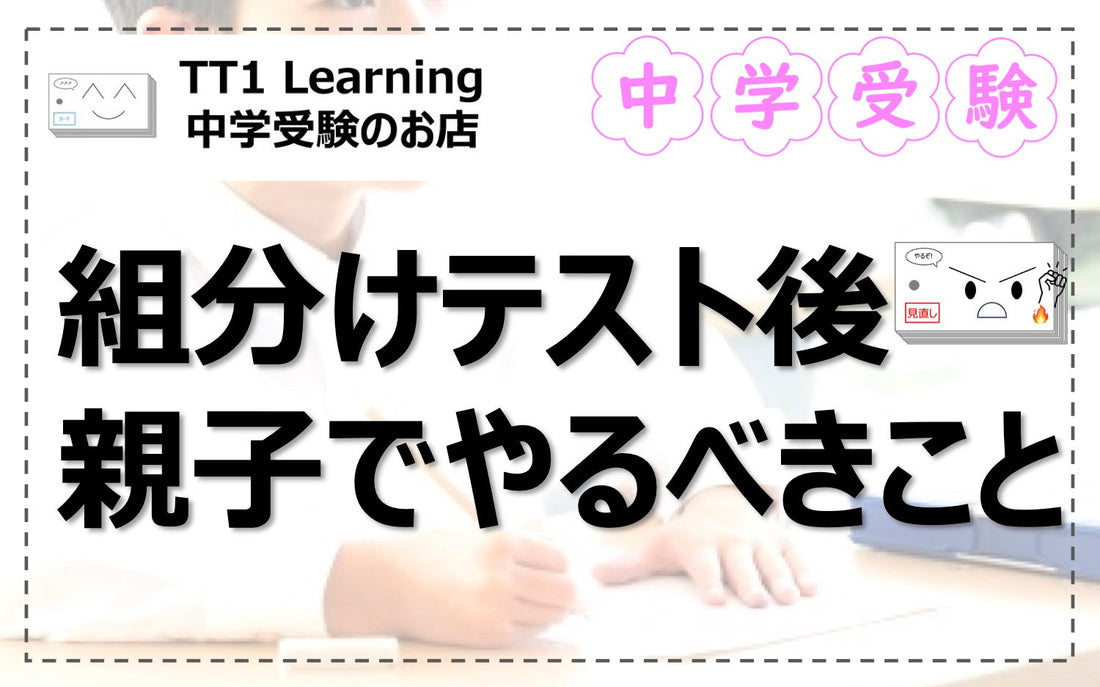
【中学受験】組分けテスト後 親子で振り返り・復習法のまとめ
共有
組分けテスト、お疲れ様でした。
この数週間、お子さんもご家庭も本当に頑張ってこられたと思います。その努力の成果が数字や偏差値という形で返ってくるのがテストですが、結果が良かった時もそうでなかった時も、本当に大切なのはここから先の行動です。
「テストが終わってホッとしたのはいいけれど、この後どう振り返ればいいの?」
「苦手だったところ、どうフォローしていけばいい?」
「親としては何をすれば子どもにとってプラスになる?」
こんな悩みは、我が家でも毎回のようにありました。そこで今回は、組分けテスト後に親子で実践しやすい振り返り・復習の流れを具体的にご紹介します。
テストの後こそ、次の成長に向けたとても大事な学びのチャンス。ぜひ、無理なく楽しく活かしていきましょう。
まずはメンタルコントロールから
まず一番大切なのは、テスト結果に対する親の姿勢と声掛けです。
親としてはどうしても「なぜここができなかったの?」「もっと頑張らないと」と焦る気持ちが出てしまいます。
でも、それがダイレクトに子どもに伝わってしまうと、結果を素直に受け止められなくなってしまうかも。
特に中学受験は長丁場。
毎回のテスト結果に一喜一憂していては、親も子どもの気持ちが持他ない。。
おすすめなのは、「本番じゃなくて良かった」「今回の振り返りが、次の力になるよ」というスタンスで接すること。
こんな声掛けを意識するといいと思います!
- 「今わかってよかった!本番で間違えるよりずっといいよ」
- 「できなかった問題は宝物。次に克服すれば武器になるね」
- 「まずは今日一緒に振り返りして、次に生かす準備しよう」
親の言葉一つで、子どもの心の切り替えは大きく変わります。特に低学年〜小5くらいのお子さんは影響を受けやすいので、ポジティブな声掛けを意識するのが◎
計画と結果を比較しよう
次に取り組みたいのが、全体の振り返りです。
まずは親子で机にテスト結果や問題用紙を並べて、「どの教科から見直す?」と子どもと一緒に流れを作りましょう。
おすすめの流れは以下の通り。
1. 目標点との比較
事前に目標点を決めていた場合は、それに対してどうだったかを確認。目標点を決めていなかった場合も、「ここはよく頑張ったね」「この単元はもう少しだったかな」と、良かったところと課題を両方伝える。
2. 単元別の強み・弱みの把握
「社会は地理はよかったけど、歴史が弱かったかな」「理科は計算問題がスムーズにできたね」
3. 時間配分・解き順の確認
「理社の時間配分どうだった?」「国語の長文は最初に解いた?後に回した?」
この振り返りは、親が一方的に分析するのではなく、子ども自身に話させるのが大事なポイント。
「今回はどうだったと思う?」「次はどうしてみたい?」
という質問形式で進めることで、子どもの考える力と主体性が育ちます。
できなかった問題の分析は宝の山
間違えた問題の見直しは、最も重要な復習のチャンス。
ただ、見直しの際に「なんでこんな問題間違えたの?」「前やったでしょ?」という言い方は逆効果。子どもは委縮してしまい、本来の学びができなくなります。
我が家で効果的だったのは、まず間違いの種類を一緒に分類することです。
分類例:
- わかっていたのにミスした(ケアレスミス)
- 知識が曖昧だった
- 解き方がわからなかった
この分類をするだけでも、子どもは「次は何を意識すればいいのか」が明確になります。

声掛け例:
- 「じゃあこれは次はどうすれば間違えずにできそう?」
- 「この知識はまだ曖昧だったね。次はどう覚え直してみようか?」
こうした問いかけベースの会話を意識すると、復習が子どもの主体的な行動につながります。
解き直しは3回サイクルで
間違い直しは、一度やって終わりにしがちですが、繰り返しのサイクルを作ることで定着度が大きく変わります
おすすめは「3回サイクル」
サイクル内容:
1回目:テスト直後に解説を見ながら確認(なるべく1〜2日以内が理想)
2回目:1〜2週間後に再確認(解説なしで自力で解く)
3回目:1〜1.5ヶ月後に全体を通して解き直し

こうすることで、「その時覚えていたけど忘れていたもの」「本当に理解できたもの」の判別ができます。
我が家では「復習カレンダー」を簡単に作り、いつどの問題を見直すかを親子でスケジュールに組み込んでいました。
これが意外と楽しく、「次はこの問題やる日だ!」と子どももやる気になるポイントになります。
知識不足には暗記カードが効果的
理社など知識系の科目は、正確な知識の積み重ねがそのまま得点差につながる分野。テスト後の復習でも暗記カードは非常に強力なツールになります。
暗記カード活用のポイント:
- 間違えた知識だけを集中反復できる
- 移動中・スキマ時間でもすぐ確認できる
- ゲーム感覚で取り組める → やる気の維持に効果的
- 親子でクイズ形式にして取り組める
「間違えた問題に関連するカード」を1セット作って集中的に回すだけでも効果は大きいです。
我が家でも、理社はカードの回数に比例して安定してきた実感がありました。
ちなみに当ECサイトでは予習シリーズの単元に合わせた暗記カードを販売中です!
ぜひ一度覗いてみてください〜
ご購入者の声をご紹介します
実際に暗記カードをご利用いただいたご家庭からは、以下のような声が多く届いています。
成績・点数に効果を実感した声
- 「社会で満点、理科も自己ベストが取れました」
- 「理社の組分けテストで点数が安定してきて、苦手意識が減ってきました」
子どもが楽しんで使っている声
- 「朝の5分でカードをめくるのが日課に。本人も自信がついたようです」
- 「親子でクイズ形式にして使っていたら、子どもの方から『もっとやりたい』と言うようになりました」
カードの質・使いやすさへの評価
- 「親が一からカードを作るのは本当に大変…。この完成度とボリュームはありがたい」
- 「図解や関連知識が入っていて、理解が深まる作りだと感じた」

まとめ
組分けテストの後、親子でどう向き合うかが、次の結果を大きく左右します。
まずは結果を冷静に受け止め、振り返り、間違いから学び、具体的な対策へと繋げていく。この一連の流れを、ポジティブな雰囲気で進めていくことがとても大切です。
その中で、暗記カードのようなツールもぜひ活用して、学習の質を高めていきましょう。
「今回はここが課題だった。じゃあ、次はこうしてみよう。」
そんな前向きなサイクルを親子で作っていけたら、きっとお子さまの学びはもっと楽しく、力強いものになります。
記事は以上です。
今回も最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
よろしければ暗記カードのサンプルや関連記事を読んでみてください。
お子様の勉強のお役に立てましたらとても嬉しいです‼︎
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。