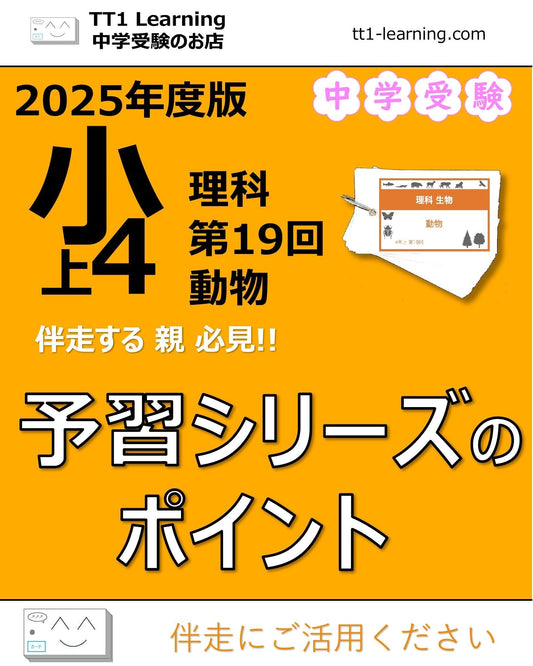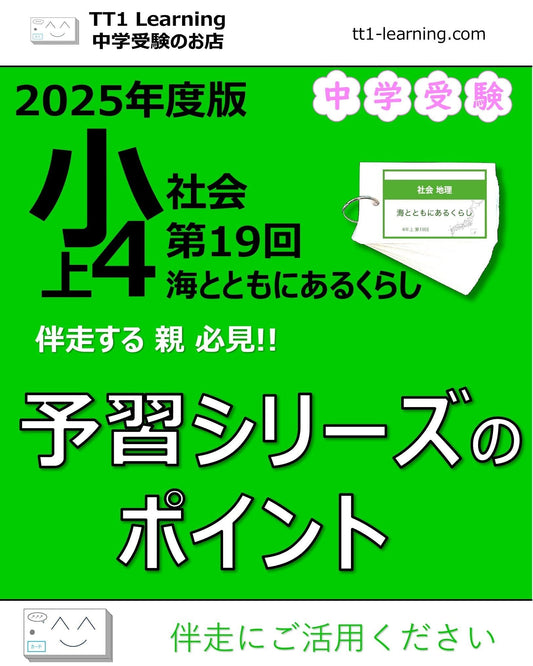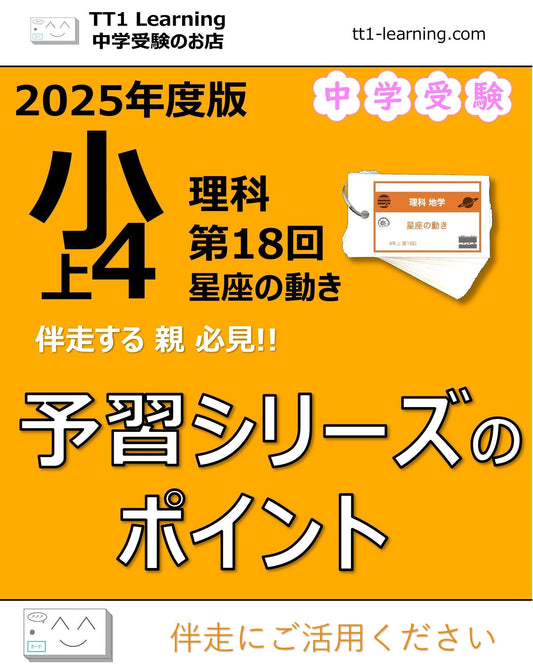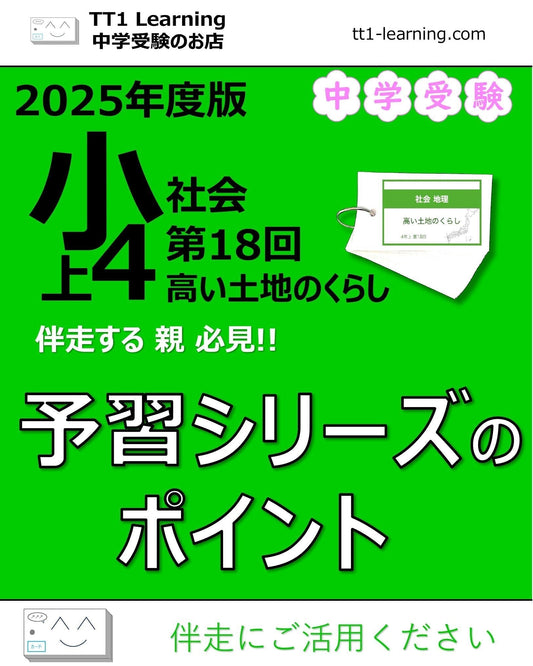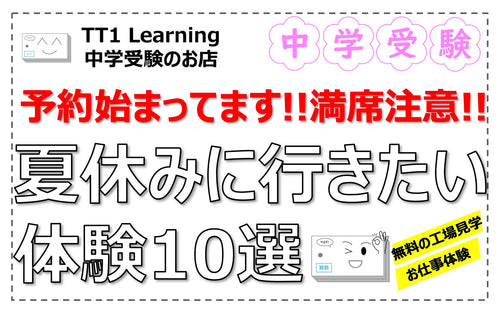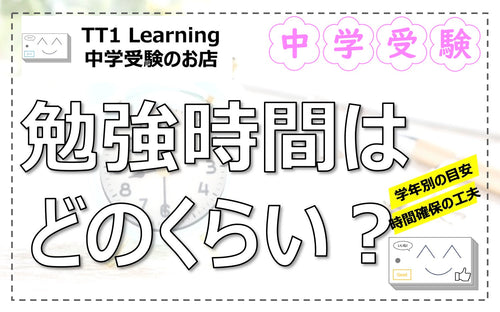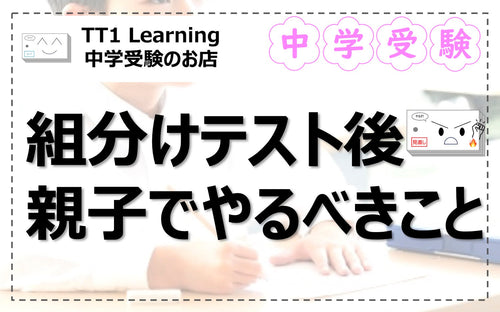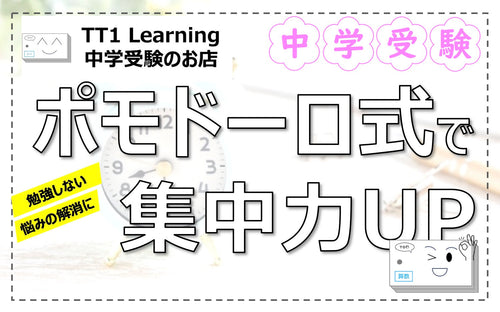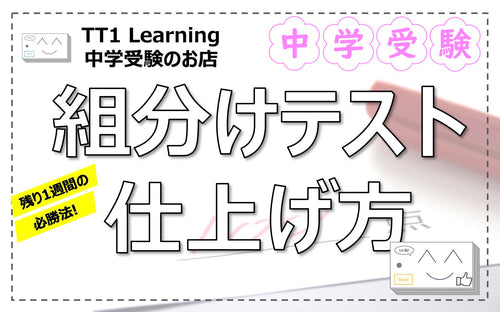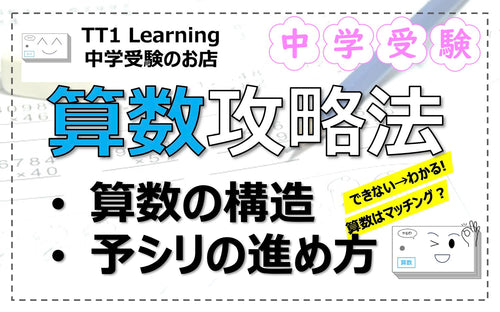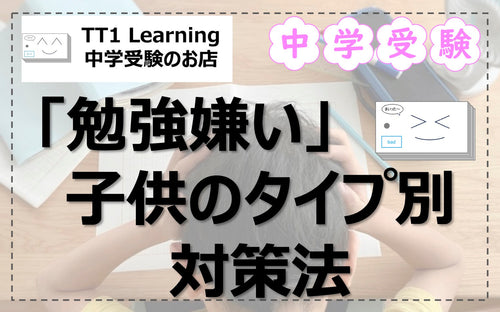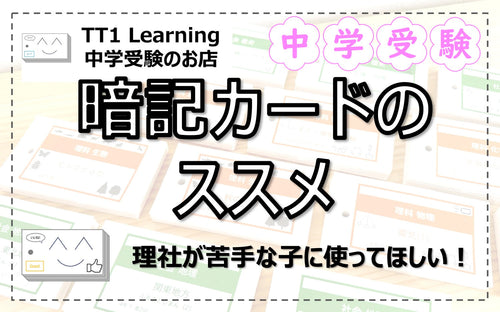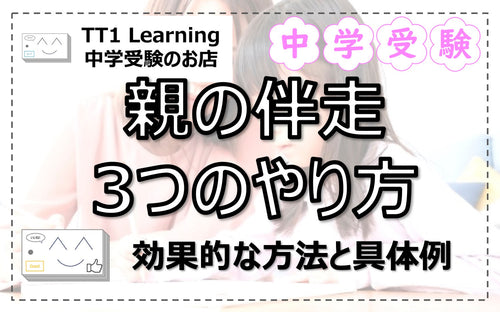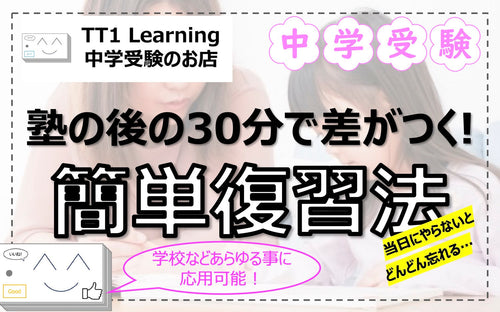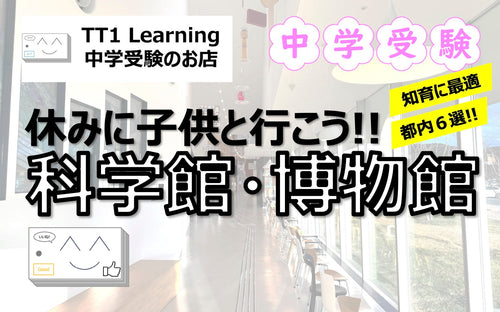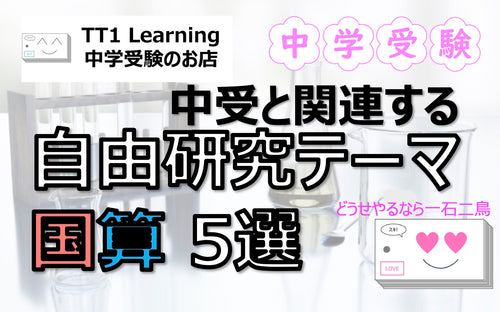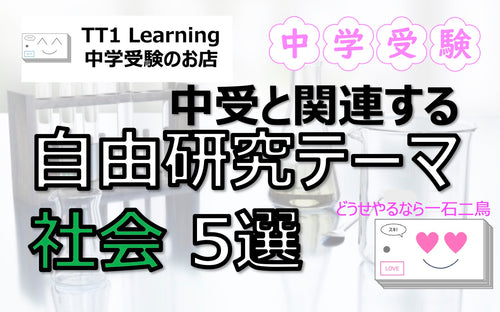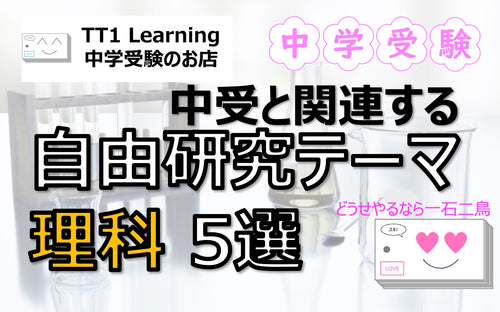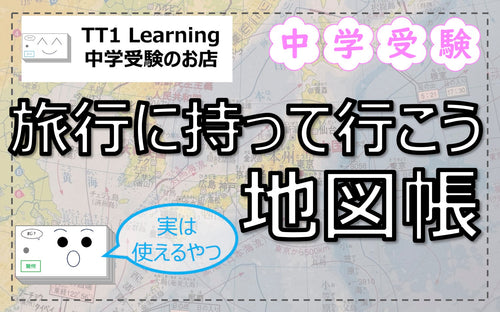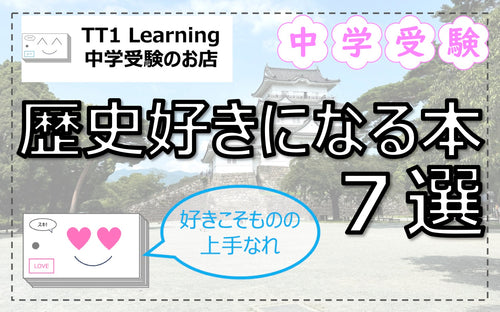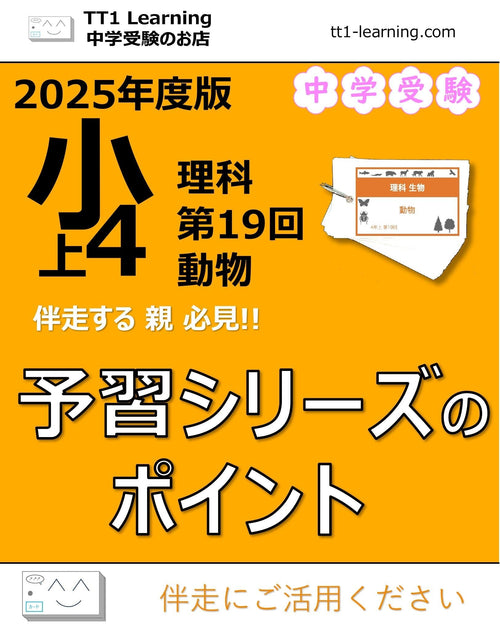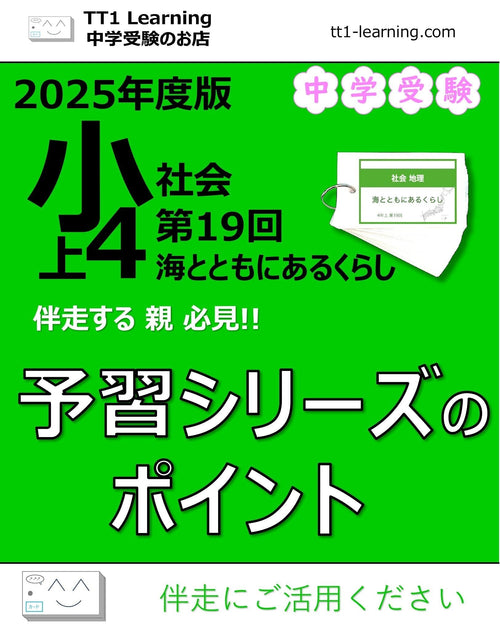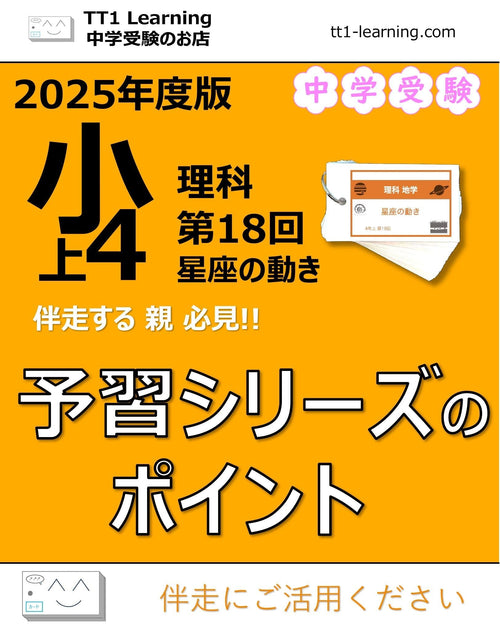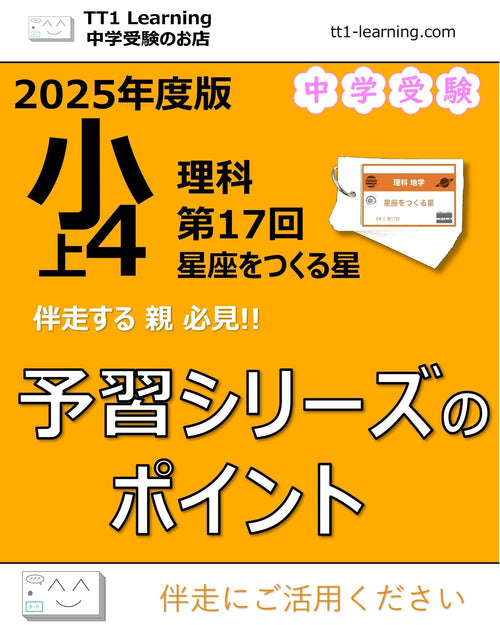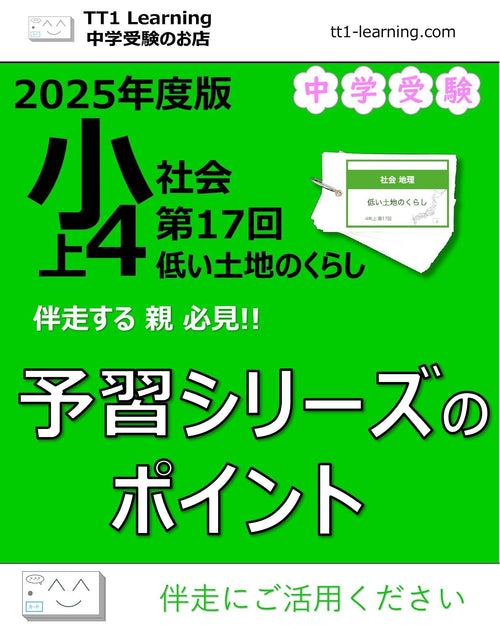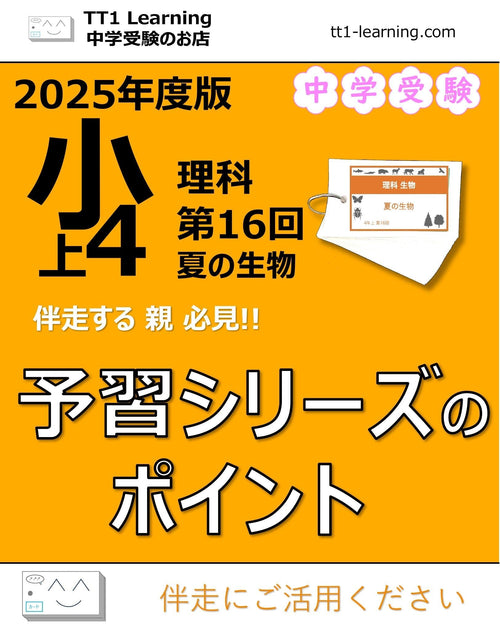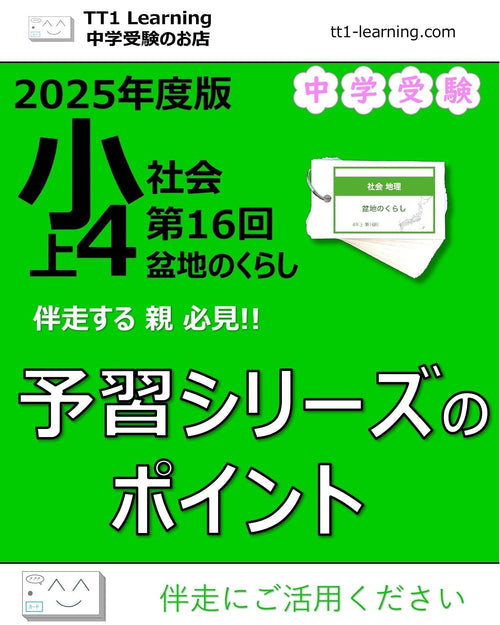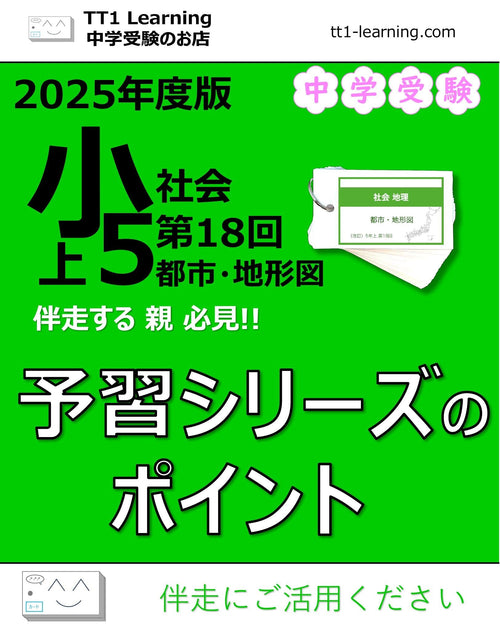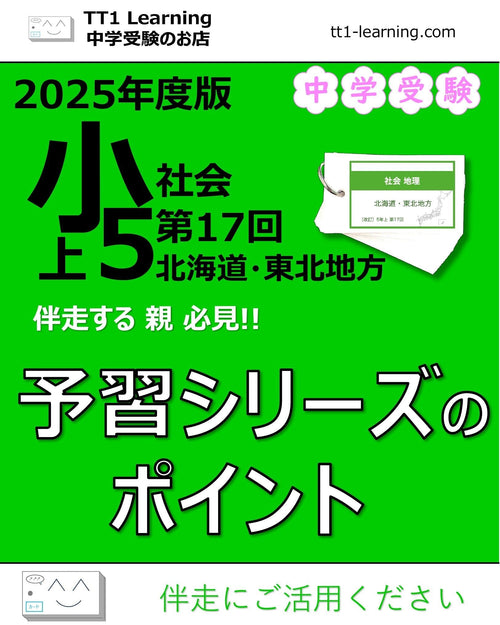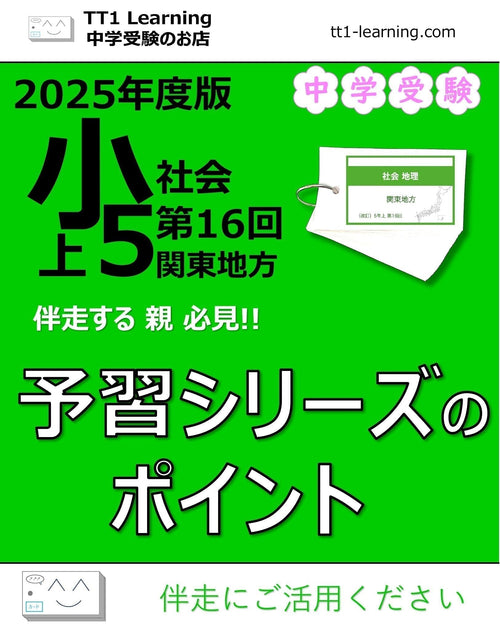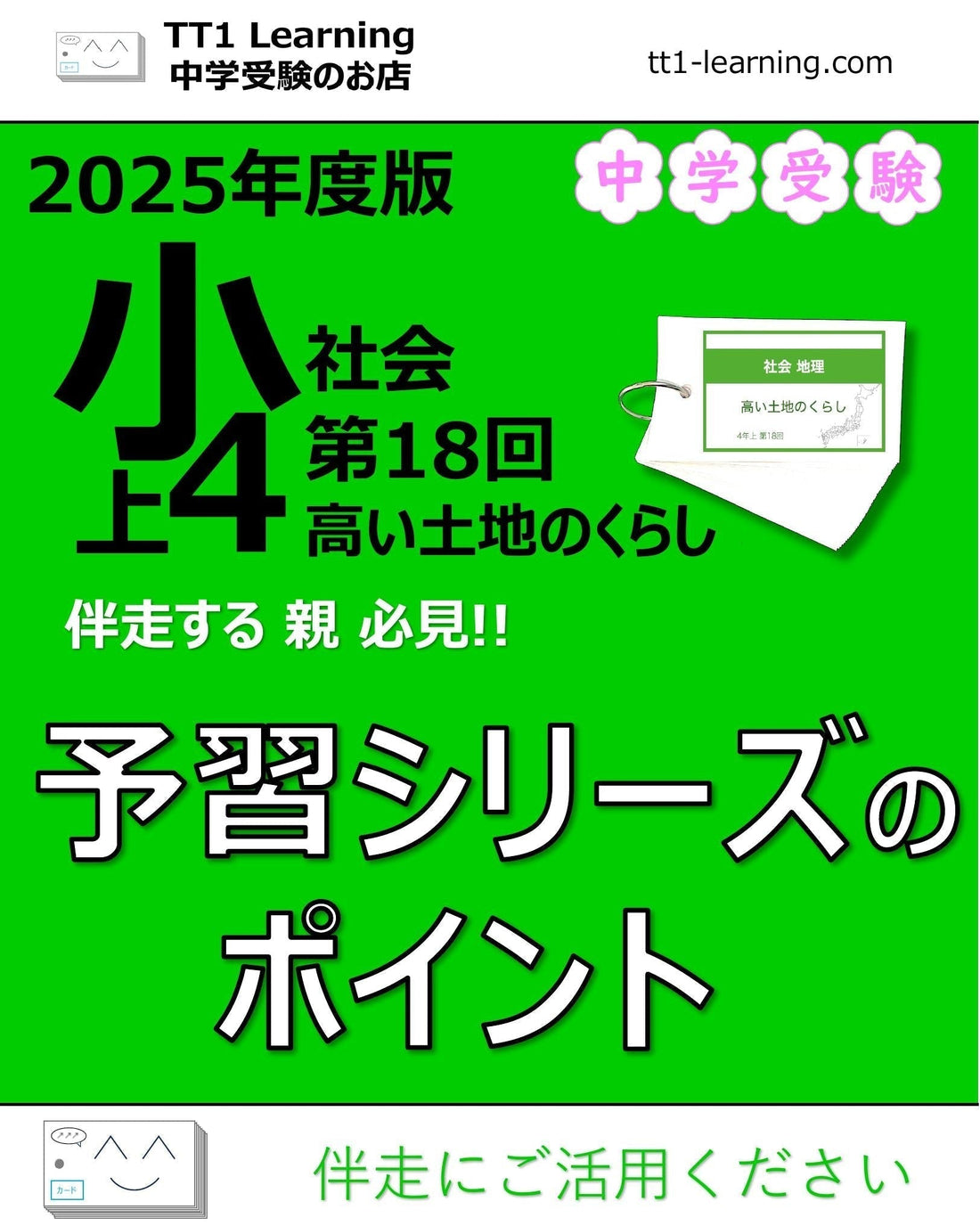
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 社会 第18回「高い土地のくらし(野辺山原)」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
共有
4年生社会予習シリーズ18回のテーマは「高い土地のくらし」。特に、長野県にある野辺山原(のべやまはら)を中心に学んでいきます。
標高が高い土地ならではの気候や自然条件、そしてそこに暮らす人々の工夫が詰まった単元です。高原野菜、酪農、観光、循環型農業など、いろいろな視点から地域を理解できる内容になっています。
親子で「高い土地ってどんなところだろう?」と一緒に考えながら進めると、知識がより深まり、楽しく学べるかも!
単元の概要
-
野辺山原の地形と気候
標高1200〜1600mの高地で、夏は東京より10℃ほど涼しい冷涼な気候が特徴。八ヶ岳の噴火による火山灰土で土地がやせており、水はけも良い。 -
農業(高原野菜と酪農)
戦後に土地を開拓して冷涼な気候を活かし、レタス、キャベツ、はくさいなどの高原野菜が栽培されています。酪農も盛んで、牛乳はヨーグルトやアイスクリームなどの乳製品に加工されています。酪農ででた牛のフンを肥料として再利用したり、配送ではコールドチェーンを発達させてきた - 観光と地域課題 夏は避暑地、冬はスキーやスノーレジャーの観光地としても有名。観光客が増える一方で、ゴミ問題や環境保全が課題となっています。
これらを総合的に理解することが、この単元の大きなポイントです。
野辺山原の全体像
野辺山原は、長野県の八ヶ岳のふもとに広がる高原地帯です。
標高が高い→すずしい気候
八ヶ岳の火山活動により火山灰土が広がる→土地が痩せて農業に不向き
この状況を戦後開拓者が尽力して農業をできるように改良しました。
その結果現在では
時期をずらした「高原野菜」が盛ん(コールドチェーン配送で新鮮なまま消費地へ運べる)
暑さに弱い牛の「酪農」が発達!
牛のフンを再度畑に戻して肥料として活用する循環型農業も定着
さらに夏は避暑地として、冬はスキーなどのレジャー地域としても発展してきました。
ただし、近年は観光客が出すゴミ問題が発生しています。

野辺山原の特徴
野辺山原は、長野県の八ヶ岳のふもとに広がる高原地帯です。
標高は日本有数の高さで1200m~1600mです。
このため東京都比較してすずしい気候になっています。東京と気温差を見ると約10℃程度違います!
野辺山駅はJRの中で最も標高が高い駅というのも覚えておきましょう!
八ヶ岳の火山活動が盛んで、この活動によりたくさんの火山灰土が降り積もっており、水はけが良い一方で養分が少なく、農業には不向きです。
このため開拓を実施して農業用地へと変化させました。

高原野菜と酪農の発展
戦後、多くの開拓者たちが野辺山原の荒地を開墾し、冷涼な気候を活かした高原野菜の栽培を始めました。
すずしい気候を生かして「高原野菜」と「酪農」が盛んです。
高原野菜としては、レタス、キャベツ、はくさいといった野菜の栽培が盛んで、夏でも涼しい気候の中で育つため病気に強く、食感が良いとされています。
他の地域で採れる時期が異なるため、全国に出荷され、高値で取引されることも特徴です。
酪農としては、野辺山の牛乳は味が濃く、ヨーグルトやアイスクリームなどの乳製品に加工されています。
牛のふんは肥料として再利用され、農地の栄養補給に使われるなど、循環型農業が実践されています。

農業の工夫
農業では栽培の工夫もたくさんされています。
苗植えを楽にするために「座って作業ができる台車」を使用するなど、体への負担を減らす工夫がされています。
また、畑には「穴あきフィルム」を敷き、病気の予防や雑草の抑制、地温の安定化を図っています。これにより、農作業の効率が向上し、収量の安定につながっています。
穴の空いたフィルムの利点をまとめると以下の通りです。
- 気温の変化に強い
- 土が風に飛ばされにくい
- 土が乾燥しにくい
- 歯の裏に土がつきにくい(植物の病気の発生の予防となります)
- 雑草が生えにくい
さらに、収穫後は「コールドチェーン」と呼ばれる冷蔵輸送システムを活用。
畑で収穫した野菜を低温のまま市場や店頭へ届けることで、新鮮さが保たれ、消費者に高品質な状態で届けられます。
このような工夫があるからこそ、野辺山原の農業は全国に誇れる品質を維持しています。
観光と地域課題
野辺山原は観光地としても人気があります。
夏は避暑地として、冬はスキーやスノーレジャーの拠点として、多くの観光客が訪れます。
特に夏の高原の涼しさは、都会の暑さに疲れた人々にとって大きな魅力です。
しかし、観光客の増加は地域に新たな課題ももたらします。
ゴミ問題や自然環境の保護など、持続可能な観光の在り方が問われています。地元では、観光と環境保全を両立させるための取り組みが続けられています。
学習のポイント
- 高地ならではの気候や土壌の特徴を整理する
- 農業や酪農がどうして発展したのか、その理由を説明できるようにする
- 観光のメリットとデメリットを比較し、環境保全の重要性を考える
- 地域の工夫(道具、循環型農業、冷蔵輸送など)を具体的に説明できるようにする
- 図や地図を活用し、視覚的に理解を深める
まとめ
高い土地のくらしは、厳しい自然条件と向き合いながら、さまざまな知恵と工夫で成り立っています。ただ覚えるだけでなく、背景にある理由や工夫の内容をしっかり理解することが、入試での得点アップにつながります。
親子で一緒に野辺山原の特産品を調べたり、地図で場所を確認したりすることで、楽しみながら知識を深めていきましょう!
暗記カードの活用法
- 短時間でも効率的に知識を整理できる
- 苦手分野の強化にピッタリ
- 親子でクイズ形式にして楽しめる
当社オリジナルの予習シリーズ準拠暗記カードは、今回の「高い土地のくらし」の要点をコンパクトにまとめています。スキマ時間にぜひ活用してみてください!
小4上期の予習シリーズのポイントの記事
社会
理科
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。