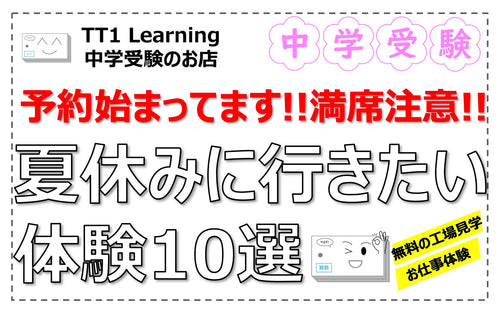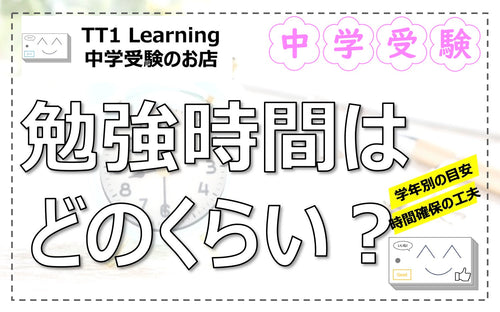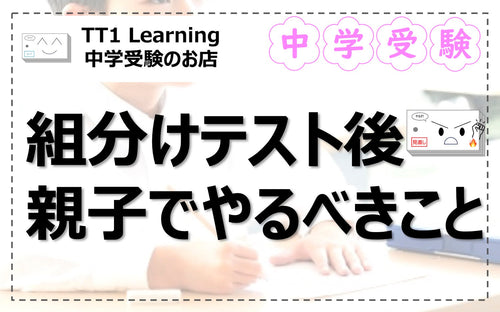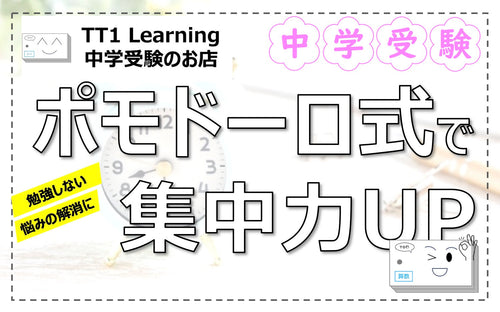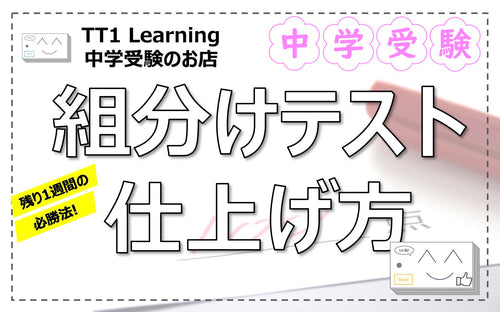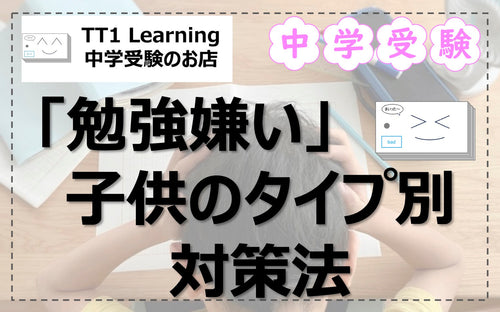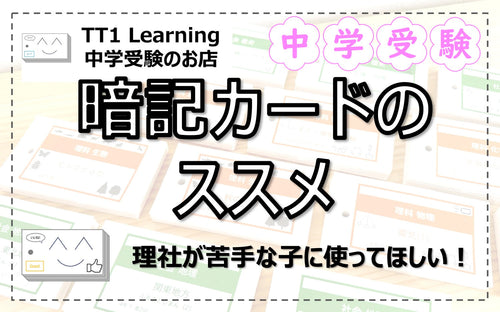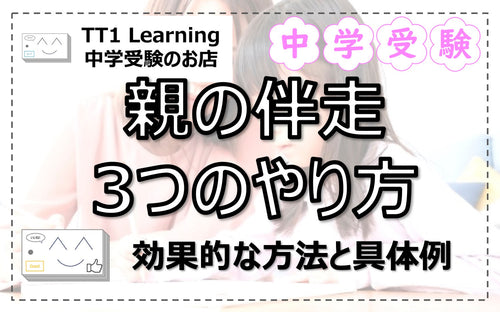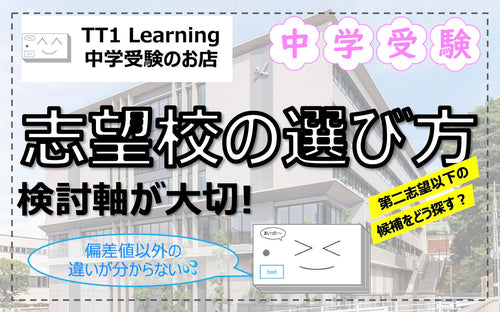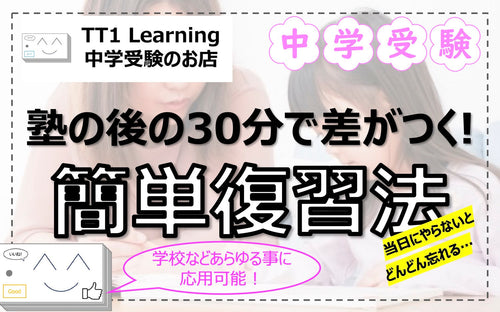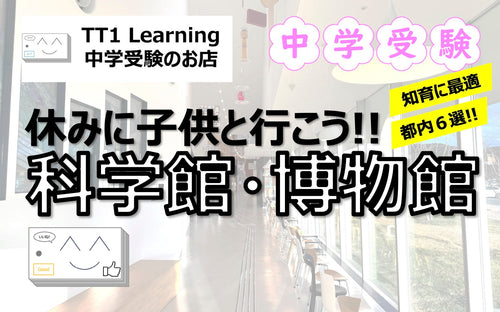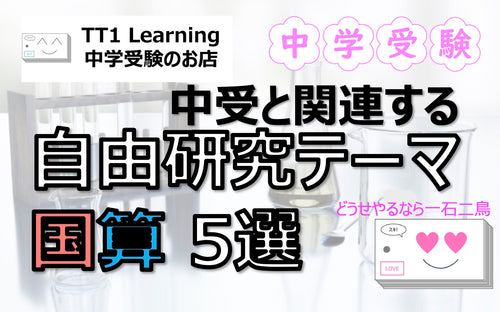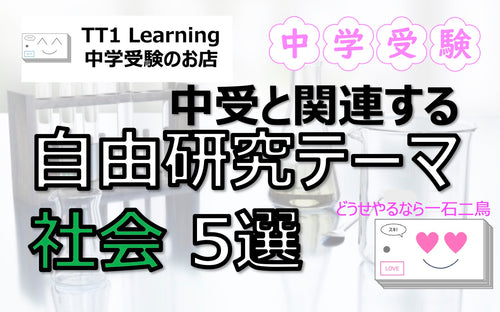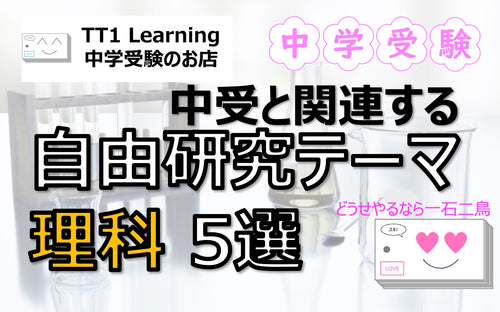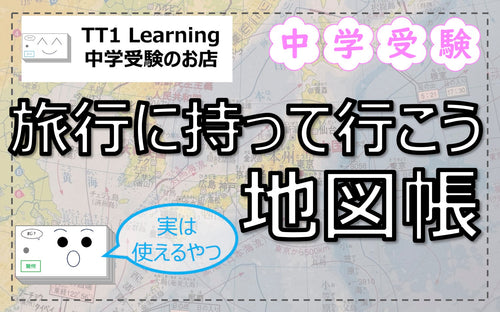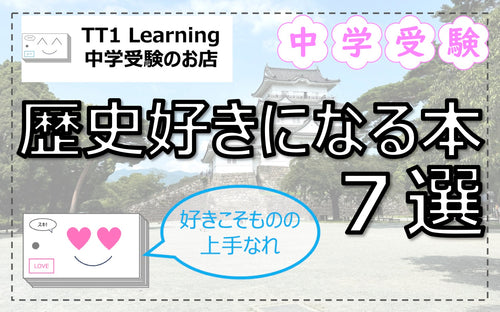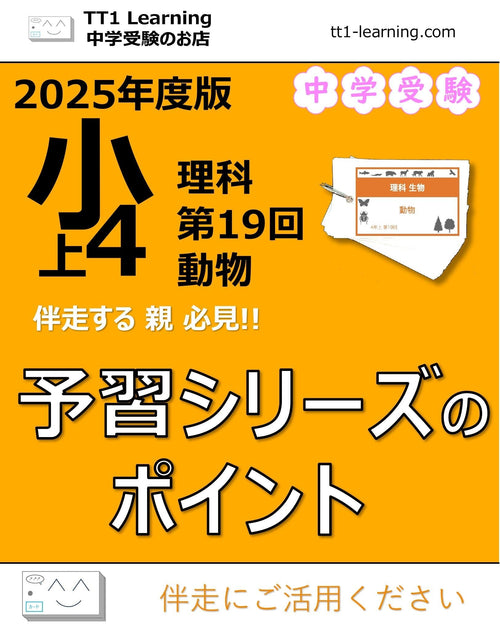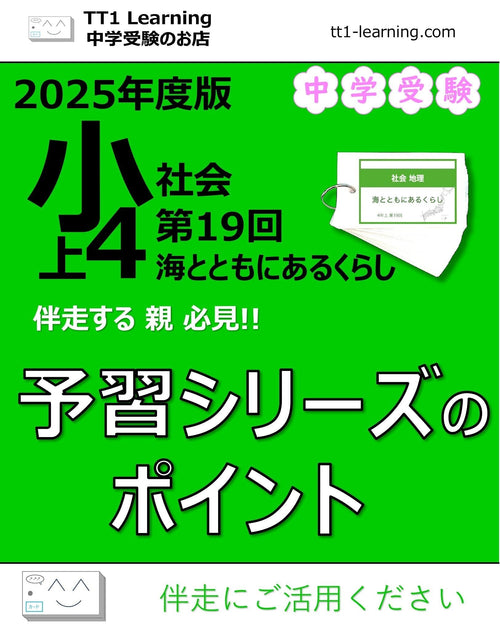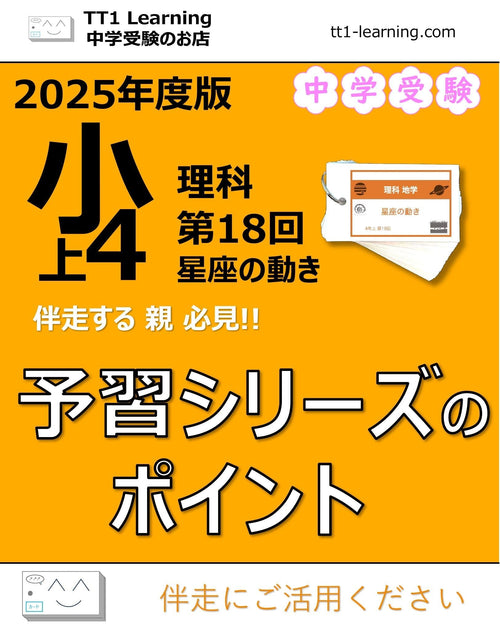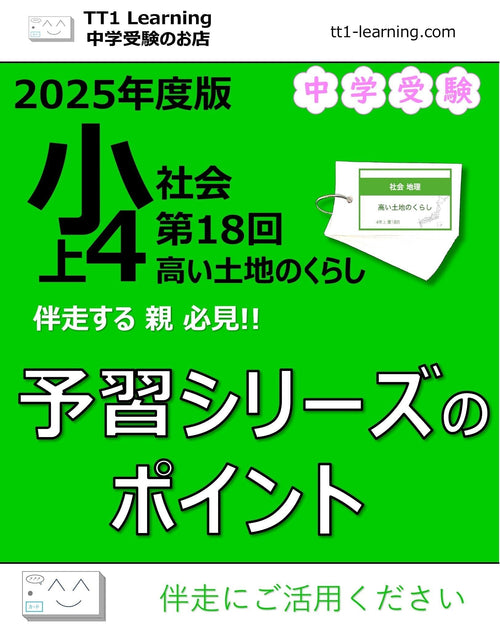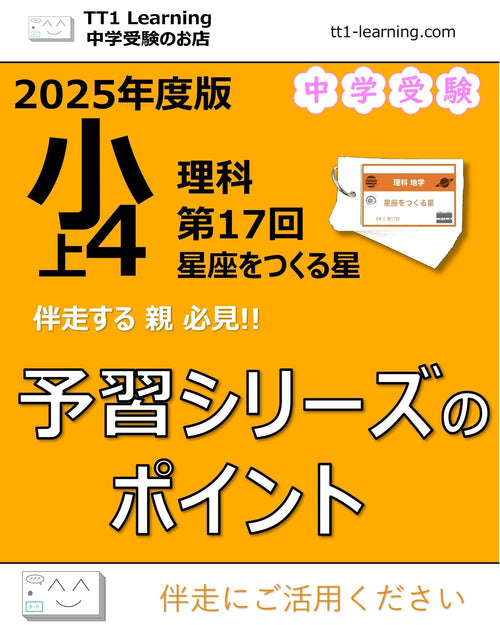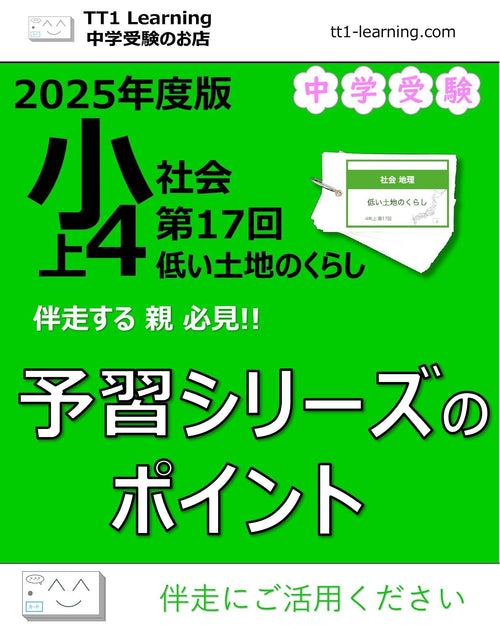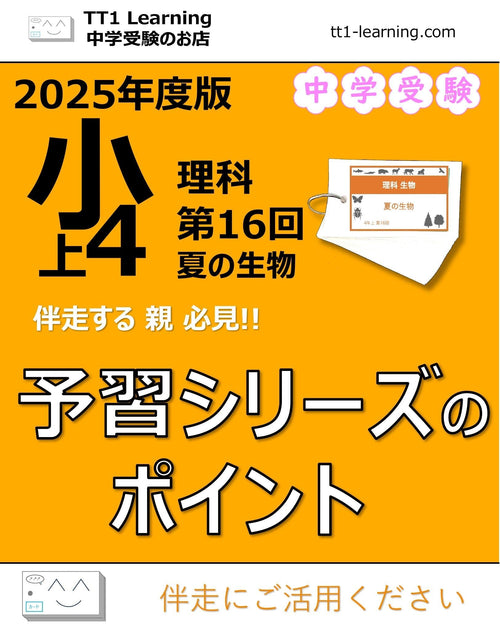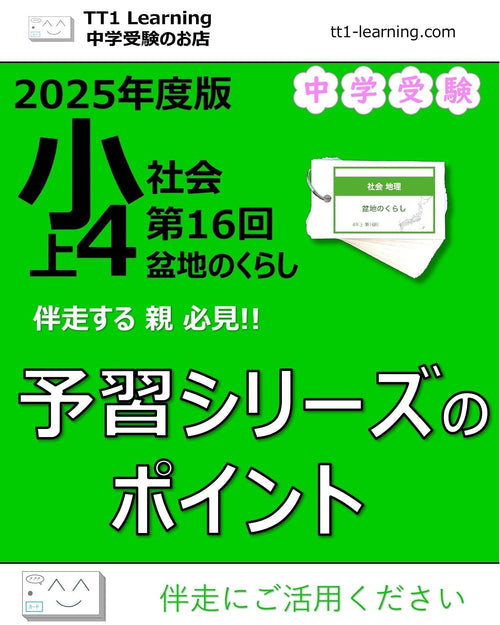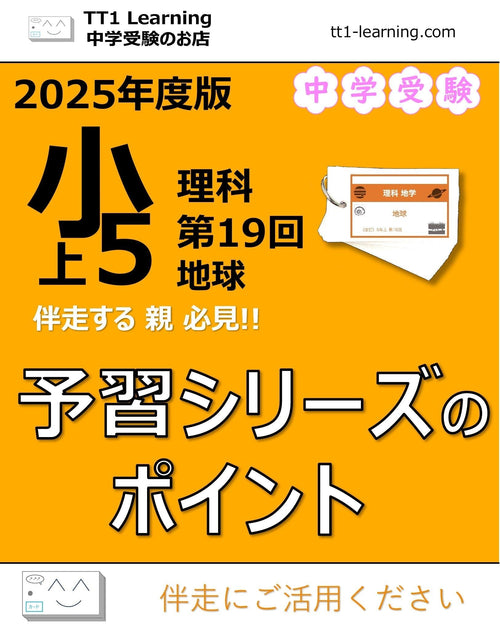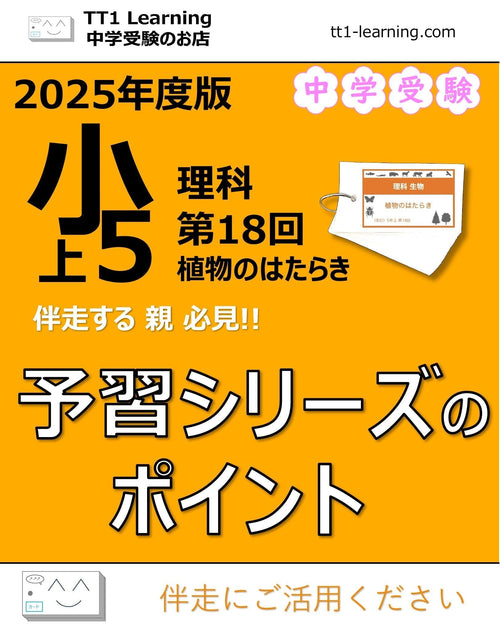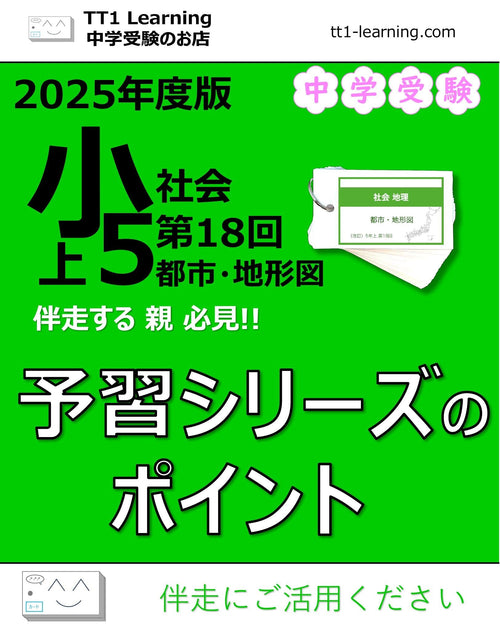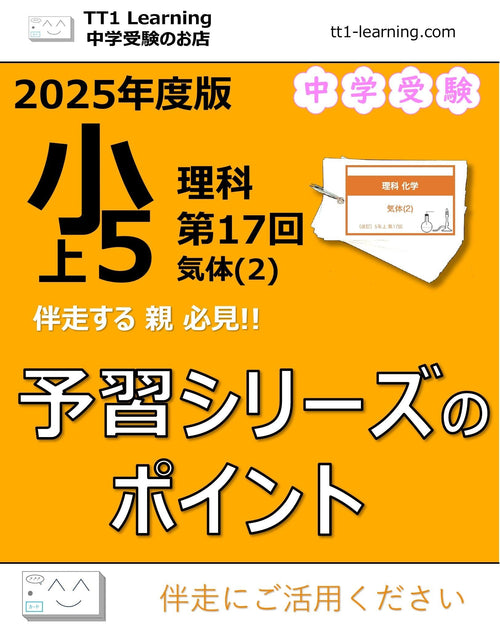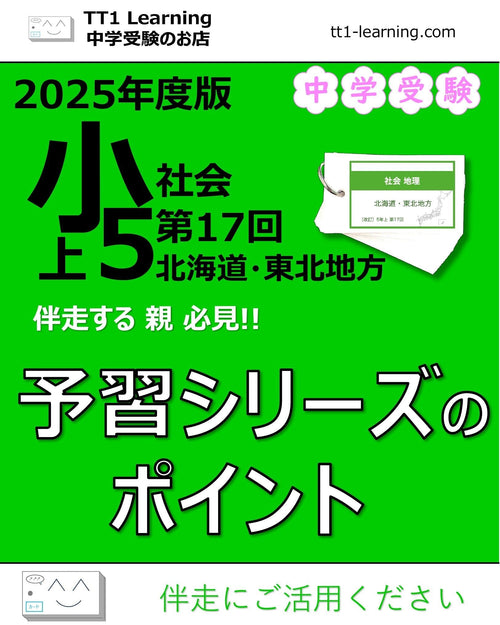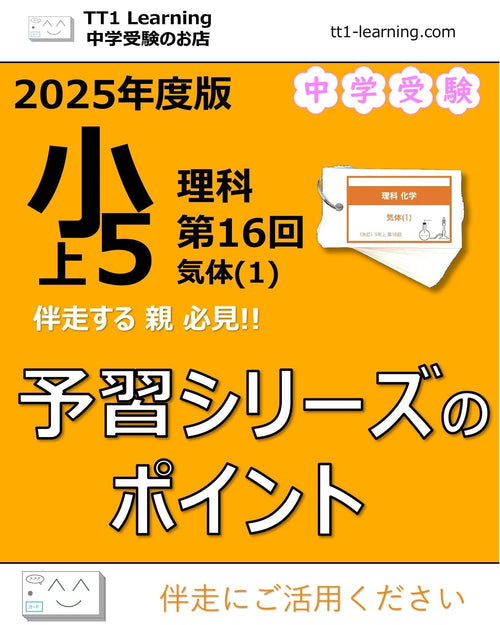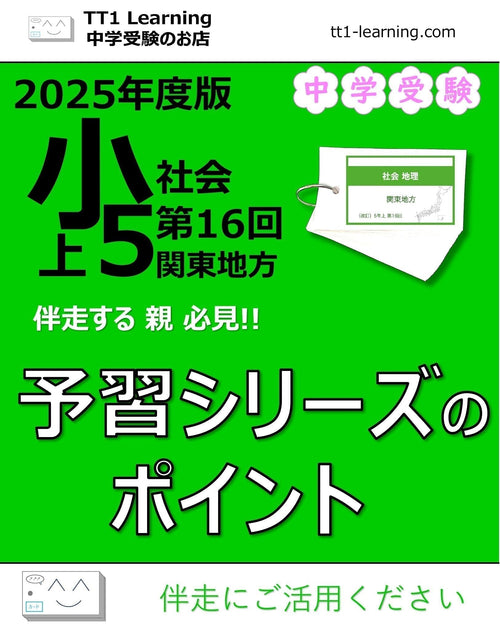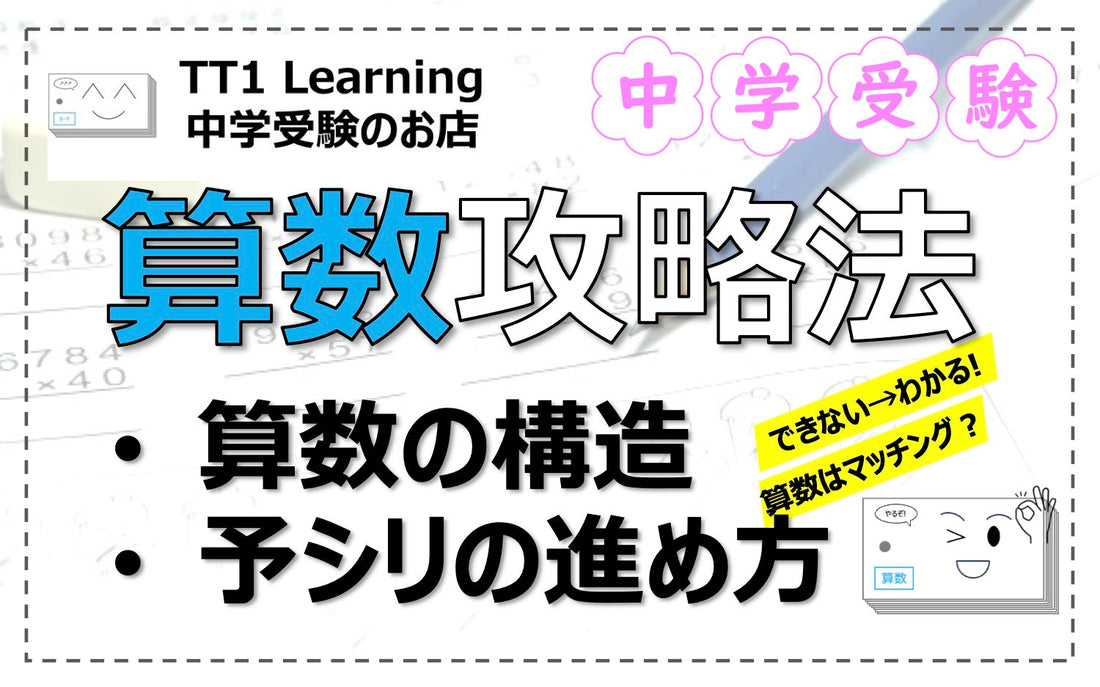
算数攻略法 「できない」から「わかる!」に変わる!予シリの使い方も解説
共有
「算数がとにかく苦手…」
「教えようとしても、なぜできないのかがわからない…」
中学受験を目指すご家庭で、こうした悩みを抱えている方は少なくありません。
でも、ちょっと考え方を変えるだけで、算数の“つまずき”は意外と整理できるかもしれません!!
今回は、算数が苦手な子が「できる!」に変わるために必要な考え方と、効果的な学習法についてご紹介していきます。
算数の本質は「問題と解法のマッチング」
算数って、パズルやゲームのような側面があります。
問題を読んで、「あ、このタイプならあのやり方かな?」と、頭の中にある“解法の引き出し”から選び出す。
つまり、算数の力とは、
- 解法を知っている(インプット)
- 解法を選べる(マッチング)
この2つの組み合わせなんです。

「解けない」ときは、
- そもそもその解法を知らない(=学習不足)
- どの解法を使えばいいか判断できない(=マッチング不足)
このどちらか。
よって、まず大切なのは、「解法そのものをしっかり覚えておくこと=暗記すること」。計算公式や基本の考え方を“引き出し”として準備しておくことで、問題に出会ったときにすばやく対応できるようになります。
難問には「2つの壁」がある
ただ、解法を暗記したら算数の問題がなんでも解けるようになるかというと、、
もちろんそうはならない。。
問題はどんどん難しくなります。
ただ、難しくなる方向性は主に次の2つの壁に区分けできます。

- 壁①:問われていることがわからない(=読解力、状況把握)
たとえば、「2人が同時に家を出て…」という旅人算の問題で、どちらの速さで何を計算すべきか混乱するケース。
あるいは、「円の中に三角形が入っている図形」で、どの長さや角度を求めるべきかが見えづらく、何を問われているのかがつかめない、といった状態です。 - 壁②:どの解法を使えばいいか思いつかない(=経験・パターン蓄積)
たとえば、「水そうに水を入れる」ような速さ×量の問題で、“比”を使うのか“割合”を使うのか迷う。あるいは、「1つの問題に2つ以上の解法を組み合わせる」必要があるとき、どれをどう組み合わせていいのかが判断できないケースです。
「難しい=理解力不足」ではありません。
つまずいた点が壁①なのか壁②なのかどこでつまずいているのかを明確にして、そこに応じた対処をしていくことが大切すす!
解釈力を鍛える3つの工夫
壁①の“読めない”問題を解決するには、
- 問題文を“自分の言葉”に言い換える(=何を聞かれてる?)
- 単元から逆算して「出るであろう解法」を予測する
- 絵・図にしてみる(=情報を視覚化)
といった工夫がおすすめです。
たとえば、「旅人算」とわかれば“速さ×時間”のどれが聞かれているかを探す。 図形問題なら、図を描いて関係性を整理する。
子ども自身が問題を“翻訳”できるようになると、読み解く力がぐっと育ちます。
解法の「組み合わせ」に慣れるには?
難しい問題ほど、1つの解法だけでなく“複数の解法”を組み合わせて解く必要があります。
この組み合わせ構築力を鍛えるためには、
- 解説を読んだ後、「どの解法がどう使われたか」を確認する
- 「割合系」「図形系」など、解法ジャンルを自分の中で分けて整理する
- 間違えた問題の「再分類ノート」を作る(どのタイプのミスだったか)
こんなふうに、1問1問を“パターンの見直し”の機会として活用しましょう。
日々の演習で出会った問題を、全部「解法データベース」の一部にしていく感覚です!
予習シリーズ(予シリ)の構成と使い方
四谷大塚などで使われている「予習シリーズ」
今まで解説した算数の構造を綺麗に対応できるように作られている優れた教材です!
- 単元の説明と例題では、「基本的な解法」を把握することができます
- 基本問題は、例題と同等、多少難しくした程度で、問題文の捉え方と解法の当てはめ方のマッチングの基本問題となっています
- 練習問題は、そこから難易度が上がっています。問題が複雑になっていたり解法を少し工夫したり複数作ったりしているものがあります。
- 応用問題は結構難易度が高くなります。
- 予習シリーズとセットの演習問題は、予習シリーズの問題・難易度に沿って作られているので、ヨシリでできなかった部分を中心にトレーニングとして使いたい教材です。
間違えた問題は、「どの解法を選べばよかったのか」に立ち戻る。
そして「似ているけど違う問題」と並べて、整理しておくと◎です。
おすすめ学習ルーチン(予シリ・演習活用)
それでは予習シリーズを使ってどのように学習していけば良いのでしょうか?
ここでは、予習シリーズをベースにした1単元の学習ルーチンを、「予習 → 授業 → 宿題 → 復習」の4ステップに分けてご紹介します。
STEP①:予習
- 目的:新しい単元の内容をざっくり把握し、「何を習うか」の見通しを立てる
- やること:例題(余裕があれば基本問題も)解いてみる、例題の考え方を一通り読み、どんな解法があるのかは習得する
- ポイント:完璧に解ける必要はなし!「使いそうな解法」「わからないポイント」のチェックが大事
STEP②:授業
- 目的:予習で見えにくかった部分の理解を深め、定着させる
- やること:授業中は「先生が何を強調しているか」を意識してノートを取る
- ポイント:「例題の解き方」「よく出るミス」などをメモしておくと、後の復習が効率的に
STEP③:宿題
- 目的:授業内容の理解度を確認し、実践力をつける
- やること:練習問題・演習問題を通じて問題↔︎解法のマッチングの精度を上げる
- ポイント:わからなかった問題は「何がわからなかったか」を明確に書き出す(計算ミス?解法の誤選択?)
STEP④:復習
- 目的:定着と弱点補強
- やること:間違えた問題を解き直す/使うべきだった解法を再確認/同じテーマの類題に挑戦
- ポイント:「できなかった問題ノート」や「解法カード」を使って、“見える化”&“反復”を習慣に
このように1週間を通してステップを意識して取り組むことで、解法がしっかりと定着し、算数の力が確実に積み上がっていきます!
まとめ:算数は“構造”と“戦略”で攻略できる
算数が苦手な子どもたちの多くは、「できない」のではなく「知らない」か「使えない」だけなんです!!
逆に言えば、正しい解法を知って、それを選べるようになれば、算数は必ず伸びます!
今日からできること:
- まずは“解き方”を暗記
- 間違えた問題のうち解法を知らなかったのか、問題文の解釈ができなかったのか分類して、自分の頭にある解法データベースを強化
- 繰り返し練習して問題と解法のマッチングの“精度向上とスピードアップ”を目指す
中学受験の算数は、積み重ねと整理で攻略できます。 あせらず、着実に。一歩ずつ進んでいきましょう!
さらに読みたい関連記事
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。