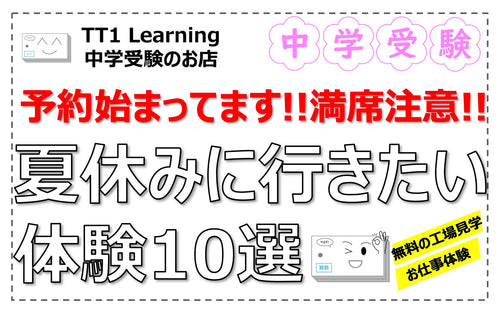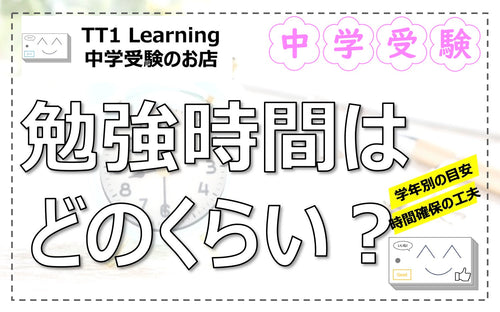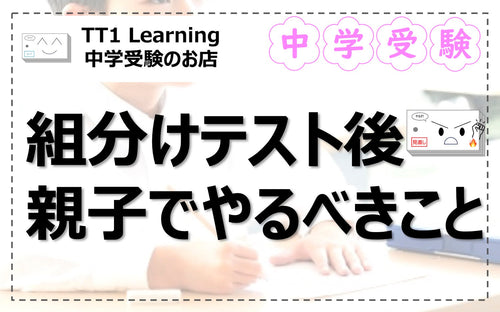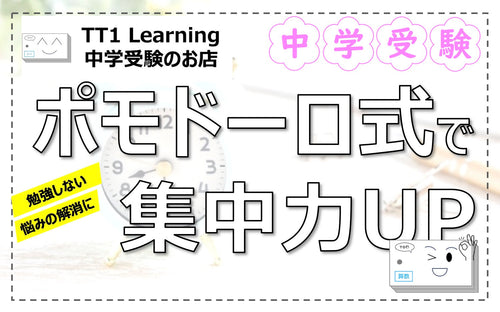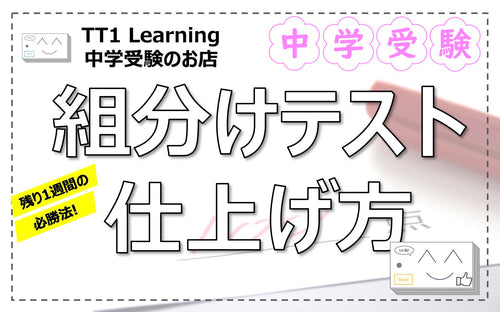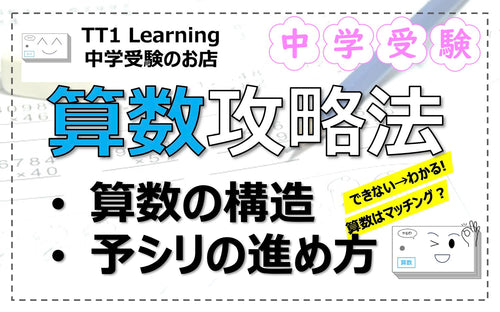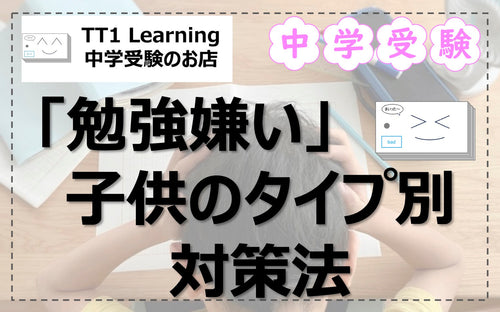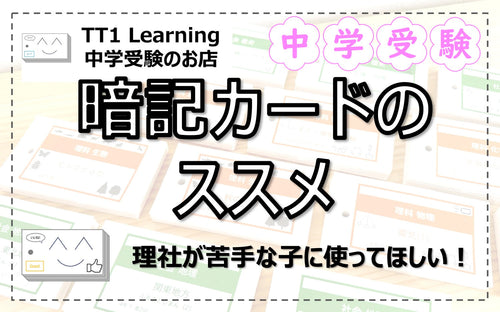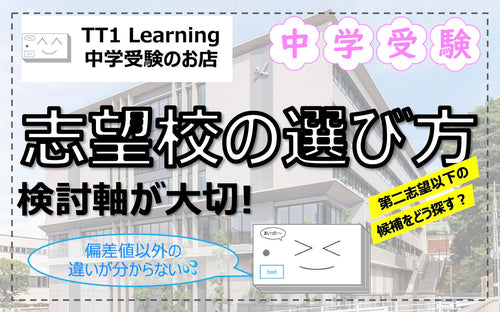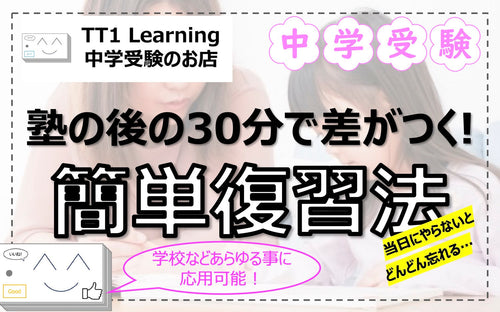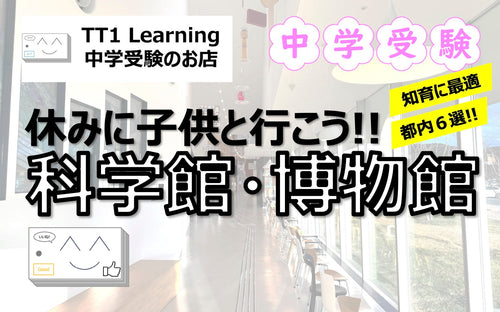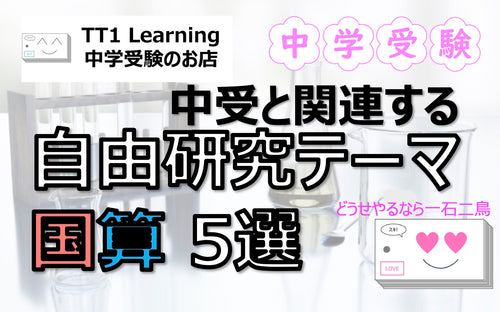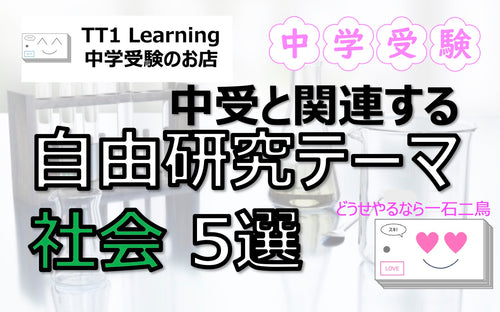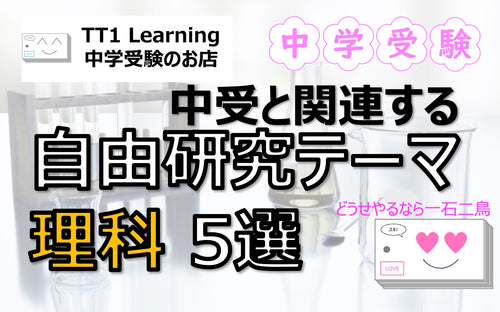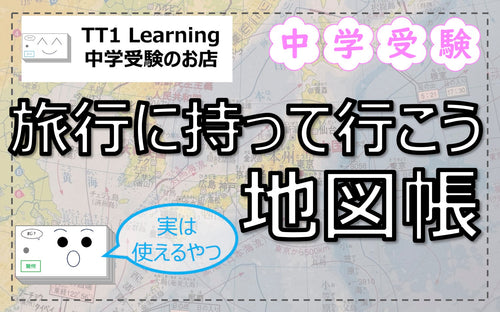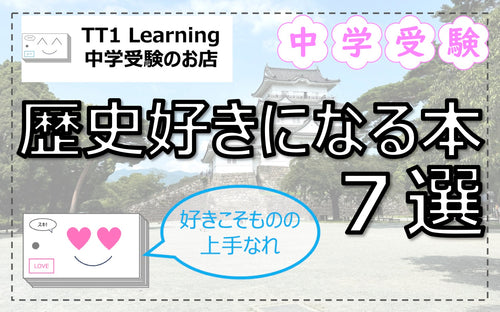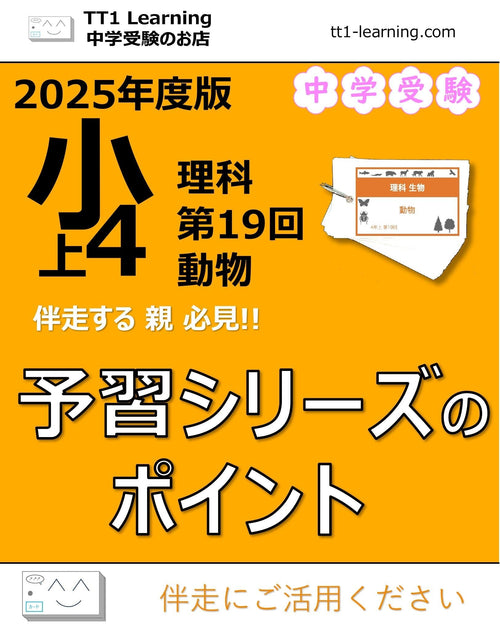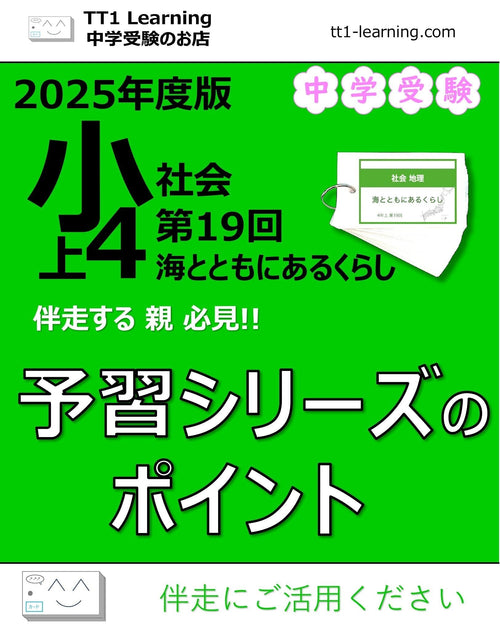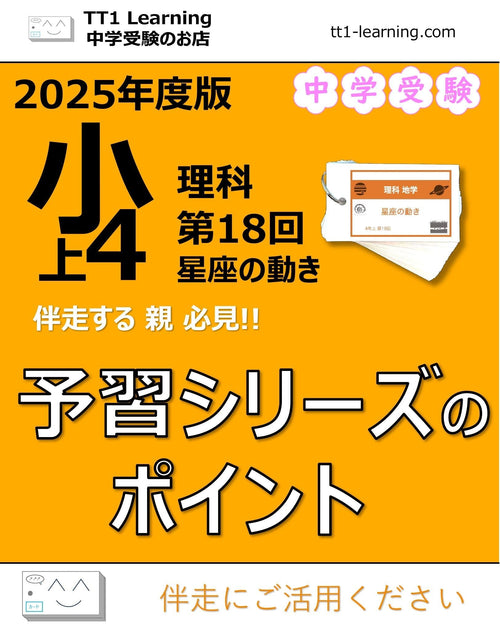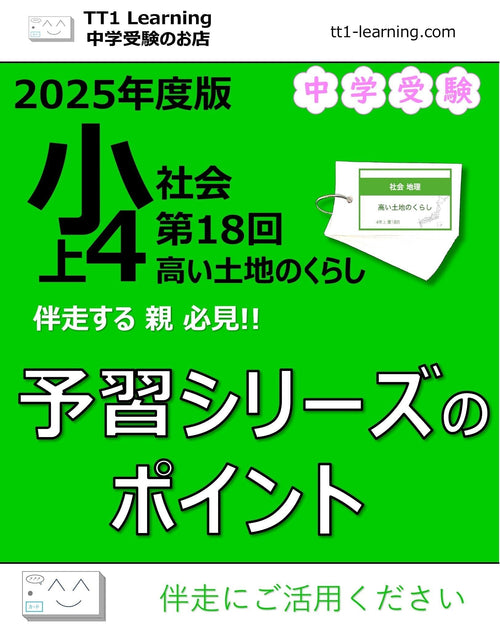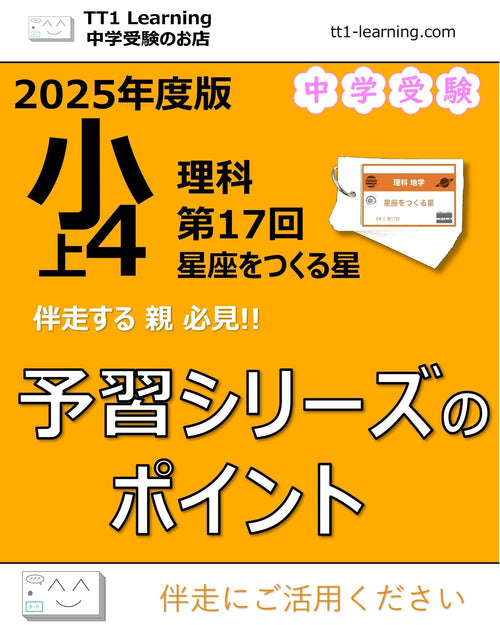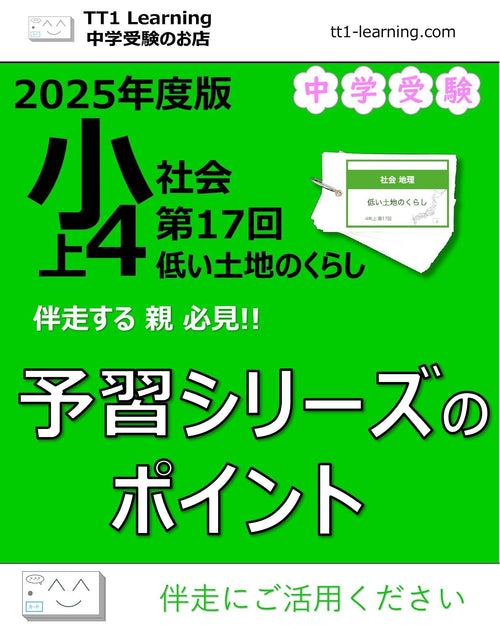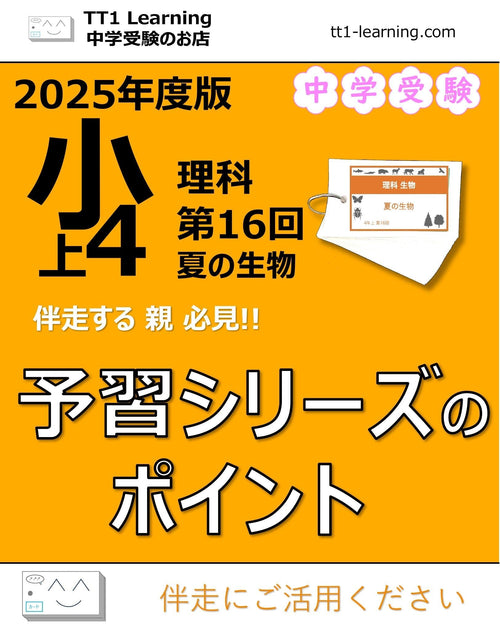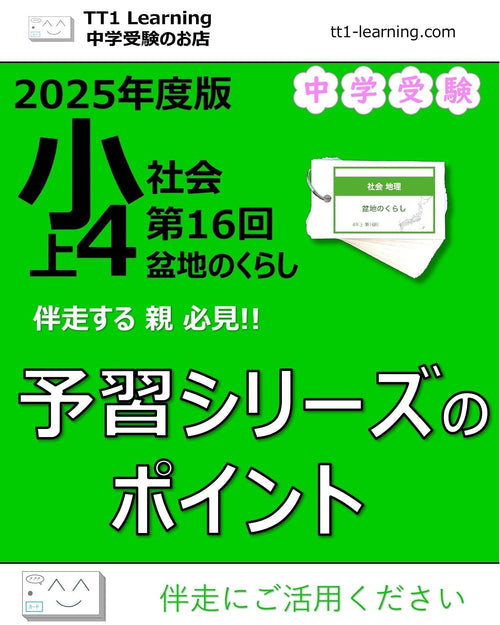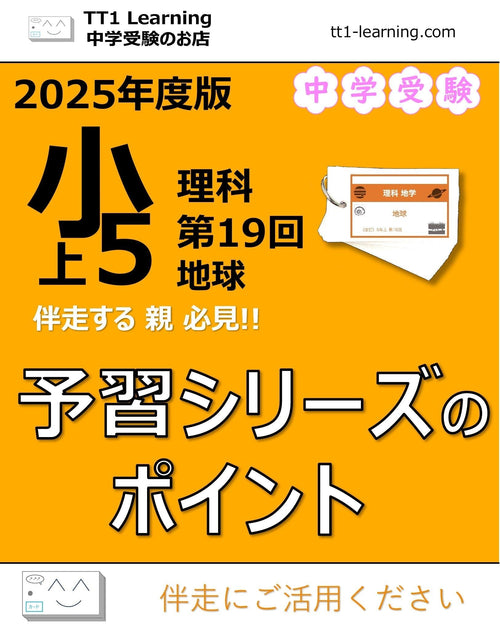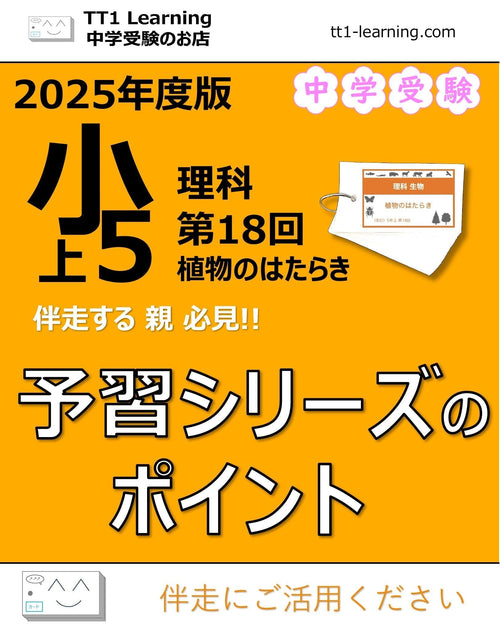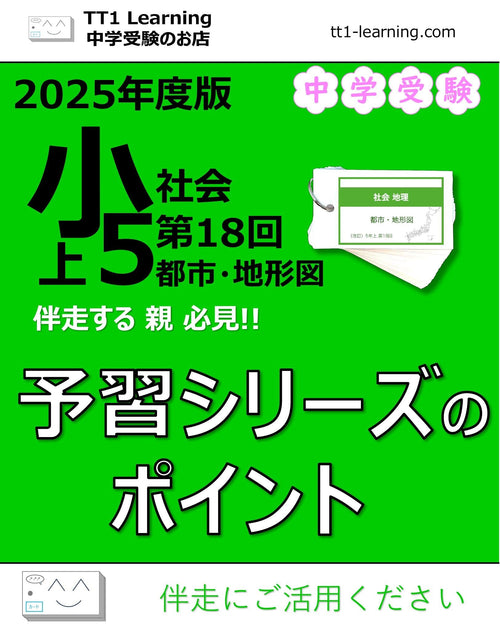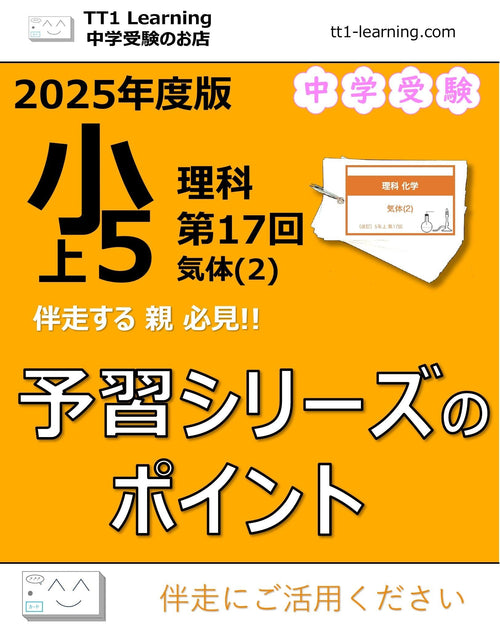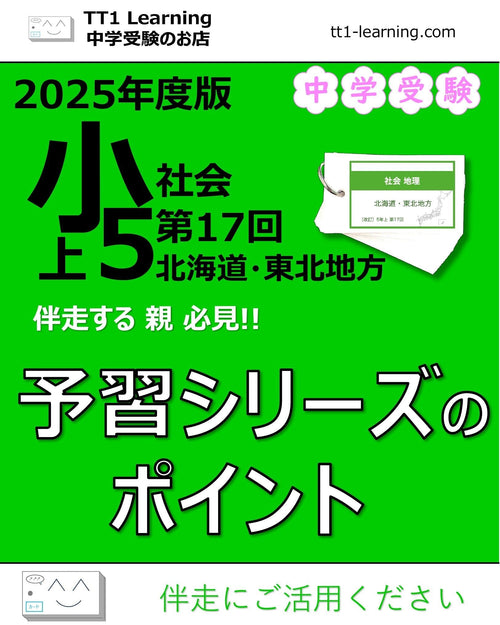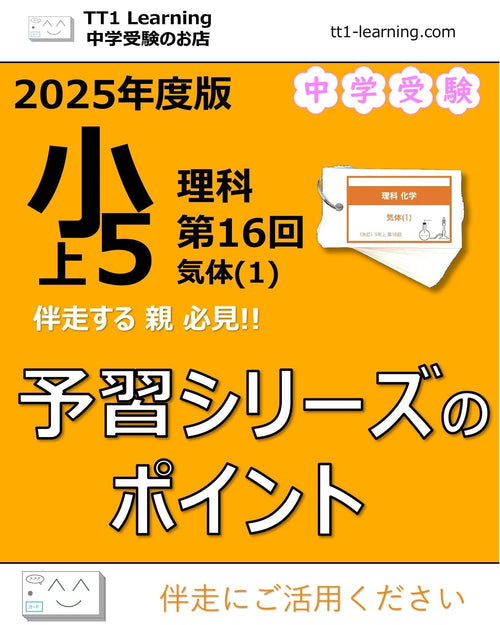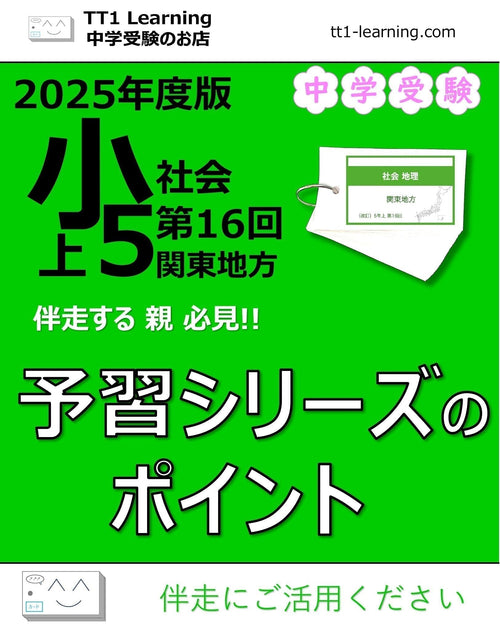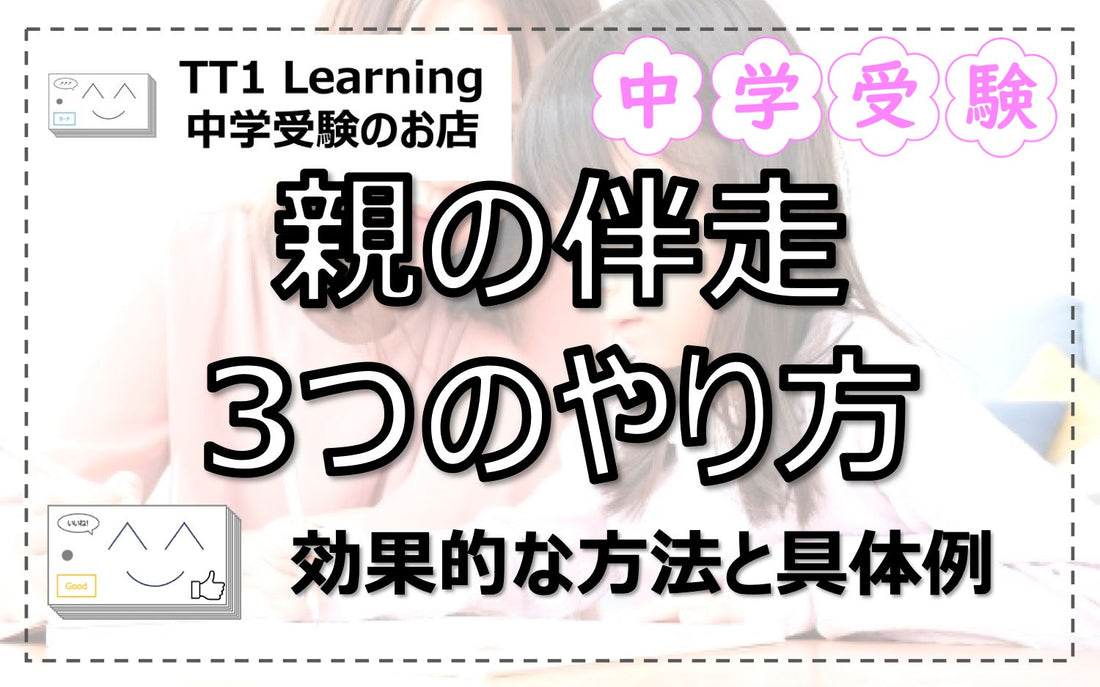
【中学受験】親の“伴走”がカギ!無理なくできる3つのサポート軸とは?
共有
中学受験は、子どもが主役。でも、それを支える親の関わり方もとても大切ですよね。「親の受験」とも言われるくらい、日々の生活や気持ちの支えが必要になるこの時期。「うちはどう関わればいいのかな」と悩まれているご家庭も多いと思います。
「全部やらなきゃ」「理想的なサポートをしないと…」とプレッシャーを感じている方もいるかもしれません。でも、完璧を目指す必要はないと思うんです。今できることを少しずつ、子どもと一緒に歩んでいく。その姿勢が何よりも大切です。
この記事では、そんな迷いや不安を抱える方に向けて、「親の伴走」をテーマに、無理なく・継続的に取り組める3つのサポートの軸をご紹介します。
「全部やろう」と思わずに、「これならできそう」と思えることから始めていきましょう。一緒に、できる形を見つけていけたら嬉しいです。
1. 伴走とは「全部やること」ではありません
子どもの勉強に関わるとき、「もっとこうすれば成績が上がるのに」「失敗させたくない」という気持ちが先に立って、つい手や口が出てしまうこともありますよね。
でも、伴走は“親が代わりに走る”ことではなく、“子どもと一緒に並走していく”こと。できないことがあっても大丈夫、一緒に頑張っていけばいいのです。
「すべてを完璧にこなす」のではなく、「自分たちにできる範囲でしっかり支える」。この視点を持つと、気持ちもグッと楽になります。
伴走の形は、家庭によってさまざまです。お仕事をしながらのサポート、兄弟姉妹の育児と並行しての関わり、ご家庭によってできることも違って当然です。
だからこそ、「親にできること」と「やらなくていいこと」を明確にし、自分たちのペースを大事にしていきましょう。
この記事では、伴走を3つの視点から考えていきます。
それは、
- 子どもが安心して勉強に取り組めるようにするための【環境】
- 前向きな気持ちを保つ【心】
- そして学習を支える適度な関わりである【勉強】
という3つの軸です。

以降でこの3つについて具体的に述べていきます。
2. 環境を整える:安心して勉強できる土台づくり
子どもが安心して勉強に向かえるようにするには、「勉強のやり方」よりもまず、「勉強しやすい環境」が整っていることが大切です。
リビングの机、寝る時間、おやつのタイミング、プリントの置き場――どれもほんの小さなこと。でも、その“ちょっとしたこと”が整っているかどうかで、子どもの集中力ややる気がグッと変わってくるんです。
身の回りをすっきり整えてみる
- 学習机の上に余計なものがないだけで、気が散りにくくなります
- よく使う文房具や辞書の場所が決まっていると、すぐ勉強に取りかかれます
- プリント類が山積みにならないよう、科目や日付ごとにファイル分けしてみましょう
おうちの中で「ここに座れば、自然と勉強モードになる」そんな空間をつくってあげられると理想的です。
時間のリズムも、環境のひとつ
- 朝起きる時間と寝る時間をだいたい一定にする
- 「塾から帰ったらお風呂→ごはん→10分だけプリント」など、流れをパターン化
“何をするか”だけじゃなく、“いつ・どの順番でするか”も決まっていると、子どもは安心して動けます。
「ごはんのあとに10分だけカードを見ようね」と、ミニ習慣をつくってみるのも◎です。
スケジュールの見える化で気持ちもラクに
「今週は塾が2回、習い事が1回、土曜は過去問の日…」
こんなふうに、予定が目で見える形になっていると、子どもも自分の時間の流れをつかみやすくなります。
- 予定をカレンダーに書き出しておく
- 「できたこと」にシールを貼る達成感ルーチンもおすすめ
大人にとっての“ToDo管理”と同じように、子どもにも「見える整理」は大きな安心材料になります。
毎日バタバタしていても、「ちょっと整えてみようかな」と思えるところから、無理なくはじめるのがコツ!!
環境が整うと、子どもは自然と勉強に向かいやすくなります。そして、家の中に“頑張れる空気”が少しずつ育っていくんです。
一緒に、整えるところから始めていきましょう!
3. 心を支える:気持ちを前向きに保つ小さな声かけ
受験期は、子どもにとっても、実は親にとっても“感情が揺れやすい時期”です。成績の浮き沈み、友だちとの関係、思うようにいかない悔しさ…。毎日の中で、ちょっとした不安やプレッシャーを、子どもたちは少しずつ感じているはず…
だからこそ、親の「心のサポート」がとても大切!!!
ではどう対応すれば良いか?
→「話を聞くこと」と「褒めること」のふたつをやるのがオススメです🎵
まずは、話を「聞く」ことから
「今日どうだった?」と声をかけたとき、返ってくる言葉は「ふつう」「まあまあ」だけかもしれません。でも、それでもいいと思います!
無理に聞き出そうとせず、「話したくなったときに聞くよ」のスタンスでいられると、子どもは安心します。
- 塾の帰り道で、「お疲れさま」とだけ言ってみる
- お風呂の時間や寝る前に、ぽつりと出た言葉を拾ってみる
そんな小さなやりとりが、子どもにとって“心の安全基地”になっていきます。
次に、「褒める」というより“見てあげる”こと
頑張ったこと、成長していることに気づいてあげる──それだけで子どもは嬉しいもの!!
- 「漢字のテスト、前よりミスが減ったね」
- 「宿題、今日早めに始められてたね」
- 「自分からノート開いたの、すごいなって思ったよ」
直接的に「えらいね!」と褒めるのが照れくさい時は、ちょっとした“気づき”を言葉にしてあげるだけで十分!!
「見てくれている」「わかってくれている」と感じることが、子どもにとっての自己肯定感の種になります。
話を聞く。頑張りに気づいて声をかける。
その積み重ねが、子どもの気持ちの土台になっていくこと間違いなし!
「今日はなんとなく静かだったな」そんな気づきでも立派なサポート。できるときに、できるかたちで、心に寄り添っていきましょう。
4. 勉強を見る:「必要な時にだけ」手を出す
「勉強を見てあげたいけど、どこまで関わればいいの?」
「教えるのが苦手で、逆にイライラしてしまいそう…」
私もそうでした。。周りにも結構多い印象です。
まず、塾に通っているなら、家庭での役割は“サポート”で十分と思います。専門はプロにしっかり任せましょう!
そしてそのサポートも、特別な知識や長時間ではなく、「できるときに、できる範囲で」
具体的には、
- 音読を聞いてあげる
- 計算問題を一緒にやってみる
- 暗記のチェック係になってあげる
- プリントの間違え直しを一緒に整理する
こうした小さな関わりが、子どもにとっては「ちゃんとそばにいてくれてる」という大きな安心感につながりますし「みられているからちゃんとやろう」という気持ちにもつながっていると思います。
教え込むのではなく、あくまで“寄り添う”。できたら一緒に喜ぶ、つまずいたら一緒に「次、どうする?」と考えてみる。そうやって、一緒に学習を進めていけたら素敵ですよね。
勉強が苦手な子ほど、「わかってもらえる」「応援してもらえる」という気持ちが、次のやる気に変わっていきます。
暗記カードは“寄り添う勉強”の味方
短時間でも取り組めて、スキマ時間に最適な暗記カード。親子で交互に問題を出し合うだけでも、自然と復習が進みます。
- 「お!覚えてた!すごい!」
- 「惜しい〜!あとちょっと!」
そんなやりとりの中で、笑顔が生まれて、学ぶことが“楽しい時間”に変わっていくことも。
➡ 親子で楽しく使える「暗記カード」はこちら
5. 忙しい家庭こそ、役割分担を味方にする
「毎日、やることが山積みで時間が足りない…」「下の子の面倒もあるし、全部は無理…」
そんな声、たくさん聞きます。本当にお忙しい中、日々を回しているだけでも素晴らしいことです。
だからこそ、全部を一人で背負う必要なんてないんです。中学受験は“チーム戦”。家族みんなで、できる人が、できるときに、できることを少しずつやっていければ大丈夫です。
ここでは「役割分担」と「ルーチン化」という2つのポイントを、伴走の3つの軸(環境・心・勉強)ごとに分けて、実例を交えながらご紹介します。
環境づくりの分担・ルーチン化の例
役割分担:
- パパが朝の体調チェックや持ち物確認、ママが夜の就寝・食事サポート
- 祖父母が塾の送迎を手伝ってくれることも心強いですね
ルーチン化:
- 「帰ってきたらランドセルからプリントを出す」
- 「勉強する前に机を整える」など、生活の流れに組み込んでしまうとラクです
気持ちを支える分担・ルーチン化の例
役割分担:
- ママが「共感して聞く役」、パパが「元気づける声かけ役」など、役割を意識すると気持ちのフォローがしやすくなります
ルーチン化:
- 「寝る前に今日頑張ったことを1つ言い合う」
- 「週末の夜は親子で一週間を振り返る会話タイム」など、安心できる時間を定例化してみましょう
勉強サポートの分担・ルーチン化の例
役割分担:
- 平日はママが音読係、土日はパパが過去問の答え合わせなど、「できるタイミング」で分け合うだけでもぐっとラクになります
ルーチン化:
- 「朝10分だけ暗記カードを使って復習」
- 「週1回、間違えた問題をふせんに書き出して壁に貼る」など、小さな“繰り返し”が力になります
何より大切なのは、“家庭のペースに合った方法”を見つけること。
他の家庭と比べる必要はありません。あなたのご家庭らしいスタイルを、家族みんなで話し合って決めていけたら素敵ですよね。
ちなみに、暗記カードはルーチン化しやすいアイテムのひとつ。
毎日○枚だけ見る、親子でクイズ形式にして遊び感覚で取り入れるなど、無理なく続けられる工夫がたくさんあります。
➡ 短時間で復習できる「暗記カード」活用はこちら
6. 受験直前の伴走:自信と安心を与えるだけでいい
受験日が近づくと、親も子どもも緊張感が高まってきますよね。
「このままで本当に間に合うのかな?」「もっとやらせた方がいいのでは?」そんな不安が頭をよぎる時期です。
でも、この直前期こそ、“勉強量”よりも“気持ちの安定”が何よりも大事。
子どもたちはもう、たくさんの知識や経験を積んできました。あとは、その力を落ち着いて出せる状態に整えてあげることが、私たち親の役割です。
直前期の伴走のポイントは「安心」と「自信」
この時期に心がけたいことは、たった2つ。
- 焦らせないこと
- 自信を持たせること
子どもは、大人が思っている以上に親の雰囲気に敏感です。
親が焦っていると「なんだか大変なことになってるかも」と不安になり、自分の力を信じられなくなってしまいます。
だからこそ、「いつも通りで大丈夫」「これまで頑張ってきたことが力になるよ」といった言葉で、落ち着いた空気を作ってあげたいですね。
知識の詰め込みより「やってきたことの確認」を
- 新しい問題集よりも、これまでに解いてきたプリントや模試の見直しを
- 「ここはもう大丈夫だね」と、できているところに目を向ける
- 「間違えた問題」より、「正解できた問題」の方を一緒に振り返る
“できていること”を確認することで、子どもの表情が明るくなっていきます。自信は、過去の成功体験の積み重ねから育っていくんですね。
暗記カードは、直前期にもぴったりのツール
- 時間がない中で「効率よく」復習したいとき
- 移動中や寝る前の“ちょっとした時間”で復習したいとき
- 自分の弱点をサクッと見返したいとき
こんなときに、暗記カードは本当に頼れる存在になります。
特におすすめなのは、親子で1問ずつ交互に読み合うこと。
「お、覚えてた!」「惜しい〜!」と、ちょっとゲーム感覚で取り組むと、リラックス効果もあって◎です。
➡ 弱点整理や直前復習に最適な「暗記カード」はこちら
「ちゃんとできるかな…」と心配になったら、「一緒に乗り越えてきた時間があるから大丈夫」と、親自身に言い聞かせてみてください。
お子さんの力は、きっと当日に花開きます。
そして、となりで支えてきたあなたの存在が、その背中を大きく押しているはずです。
まとめ:親の伴走は“完璧”じゃなくていい
ここまで、親の伴走について「環境」「心」「勉強」の3つの軸でお話ししてきました。
正解は一つじゃありません。
家庭の数だけ、伴走のスタイルがあっていいんです。
- 家の中をちょっと整えてあげる「環境の伴走」
- 子どもの気持ちにそっと寄り添う「心の伴走」
- 少しだけでも一緒に学習する「勉強の伴走」
どれも、“完璧”を目指す必要はありません。
少し手を添えるだけでも、子どもは「見てくれてる」「応援してくれてる」と感じて、力が湧いてきます。
できることから、少しずつ。一緒に走り続けましょう
親だって、不安になる日や疲れる日がありますよね。
だからこそ「今日はここまでで十分」「これだけできた自分を認めよう」と、親自身の心にも優しくあってほしいと思います。
お子さんと一緒に悩んだり笑ったりしながら、二人三脚で進んでいく――
それが“伴走”の本当の姿なんだと思います。
大丈夫。今日できることが、明日につながっていきます。
最後に:暗記カードも、そんな伴走のひとつに
家庭学習での声かけやサポートに、暗記カードを取り入れているご家庭も増えています。
- 苦手を整理して、見える化する
- 復習を時短で済ませる
- 親子で一緒に確認して「できたね!」と共有する
こうした小さな積み重ねが、子どもの「やれるかも」という気持ちにつながっていくんです。
➡ 伴走にぴったりの「暗記カード」はこちら
あなたの家庭に合ったやり方で、無理なく、あたたかく、受験の日々を乗り越えていきましょう。
これからも、応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
さらに読みたい関連記事
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 四大塾比較|どの塾がうちの子に合う?徹底解説 → サピックス・日能研・四谷大塚・早稲アカの特徴を比較。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。