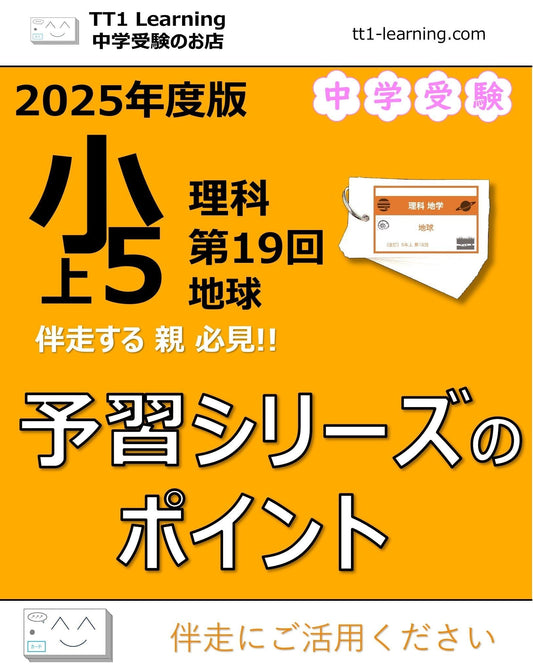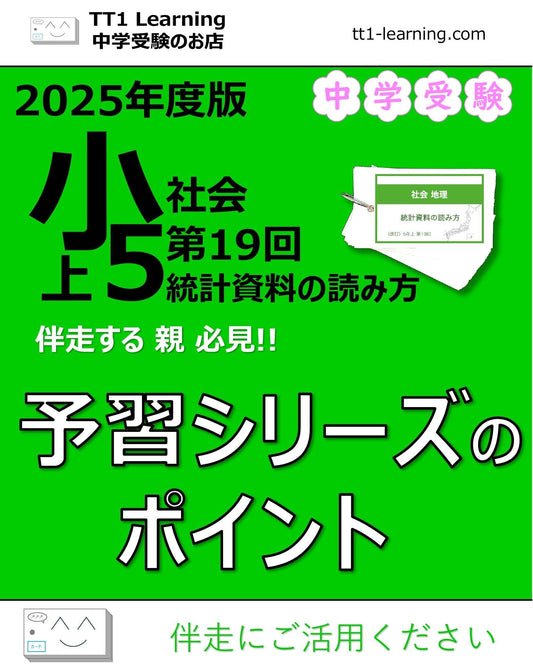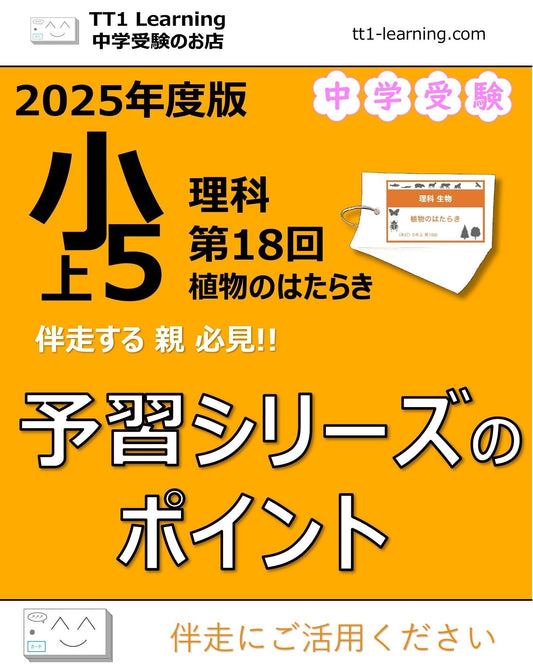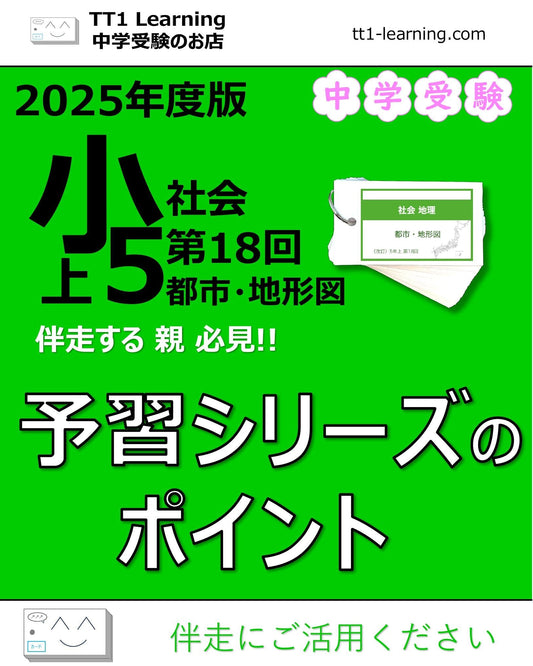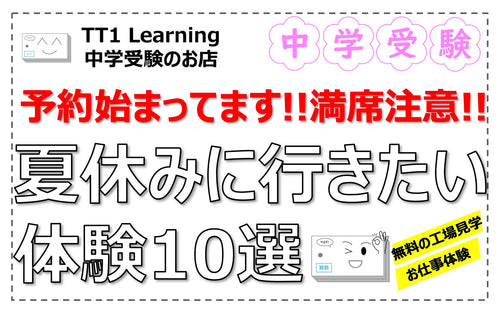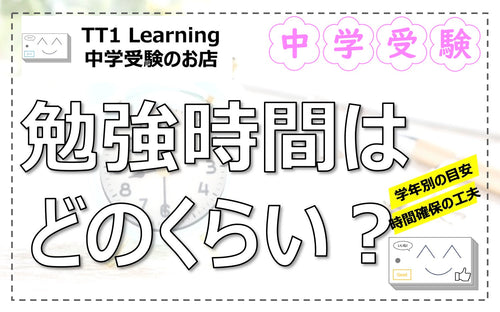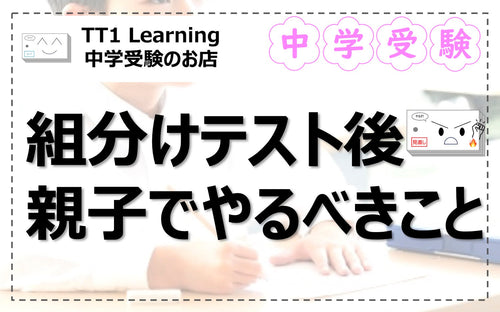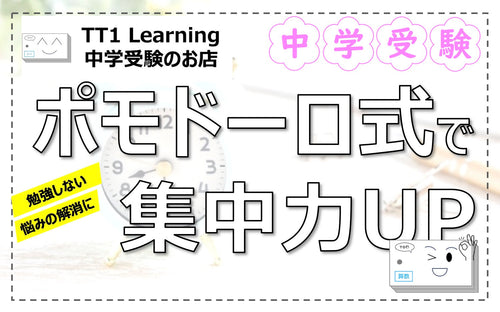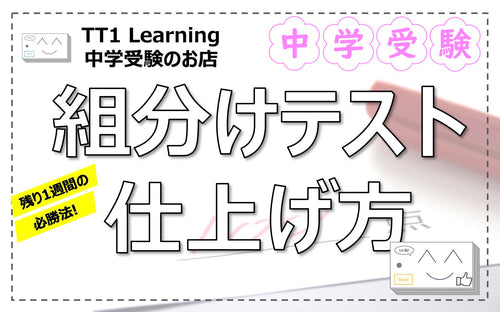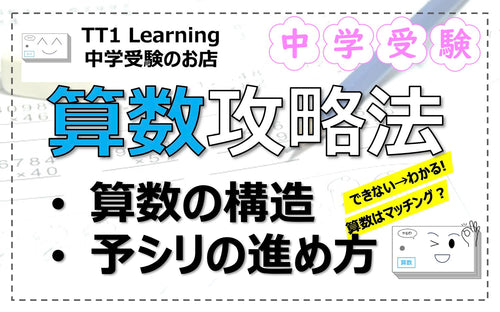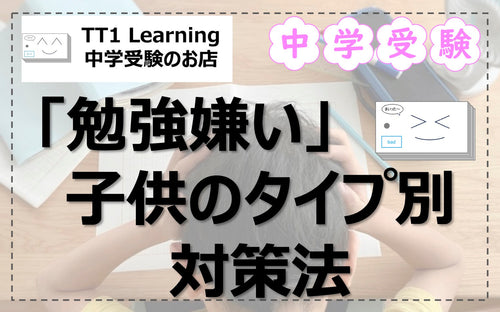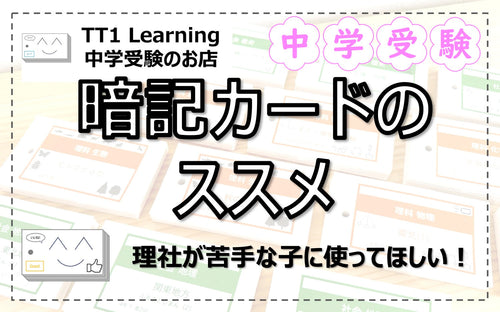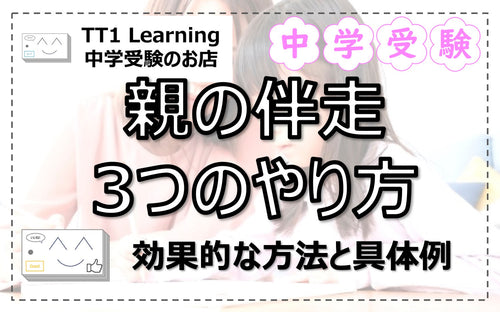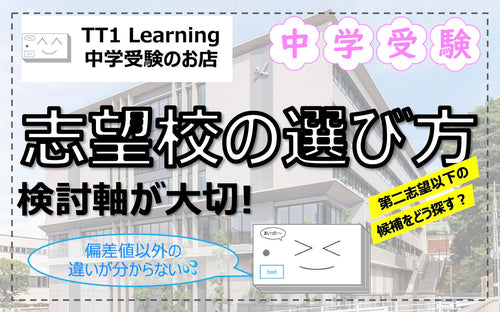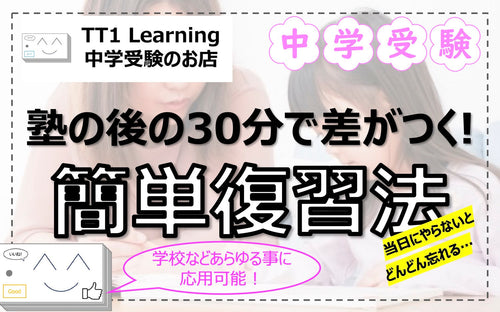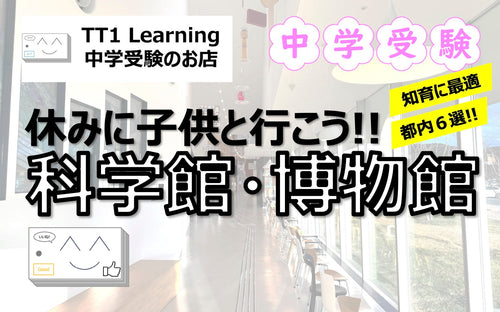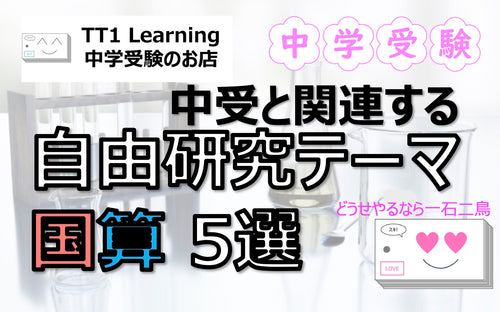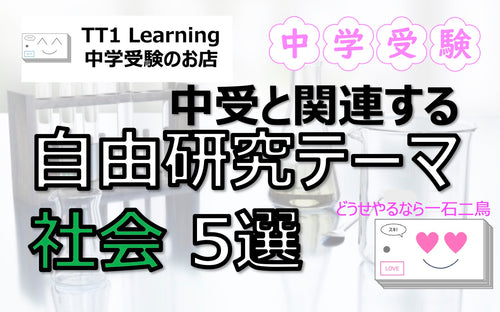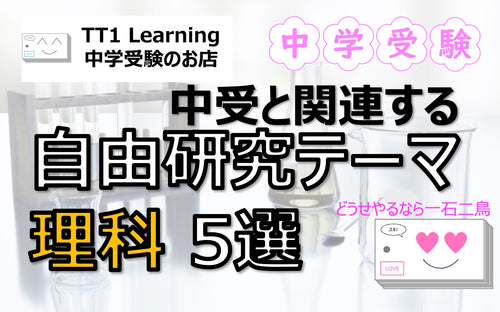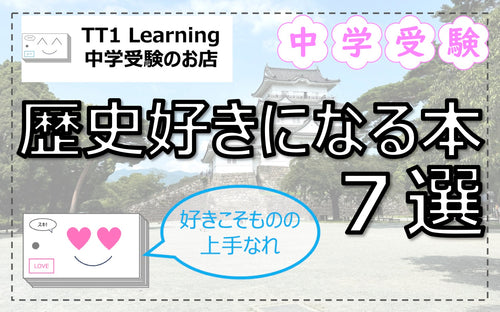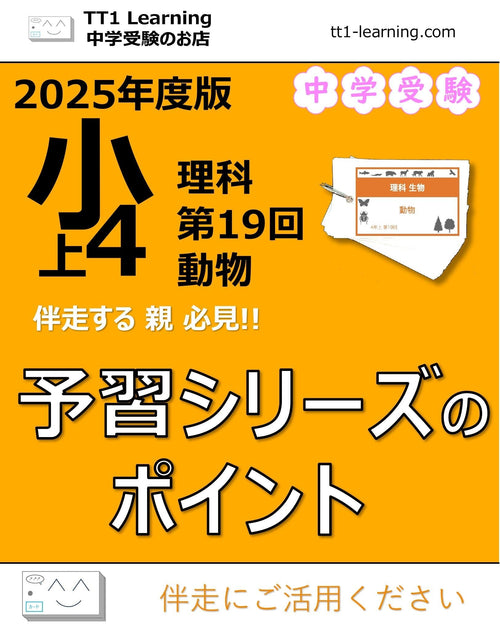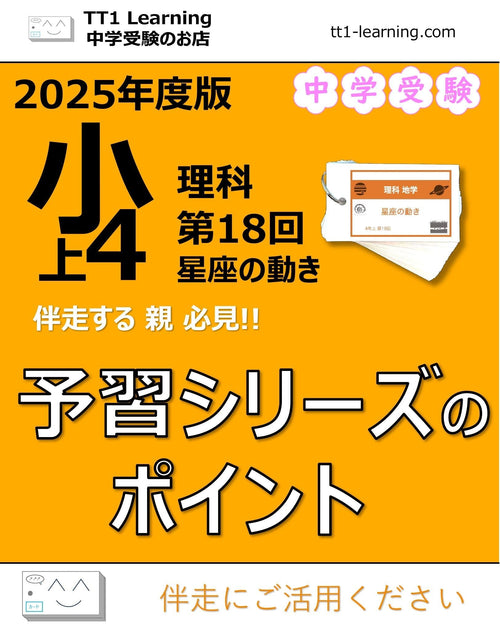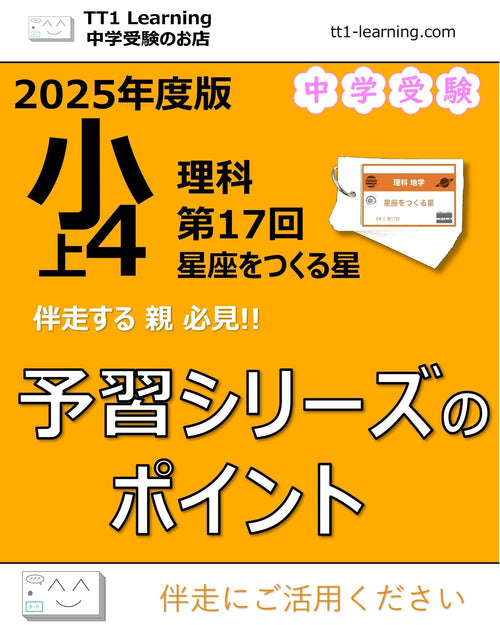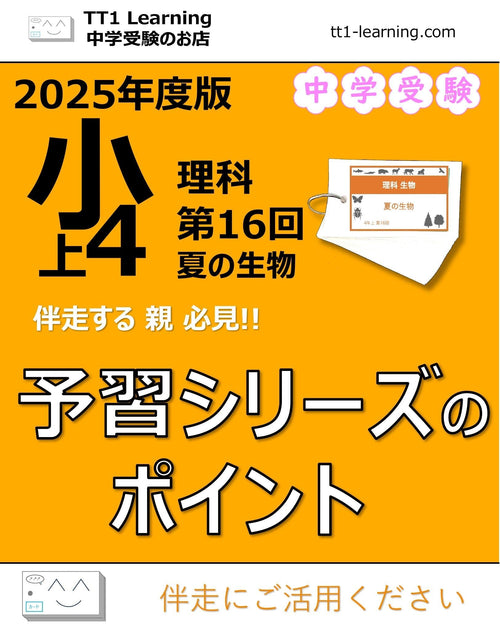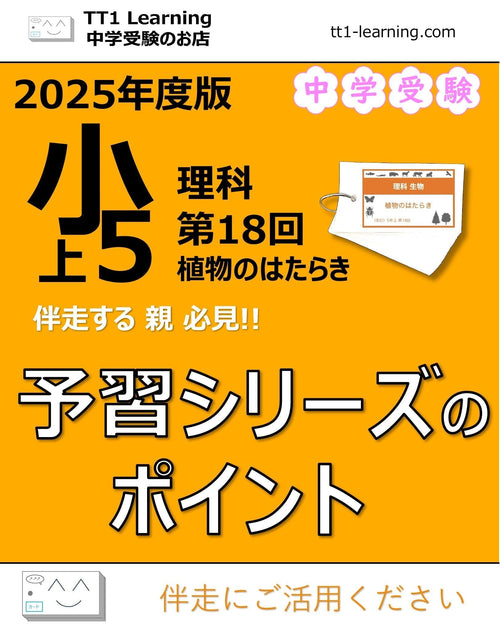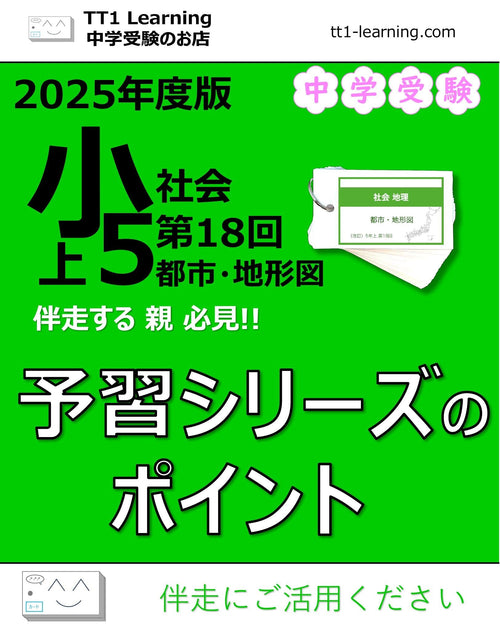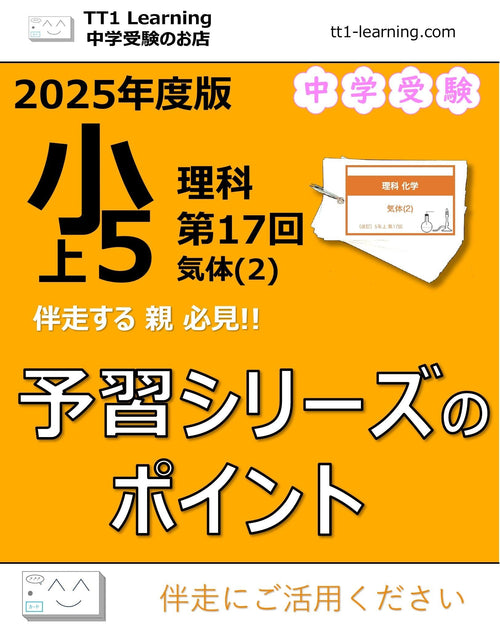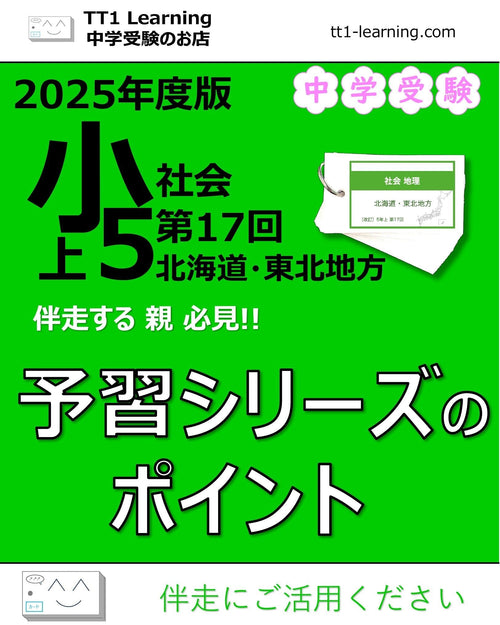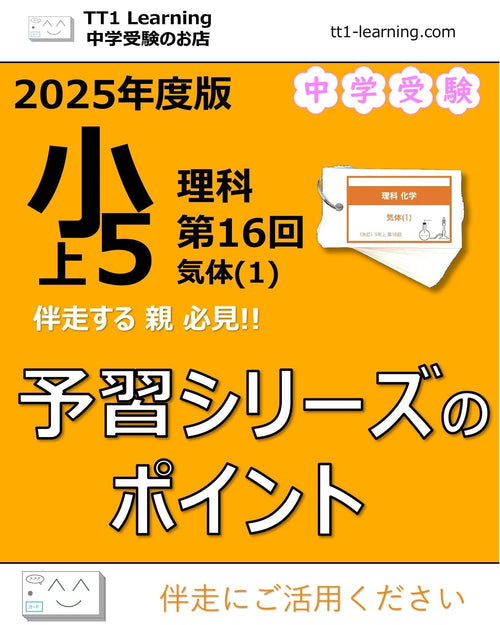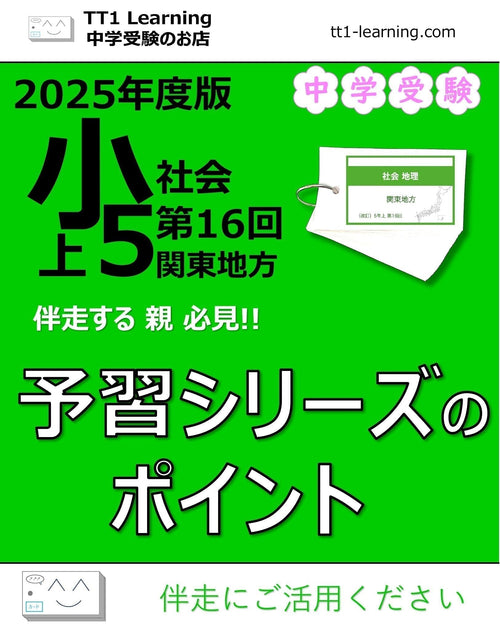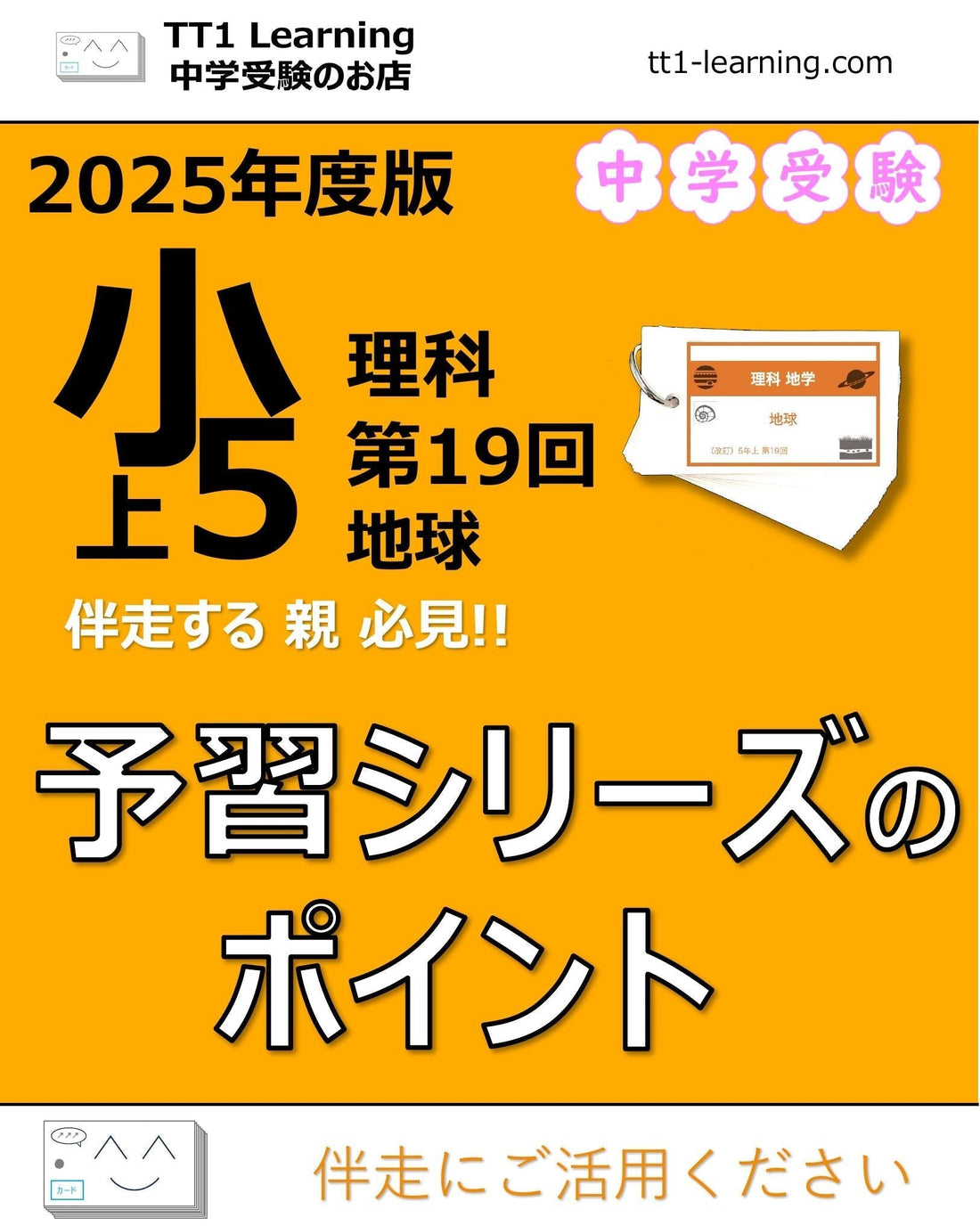
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第19回「地球」ポイントまとめ
共有
上期最後!第19回は「地球」の単元です。
地球は私たちが住む場所ですが、その内部構造、歴史、動きなど、知れば知るほど面白いポイントがたくさんあります。
しかし、用語が多く図的理解や計算も絡むので、「覚えることが多い」「混乱する」と感じるお子さんも多いです。
だからこそ、一つずつ整理して「なぜ?」を理解しながら進めることがとても大切です。
親御さんと一緒に表を作ったり、図を描きながら話し合ったりすると、理解度がぐっと上がります。今回も、一緒に「楽しく学ぶ」スタイルでまとめていきましょう!
単元の概要
地球の単元は、大きく分けると以下の内容があります。
- 地球のスペック(形、大きさ、動き)
- 表面構造(大気圏、水圏、岩石圏)と内部構造(マントル、外核、内核)
- 地球の歴史(4つの時代と示準化石)
- 地球上の位置(緯度、経度、太陽の見える方向、時差)
どれも大切ですが、特に「どうしてそうなるのか」を意識して学ぶと、知識が定着しやすくなります。
1. 地球のスペックをおさえよう
まずは地球の基本情報、いわば「地球のプロフィール」を整理しましょう。
- 形:ほぼ球形ですが、実は南北にわずかにつぶれています。これは自転による遠心力の影響です。完全な球ではないことを知っておくと、応用問題でも役立ちます。
- 大きさ:直径は約1.3万kmです。太陽(約140万km)と比べると約109分の1、月(約0.35万km)と比べると約4倍の大きさです。身近なイメージが湧くように比較しておくと覚えやすいです。
-
動き:地球は自転(西から東へ)と公転(太陽の周りを回る)をしています。
自転の軸は23.4度傾いていて、この傾きが四季の原因になります。「なぜ季節があるの?」という質問にもここが答えになります。 - これらの情報は、図や模型を使って説明するとイメージがつきやすいです。親子で地球儀を回しながら確認するのもおすすめです。
2. 地球の構造を理解する
地球は表面と内部で大きく分けられます。まずは表面から整理します。
- 大気圏:地表から約100kmの範囲を指し、私たちが呼吸している空気を含む層です。ちなみに、雲ができる高さはおおよそ10kmまでです。
- 水圏:地球の表面の約70%が水で覆われています。海、湖、川などがこれに含まれます。
- 岩石圏:平均約35kmの厚さの地殻部分です。プレートの動きや地震など、理科の他の分野とも関連があります。
内部構造には以下の3つがあります。
- マントル:岩石圏の下にあり、ゆっくり動く流動層です。地震や火山活動にも深く関わります。
- 外核:液体の金属でできており、地磁気を作る原因にもなっています。
- 内核:金属の固体部分で、非常に高温高圧です。
図や模式図を使って「どこがどの部分か」を一緒に確認しながら進めると理解が深まります。「表面の3つ」「内部の3つ」とセットで覚えると整理しやすいですよ。
3. 地球の歴史と示準化石
地球の誕生は約46億年前とされています。これまでの歴史は大きく4つの時代に分けられます。
- 先カンブリア時代:地球誕生から約5.4億年前まで。生物の誕生や地磁気の発生が特徴です。らん藻類やクラゲなどの古い生物が登場します。
- 古生代:約5.4億年前から約2.5億年前。オゾン層ができ、陸上への生物進出が始まりました。代表的な化石はフズリナ、サンヨウチュウです。
- 中生代:約2.5億年前から約6600万年前。恐竜が栄え、アンモナイトもこの時代に繁栄しました。哺乳類も登場します。
- 新生代:約6600万年前から現代まで。人類の出現(約700万年前)、マンモスなどが特徴です。
これらの時代と示準化石(その時代を代表する化石)はセットで覚えることが大切です。表にして「時代」「特徴」「代表化石」をまとめると頭の中が整理できます。
4. 緯度・経度と位置の特定
地球上の位置を表すときに使うのが「緯度」と「経度」です。

- 緯度:赤道を基準に南北の位置を示す角度。赤道は0度、北極は北緯90度、南極は南緯90度です。
- 経度:本初子午線(ロンドンのグリニッジ)を基準に東西の位置を示す角度。東経0度がロンドン、日本は東経135度、ハワイは西経150度です。
図を使って位置を確認するときは、北と南、東と西を間違えないように注意が必要です。緯度と経度を理解すると、世界地図を見る楽しさが増えます。
お子さんと一緒に地図を広げて「日本はどこ?」「ハワイは?」と指差しながら確認するのはおすすめの学習法です。
5. 太陽の見える方向と時差の計算
地球が自転しているため、太陽の見える方向が地域によって異なります。

- 北半球:太陽は南に昇り、南の空を通って沈む。
- 南半球:太陽は北に昇る。
また、地球は西から東に自転しているため、東の地域ほど早く朝が来ます。これが「時差」の原因です。
時差の計算方法も重要です。地球は360度を24時間で回るので、15度で1時間の時差が生まれます。

例として、日本(東経135度)とロンドン(0度)の時差は135÷15=9時間です。日本の方がロンドンより9時間進んでいます。
さらに、日本(東経135度)とハワイ(西経150度)の時差は(135+150)÷15=19時間になります。ただし、日付変更線を挟む場合は注意が必要です。図を描きながら説明すると、お子さんにも理解しやすくなります。
表や暗記カードでまとめて復習
「地球」の単元は覚える内容が多いですが、表や暗記カードを使うと整理しやすくなります。
例えば、以下のような表を作ると便利です。
- スペック:形、大きさ、動き
- 表面構造:大気圏、水圏、岩石圏
- 内部構造:マントル、外核、内核
- 歴史:時代、特徴、代表化石
これを親子で一緒に作り、クイズ形式で答え合わせをするのがおすすめです。「この化石はどの時代?」など問いかけると、自然と記憶に残ります。
当サイトの暗記カードも、予習シリーズに合わせて要点がまとめられているので、効率よく確認できます。「苦手だな」と思った部分はカードを繰り返し使い、理解度を深めましょう。
まとめ
「地球」の単元は範囲が広く、用語も多いので、最初は大変に感じるかもしれません。しかし、図や表を活用して「どうして?」を考えながら学ぶと、一つずつ理解できるようになります。
親御さんと一緒に進めることで、お子さんも安心して学べますし、楽しさも倍増します。「わかった!」「できた!」という小さな成功体験が積み重なると、大きな自信につながります。
わからない部分があったら一度立ち止まって、表を見返したり、一緒に模型や地図を使って確認したりしてください。楽しく学ぶことが、結果的に最も効率的な勉強法になります。
もし疑問や不安があれば、コメントやお問い合わせで気軽にご相談ください。一緒に「地球」の単元を得意分野に変えていきましょう!
小5上期の予習シリーズのポイントの記事
社会
理科
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。