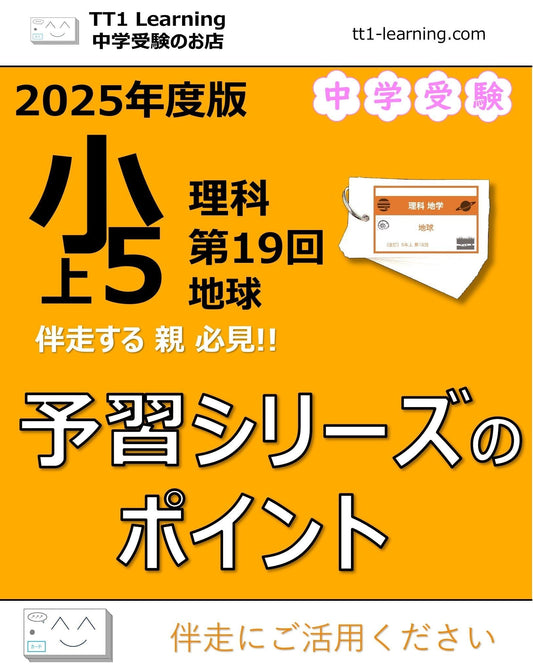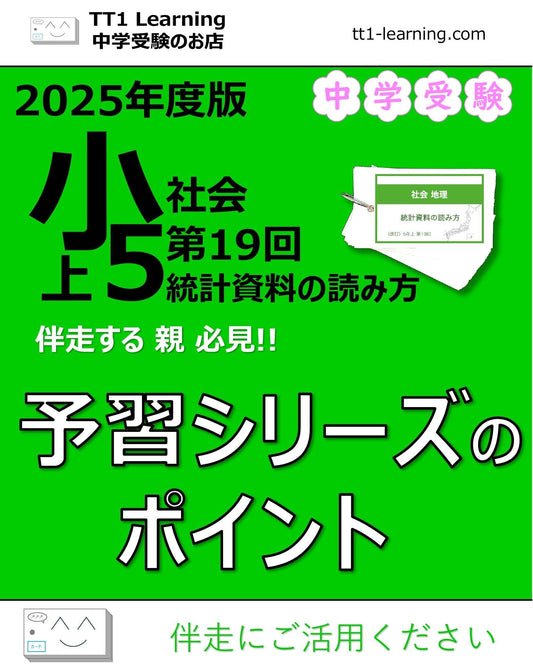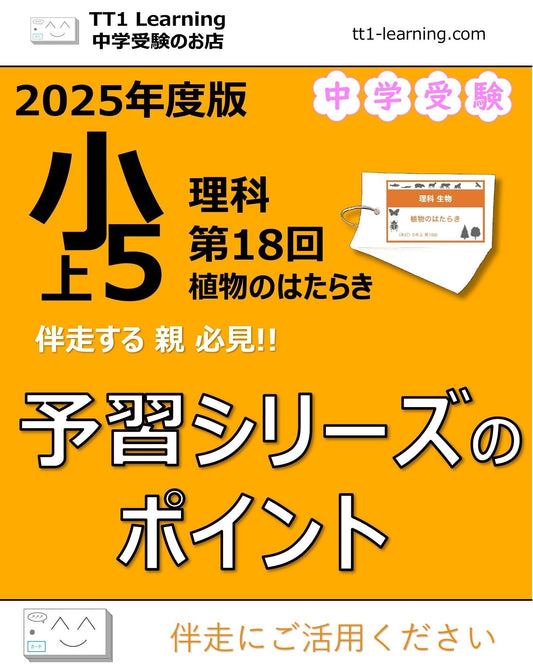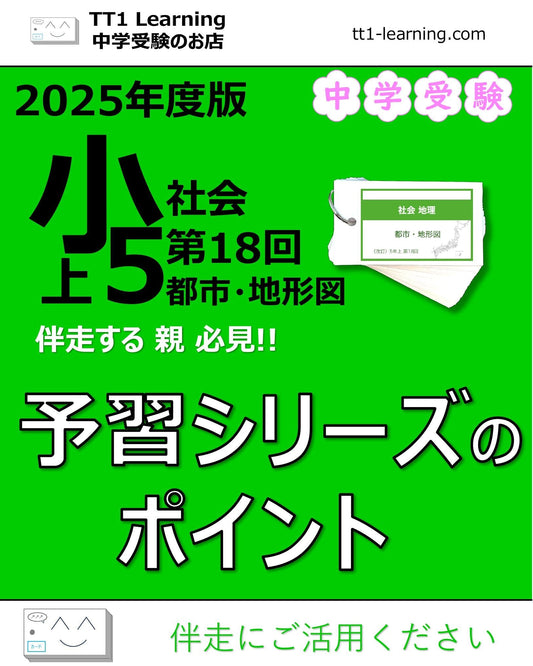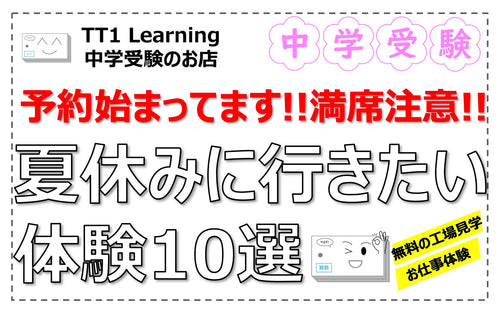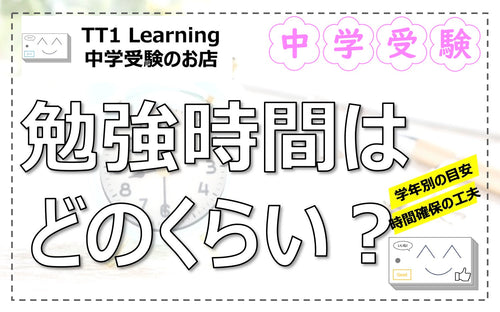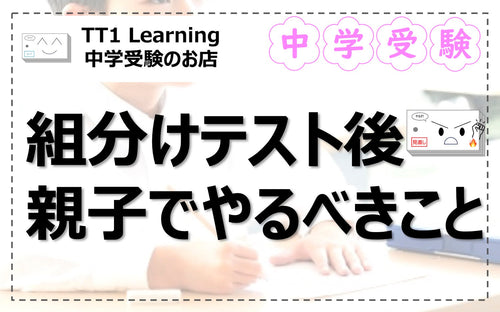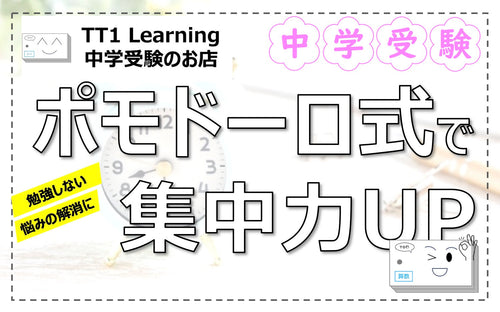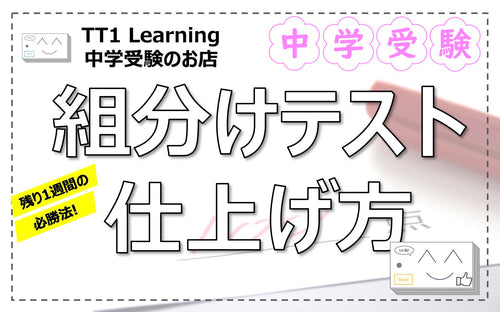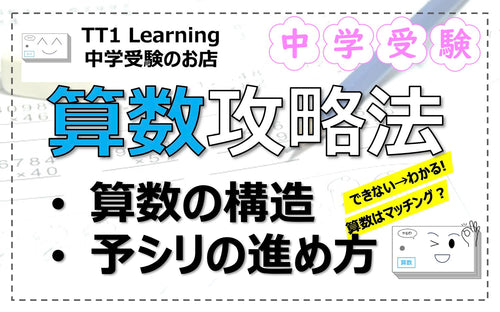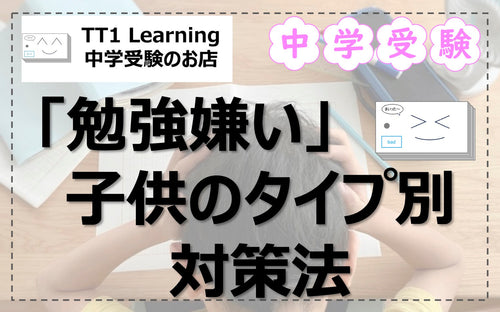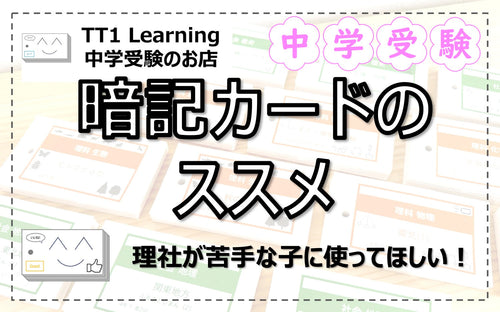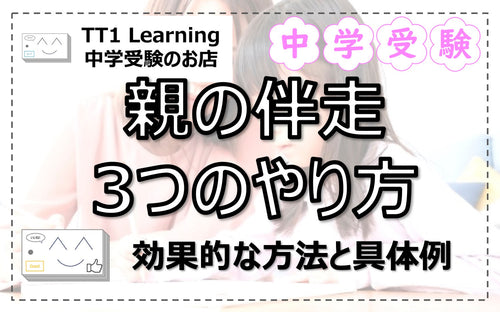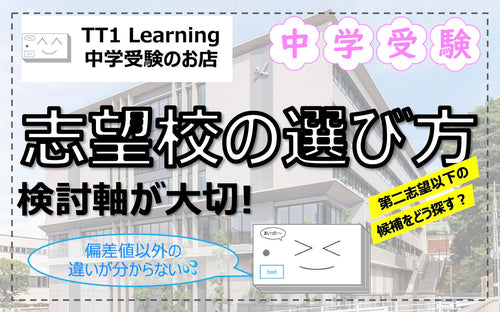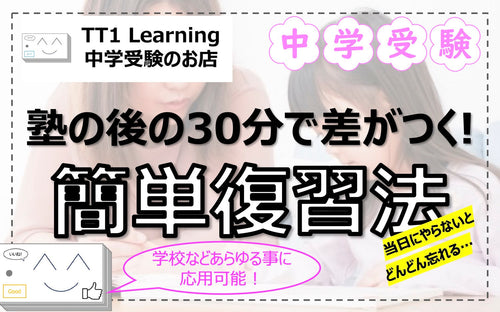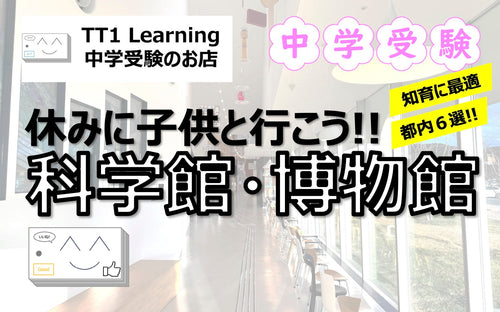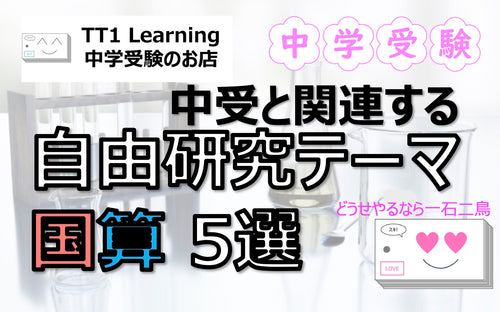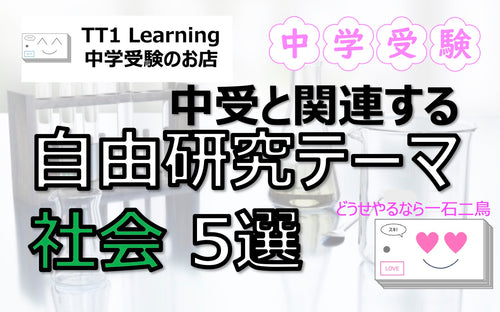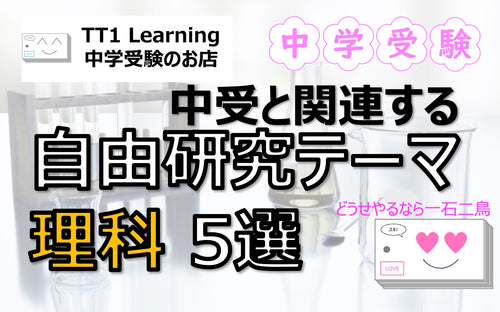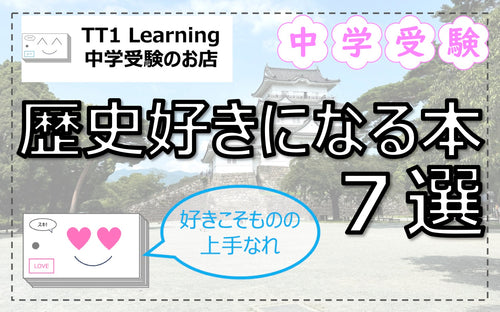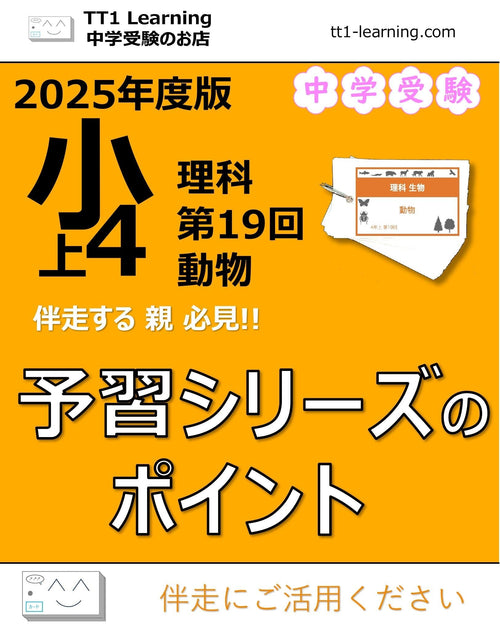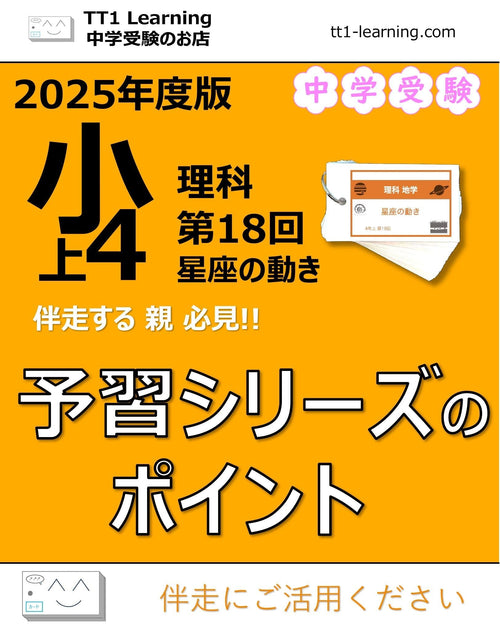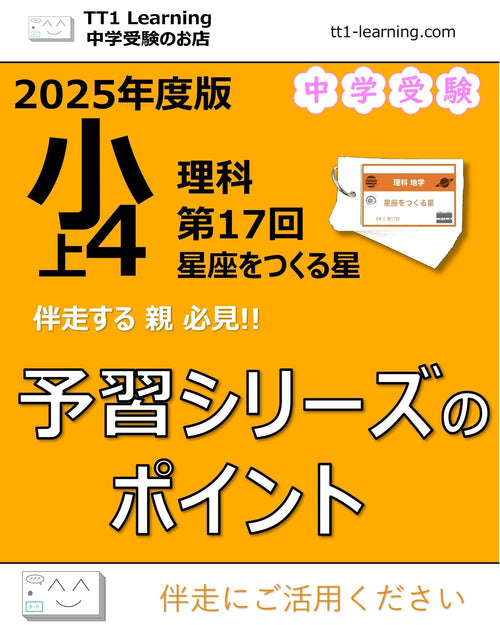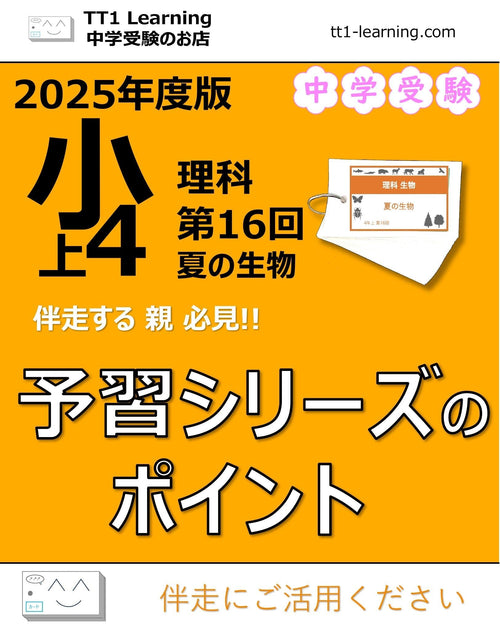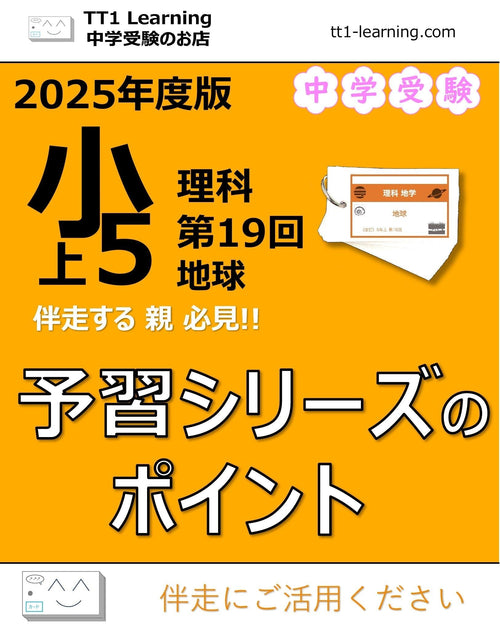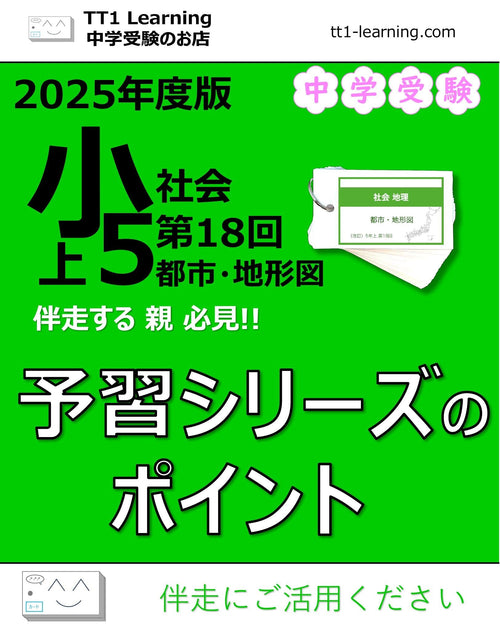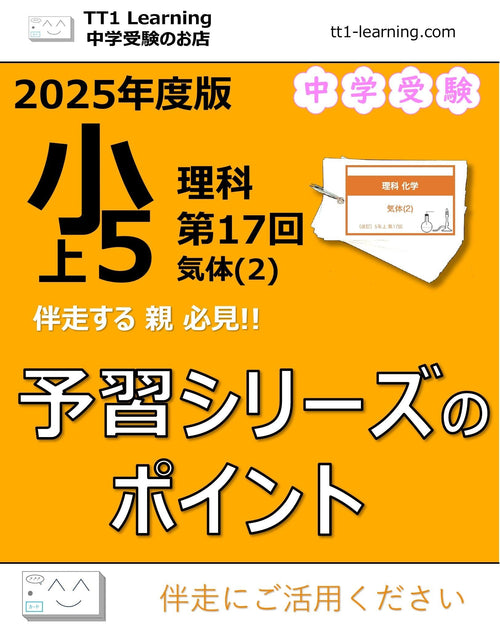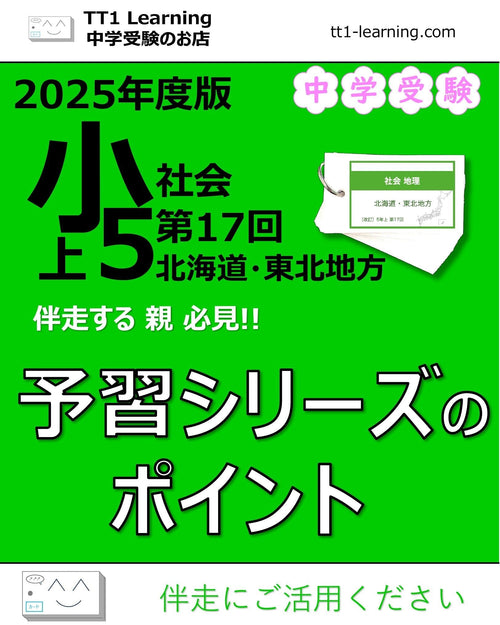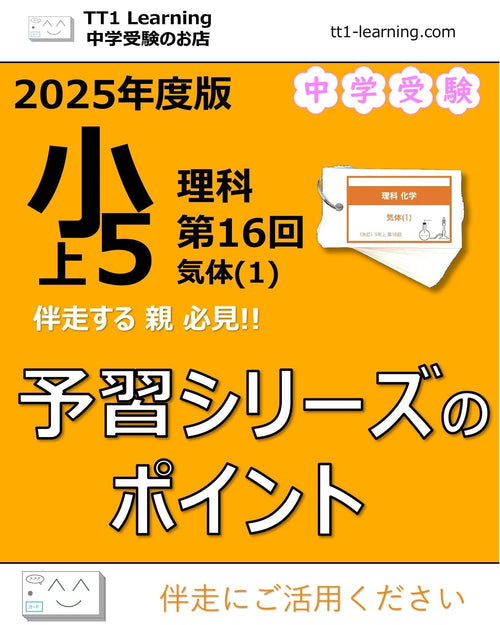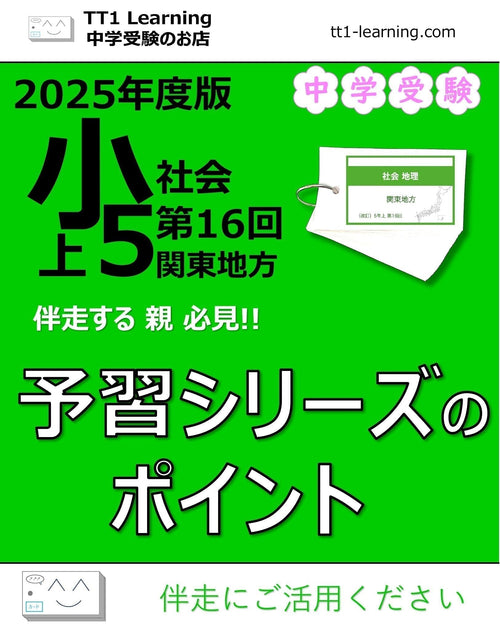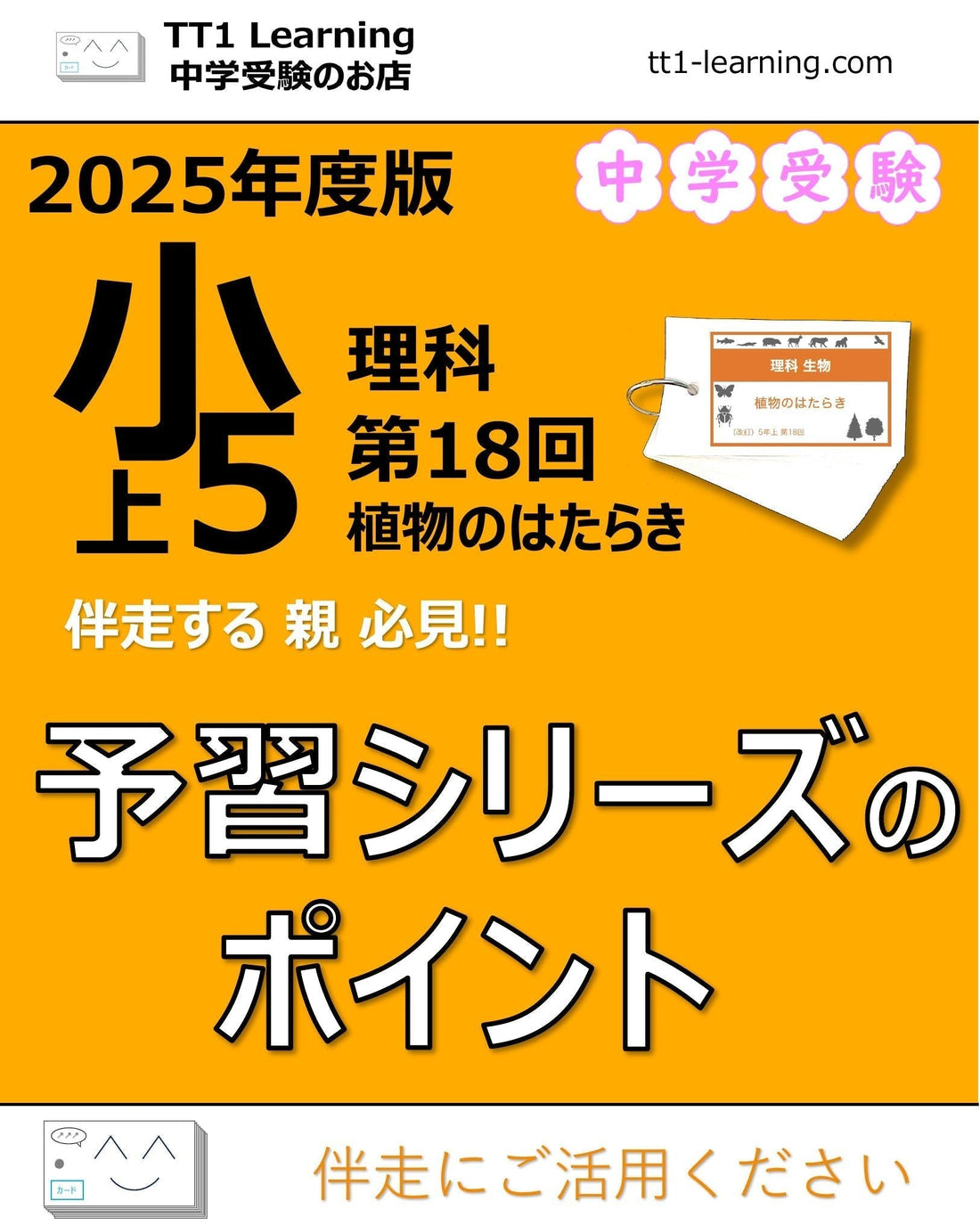
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第18回「植物のはたらき」ポイントまとめ
共有
今回は「植物のはたらき」をテーマにまとめていきます。
植物といえば、普段私たちの周りにある当たり前の存在ですが、その中で行われている活動はとても奥深いです。
小学生の理科では、特に「光合成」「呼吸」「蒸散」という3つのはたらきが重要ポイントになります。
これらはただ覚えるのではなく、
「なぜそれをするのか」
「いつ、どこで行われるのか」
を理解することが大切で、それらが理解できればぐっと腑に落ちて記憶に残りやすくなります。
お子さんにとっては、単語や用語が多く、混乱しがちな単元です。
しかし、目的や仕組みを一緒に確認しながら進めると、理科が楽しくなり、確実に得点源になります。親御さんと一緒に表を作ったり、実験をイメージしたりする時間を楽しんでください!
単元の概要
植物の活動は「光合成」「呼吸」「蒸散」の3つに大きく分けられます。それぞれには明確な目的があり、行われるタイミングや場所も異なります。
-
光合成:養分(デンプン)を作るための活動。主に昼間、日光があるときに葉緑体で行われます。副産物として酸素ができますが、酸素を作ることが目的ではありません。
-
呼吸:活動エネルギーを作るための活動。昼夜を問わず一日中、植物全体で行われます。酸素と養分を使い、二酸化炭素と水を排出します。
-
蒸散:体温を下げるための活動。気孔から水分を蒸発させることで体温を調節します。日中、気温や湿度、風の条件によって強さが変わります。
これらの「目的」をしっかり理解することがポイントです。テストでも「何のために行っているか」が問われる問題が多いので、表面的な暗記にとどまらず、「どうして?」を意識しましょう。
1. 光合成・呼吸・蒸散の基本を理解しよう
まず、3つのはたらきの基本を整理します。

光合成は、二酸化炭素と水を使って養分(デンプン)を作る働きです。日光のエネルギーが必要なので、主に昼間に行われます。葉の中の「葉緑体」がこの反応を担っています。
呼吸は、光合成で作った養分(デンプン)と酸素を使ってエネルギーを作り出す活動です。このエネルギーは、植物が生きるために必要な動きに使われます。呼吸は昼夜を問わず行われ、植物の全身で進みます。呼吸の結果、二酸化炭素と水が出てきます。
蒸散は、気孔を通して水を蒸発させることによって体温を下げる活動です。植物は自分で温度調節ができないため、蒸散によって水分を外に出して温度を下げています。条件によって蒸散の強さは変わり、日差しが強い、気温が高い、湿度が低い、風が吹くなどの状況で盛んになります。
このように、3つのはたらきにはそれぞれ目的があり、それが「生きるための活動」であるという理解が大切です。
2. 光合成と呼吸の関係を整理する
次に、光合成と呼吸の関係を整理しましょう。光合成と呼吸は「逆の反応」とも言われます。
-
光合成:二酸化炭素 + 水 + 日光エネルギー → 養分(デンプン) + 酸素
-
呼吸:養分(デンプン) + 酸素 → 二酸化炭素 + 水 + エネルギー
光合成では、二酸化炭素と水を材料にして日光のエネルギーを使い、養分(デンプン)と酸素を作ります。呼吸では、光合成で作った養分を使って酸素と反応させ、エネルギーを取り出します。この時に二酸化炭素と水が排出されます。

グラフ問題では「補償点」や「光飽和点」が出てきます。補償点は、光合成で吸収する二酸化炭素の量と呼吸で排出する二酸化炭素の量が釣り合う点です。光飽和点は、光の強さをいくら強くしても、これ以上光合成の速度が増えない点です。

お子さんと一緒に「光合成と呼吸は何をしているのか」「グラフの縦軸と横軸は何を表しているのか」を確認しながら進めると理解が深まります。特に「グラフのどの部分で何が起きているか」を話し合うのはおすすめです。
3. 蒸散の役割と条件を確認する
蒸散の役割は体温調節です。植物は人のように汗をかいたり動いたりして体温を調節することができません。その代わりに、気孔を通じて水分を蒸発させることで温度を下げています。
蒸散が活発になる条件は以下の通りです。
- 日差しが強いとき
- 気温が高いとき
- 湿度が低いとき
- 風が吹くとき
これらの条件が重なると、植物の蒸散は非常に盛んになります。また、冬には水分の吸収も少なくなり、蒸散を減らすために葉を落とす植物もあります。葉を落とす理由を「蒸散を減らすため」と関連付けると、理解がより深まります。
「蒸散=水を蒸発させることで体温を下げる活動」と覚えると、なぜそうするのかが自然と頭に入ってきます。
4. 実験と確認方法をおさえる
植物の活動を理解するうえで、実験はとても大事なポイントです。それぞれのはたらきを確認する方法を整理しておきましょう。
- 光合成の確認:葉にヨウ素液をたらして、青紫色に変わるかどうかでデンプンの生成を確認します。
- 呼吸の確認:石灰水を使って、二酸化炭素が発生しているかを確認します。二酸化炭素があると石灰水が白く濁ります。
- 蒸散の確認:塩化コバルト紙を使って、水分の発生を確認します。水分があると青色から赤色に変わります。
このように、実験の目的や指示薬の変化を「なぜそうなるのか」を一緒に話しながら覚えると、単なる暗記ではなく理解に繋がります。お子さんと「どうして色が変わるのかな?」と問いかけ合うことで、知識が深く定着します。
表や暗記カードを使った復習法
学習した内容を整理するには、表や暗記カードを活用するのがおすすめです。表にまとめると、視覚的に整理できて記憶に残りやすいです。
例えば、「光合成」「呼吸」「蒸散」の目的、行われる時間帯、行われる場所、副産物などを表に書き出すと、一目で比較できます。お子さん自身に書かせることで、頭の中が整理され、自分の言葉で理解できるようになります。
暗記カードは、短時間で何度も繰り返し確認できる点が強みです。おうちでクイズ形式にすると、ゲーム感覚で楽しく進められます。間違えたカードはまとめて再挑戦するなど、工夫するとより効果的です。
 当サイトでも単元に合わせた暗記カードを用意しています!!
当サイトでも単元に合わせた暗記カードを用意しています!!
中学受験に直結するポイントが整理されており、どの問題が出ても自信を持って答えられるようになります。
まとめ
「植物のはたらき」の単元は、内容が多く感じるかもしれませんが、整理して理解すればとても楽しく、得点源にできます。覚えるだけでなく、「なぜそのはたらきをするのか」を一緒に考えることが理解への第一歩です。
最初は覚えづらい部分もあるかもしれませんが、一緒に図を書いたり、実験の仕組みを話したりする中で、だんだん楽しくなってくるはずです。小さな「わかった!」を積み重ねることが自信につながり、テスト本番でも大きな力を発揮します。
親御さんとお子さんが一緒に進める時間は、知識だけでなく、信頼関係や挑戦する楽しさを育む大事な機会と思います!ぜひ、頑張ってください〜
小5上期の予習シリーズのポイントの記事
社会
理科
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。