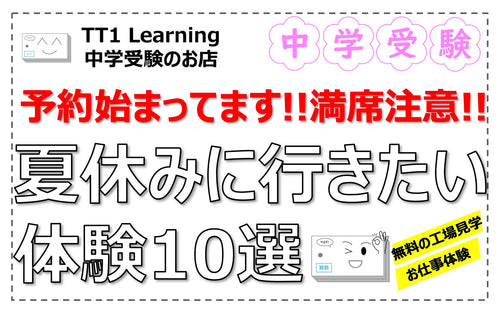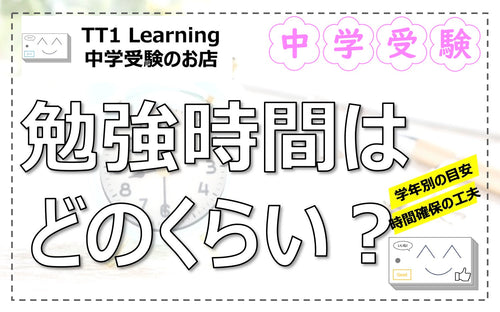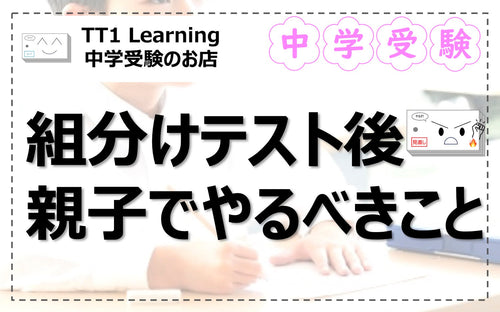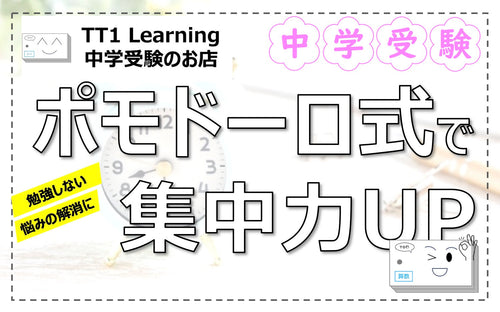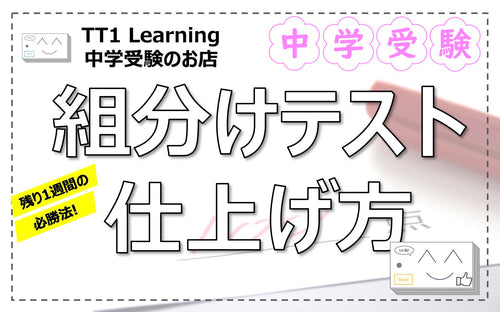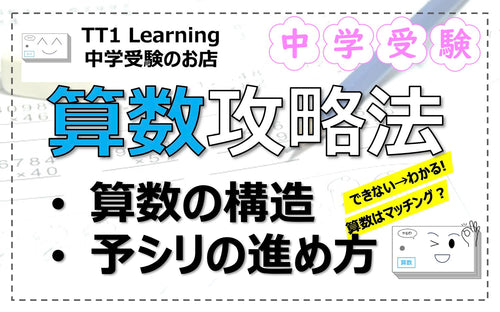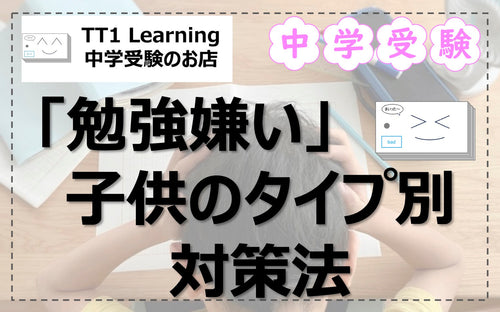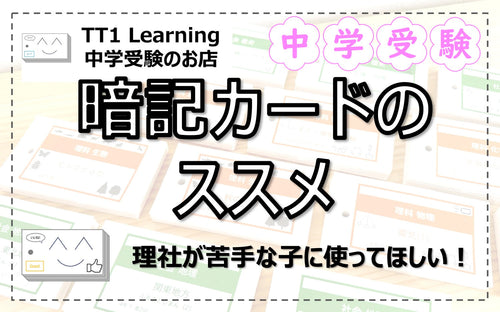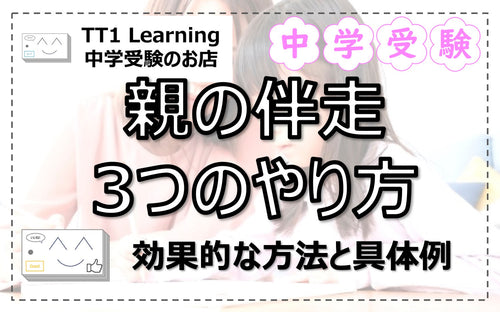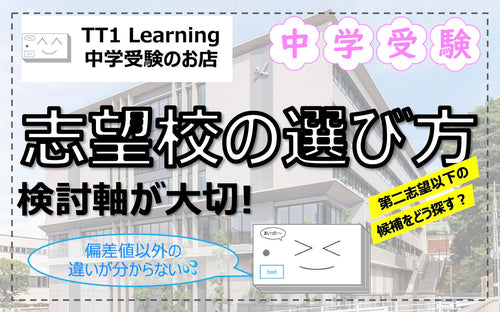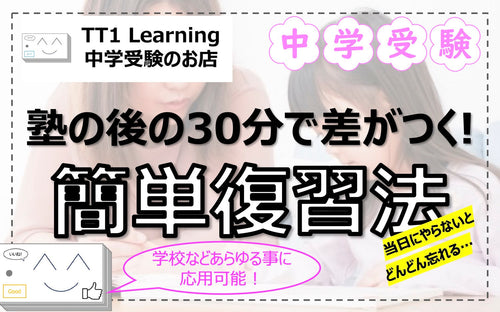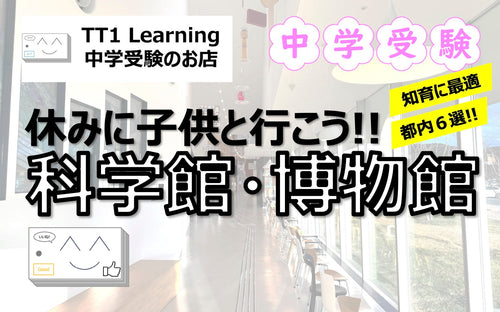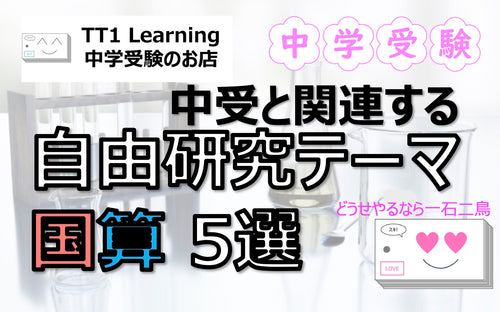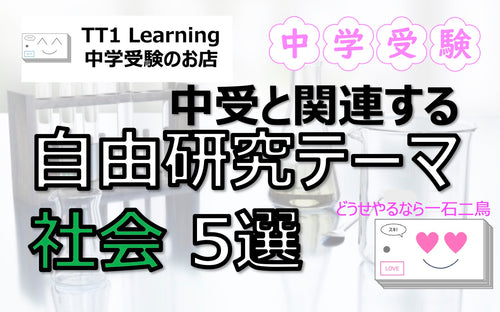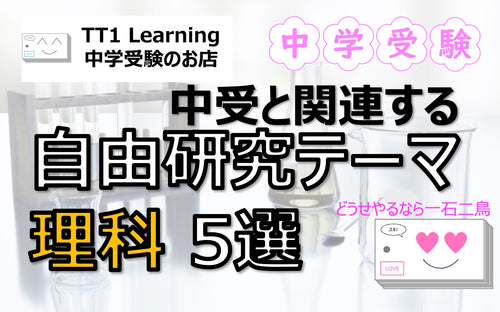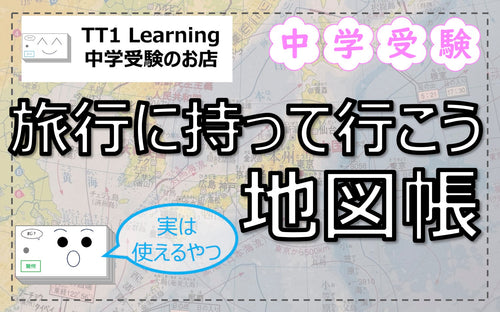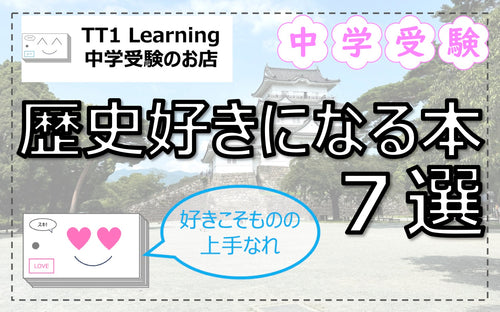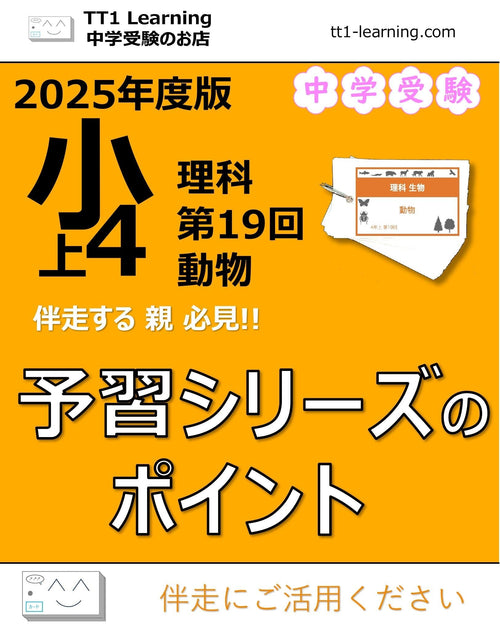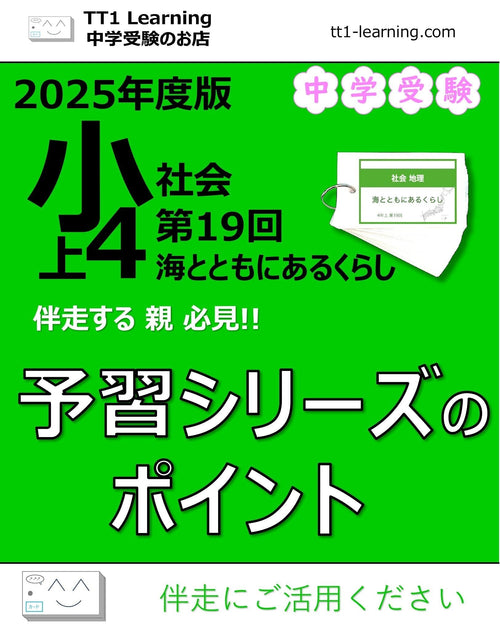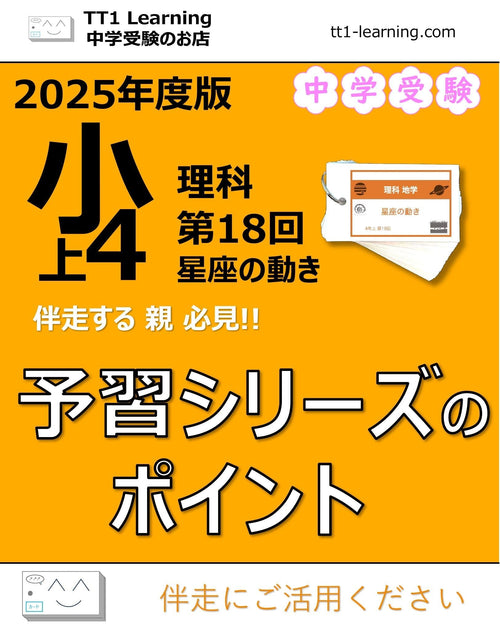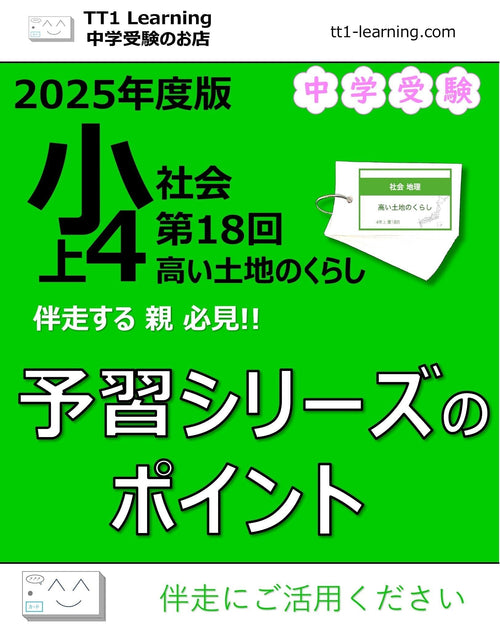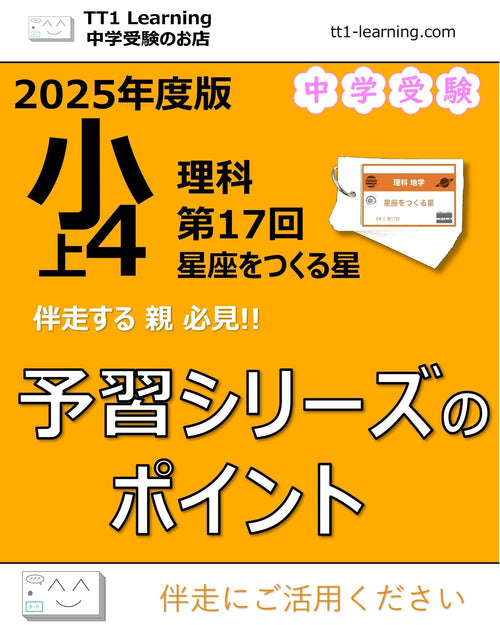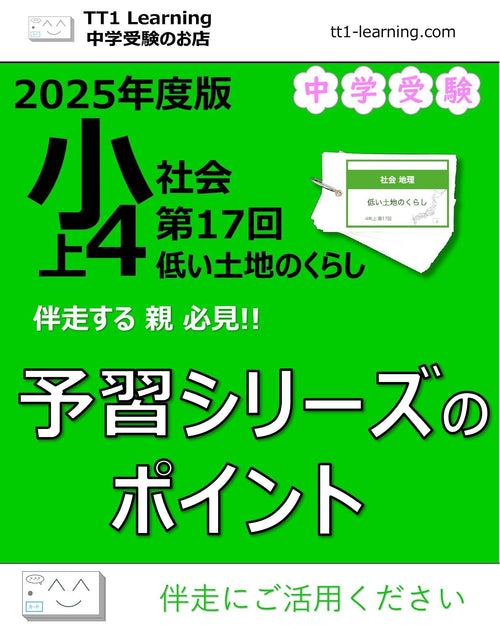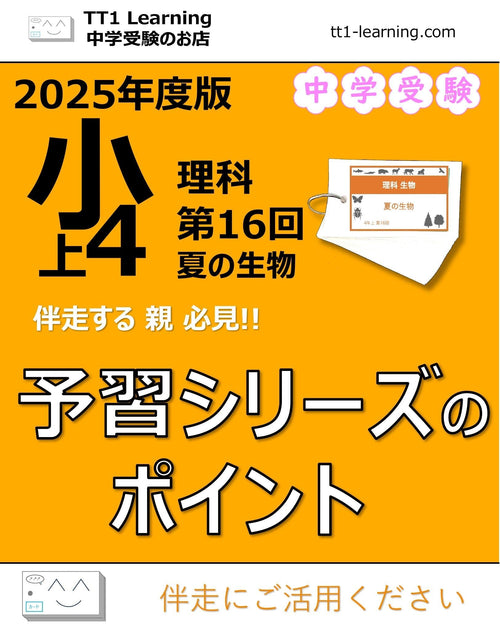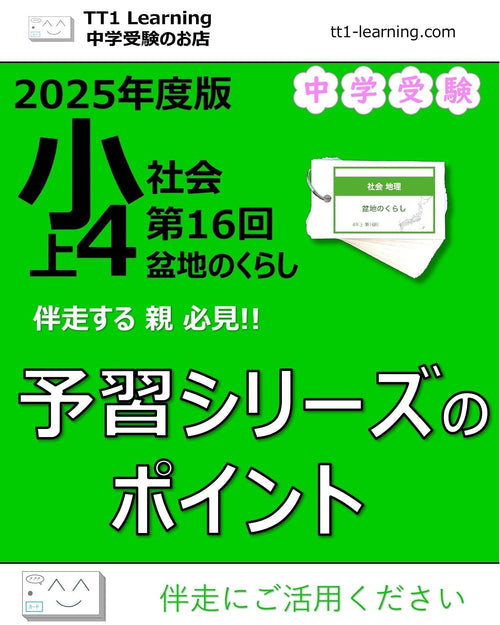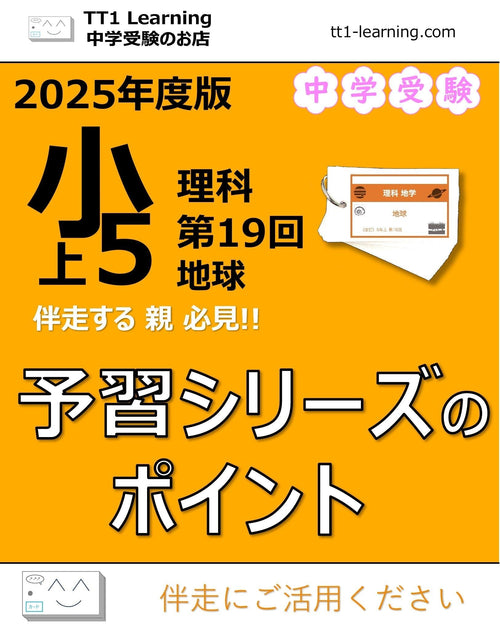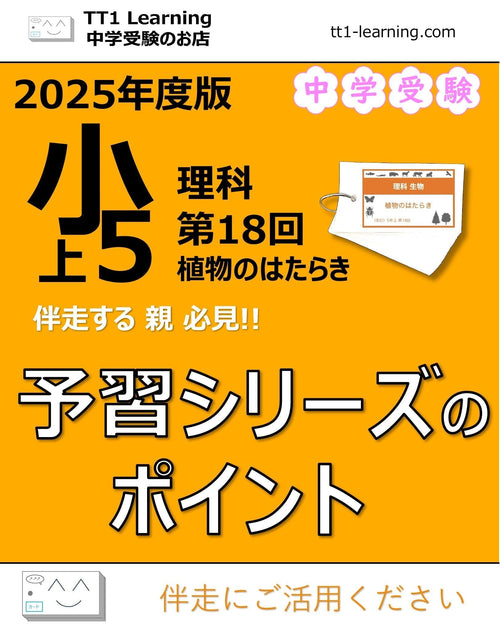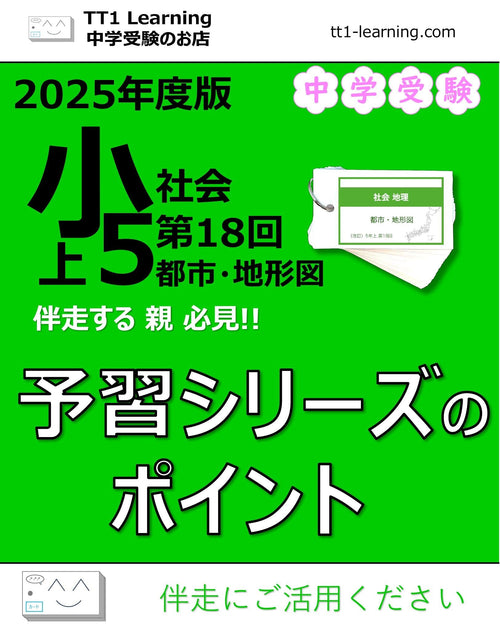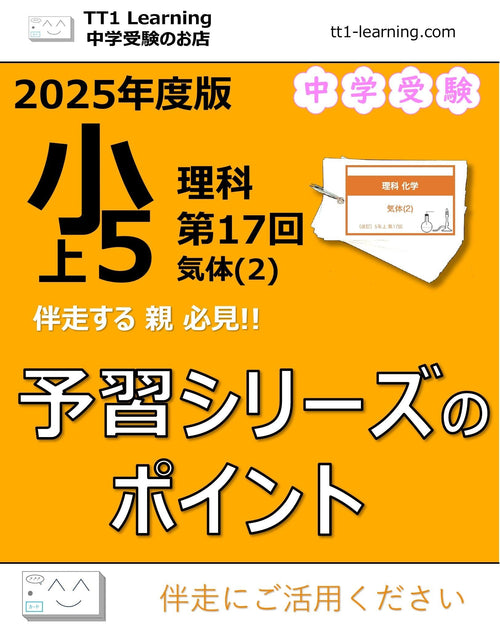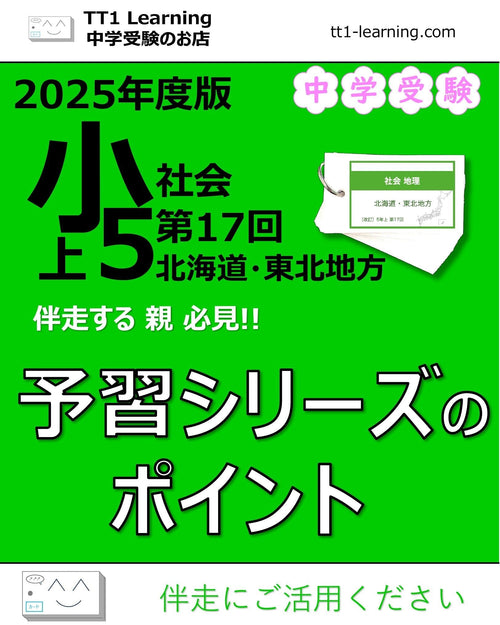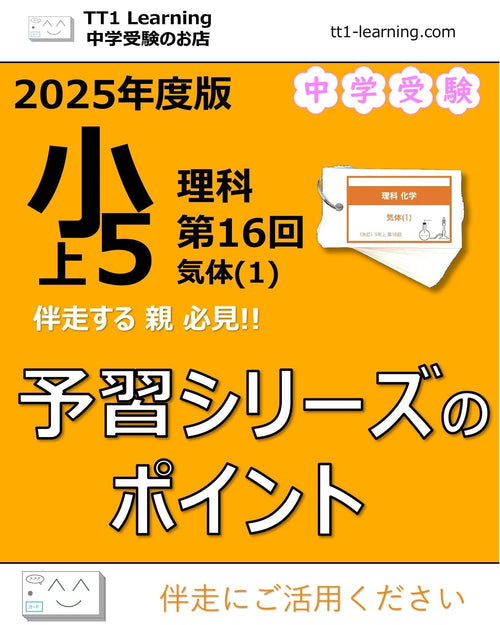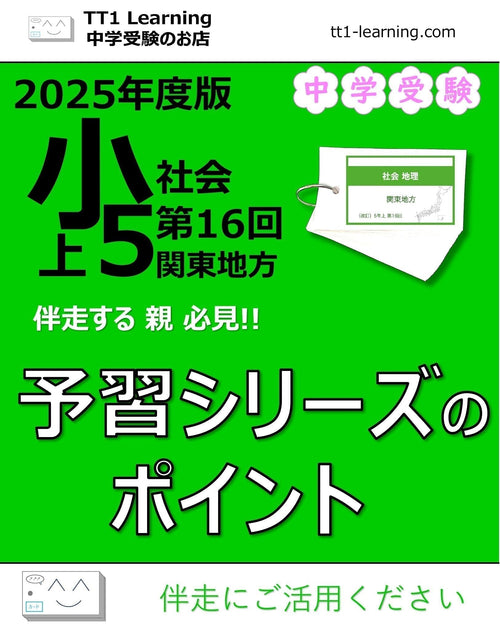-
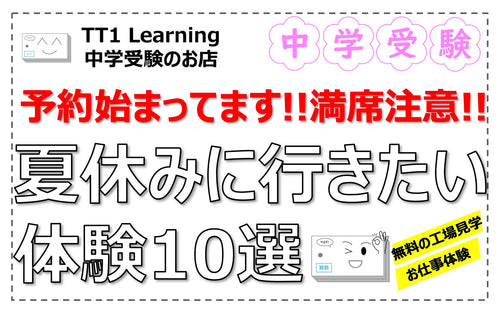
夏休みにおすすめ!首都圏から行ける無料の工場見学10選(2025年版)
「夏休み始まってから、工場見学でも行こうか~って検索したら…全部満席だった…!」
実はこれ、私自身も経験しました。
特に人気の工場見学は、1〜2ヶ月前から予約が始まり、すぐに埋まってしまうのが現実。
「無料だし、アクセスも良さそう!」...
-
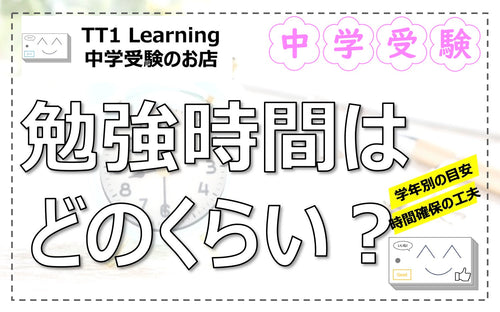
中学受験、みんなどれくらい勉強してる?
「うちの子、けっこう頑張ってると思うけど…偏差値が伸び悩み…」「他の子ってどれくらいやってるの?」
中学受験に取り組むご家庭では、ふとした時にこうした疑問がわいてくるものです。特に、周囲との比較がしづらい「家庭学習の時間」については...
-
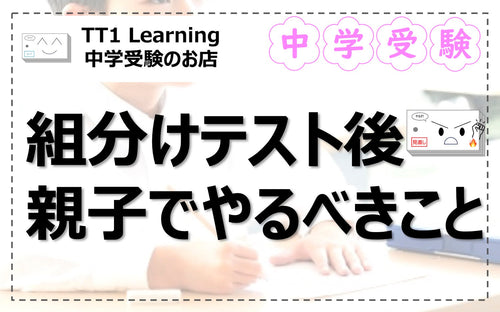
【中学受験】組分けテスト後 親子で振り返り・復習法のまとめ
組分けテスト、お疲れ様でした。
この数週間、お子さんもご家庭も本当に頑張ってこられたと思います。その努力の成果が数字や偏差値という形で返ってくるのがテストですが、結果が良かった時もそうでなかった時も、本当に大切なのはここから先の行動で...
-
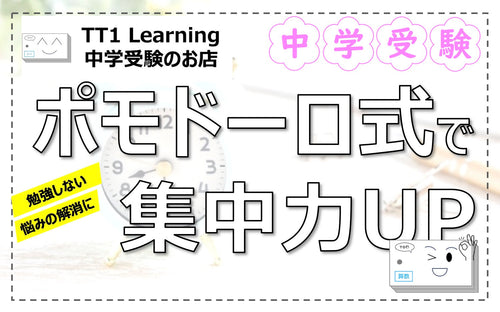
【中学受験】「勉強しない」問題に効く!ポモドーロ式を導入して“学習スイッチ”を入れよう
「勉強しなさいって言ったのに、また漫画読んでる…」
「10分前に始めたばかりなのに、もううろうろし始めてる」
「今日も集中できずに、結局ダラダラして終わった…」
こんな日々に、私も頭を抱えていました。
また、中学受験で志望校も...
-
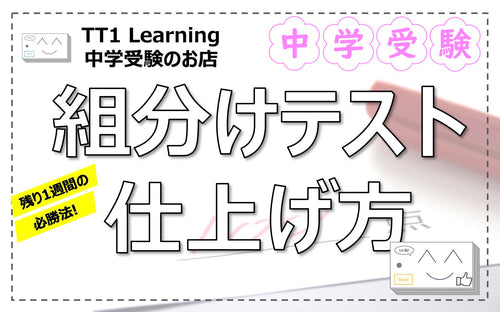
【中学受験】組分けテスト直前の仕上げ方|教科別&1週間の効率的な過ごし方を徹底解説!
「今回も全然仕上がってない…」
「週テ・カリテの見直し、手つかずかも…」
「とにかく時間が足りない!」
組分けテスト前に何度思っただろう。。。
あっという間にやってくる組分けテストに向けて、残り1週間をどう使うか!とても大切です。...
-
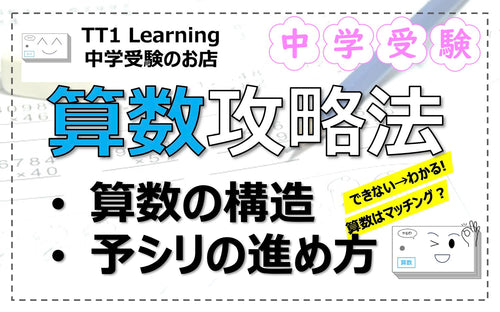
算数攻略法 「できない」から「わかる!」に変わる!予シリの使い方も解説
「算数がとにかく苦手…」
「教えようとしても、なぜできないのかがわからない…」
中学受験を目指すご家庭で、こうした悩みを抱えている方は少なくありません。
でも、ちょっと考え方を変えるだけで、算数の“つまずき”は意外と整理できるかもしれ...
-
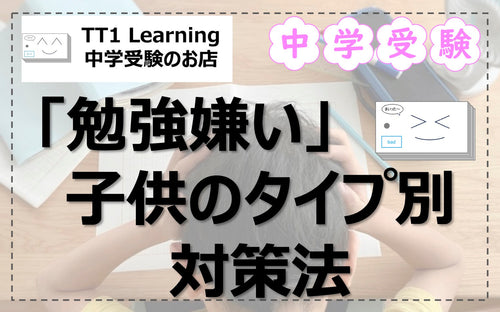
中学受験生 親の悩み「勉強嫌い」は性格タイプがカギ!4つの性格タイプ別対策法
中学受験を目指す多くのご家庭で、「うちの子、全然勉強しない」「勉強が嫌いみたいで困っている」といった悩みの声をよく聞きます。
やる気がなさそうな子どもを見て、ついつい「勉強しなさい」と怒ってしまい、「なんでこんなにやらないの!?」...
-
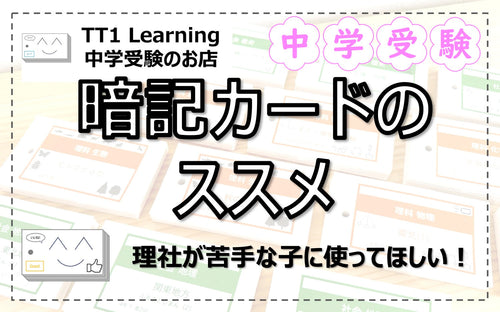
「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!
今回の記事は
「理科と社会がなかなか伸びない…」「何度やっても用語を忘れてしまう…」
そんなお悩みある方必見です!!
実は、多くの受験生が苦戦する“理社の暗記”には、ある秘密兵器があるんです。 それが
暗記カード!
シンプルだ...
-
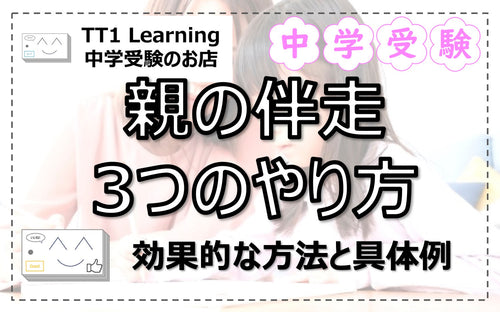
【中学受験】親の“伴走”がカギ!無理なくできる3つのサポート軸とは?
中学受験は、子どもが主役。でも、それを支える親の関わり方もとても大切ですよね。「親の受験」とも言われるくらい、日々の生活や気持ちの支えが必要になるこの時期。「うちはどう関わればいいのかな」と悩まれているご家庭も多いと思います。
「全部...
-
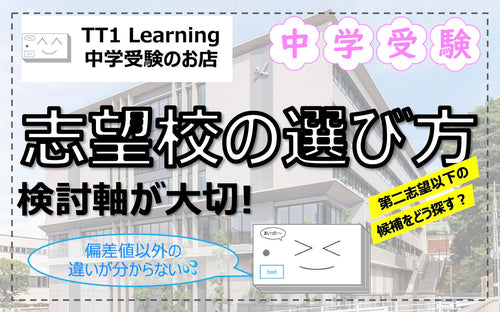
志望校はどう選ぶ?選ぶべき5つの軸で納得の学校選びを
中学受験に向けて塾通いを続ける中、「そろそろ志望校を考え始めないと…」と焦りを感じている方も多いのではないでしょうか?
偏差値はもちろん大事な基準ですが、それだけで志望校を選ぶのは実はとても危険です。「通える範囲に偏差値が合う学校があ...
-
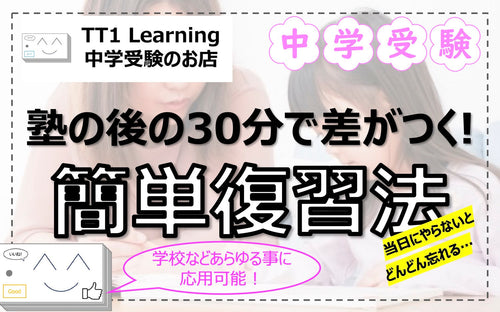
【中学受験】塾のあとの30分で差がつく!家庭でできる簡単復習法
中学受験を目指すご家庭にとって、塾で学んだ内容をいかに家庭で定着させるかは非常に重要なテーマです。「復習をどうやるか」で成績の伸び方に大きな差が出るのは、言うまでもありません。特に、塾の後のたった30分をどう活用するかで、その日の学び...
-
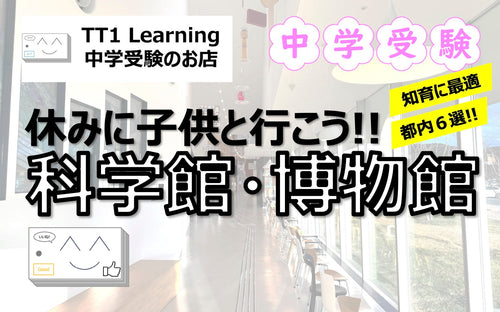
日帰り知育旅にオススメ! 都内の科学館・博物館
子供には机上の勉強だけでなく、なるべく実際に体験させてあげたい。何か興味を持ったらその後の進路にも影響するかもしれないし、探究学習などにも興味を持つかもしれません。
今日は半日程度で東京で行ける科学館・博物館のご紹介です!!夏休みに限...
-
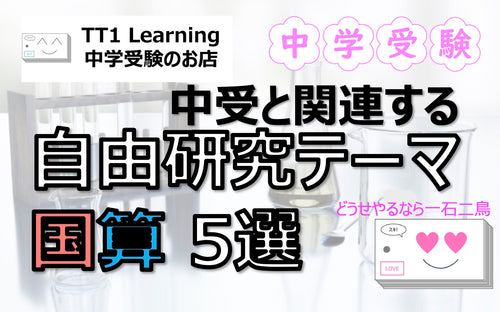
中学受験と関連する おすすめ「自由研究テーマ」国語・算数編
夏休みの宿題といえば、自由研究!!
受験期はなるべく短時間で終わらせて、受験勉強に時間をさきたいところ。
でも、小学生の夏休み、この時期に自由研究をちゃんと体験しておくのも良い経験になると思います!
そう考えると、せっかくな...
-
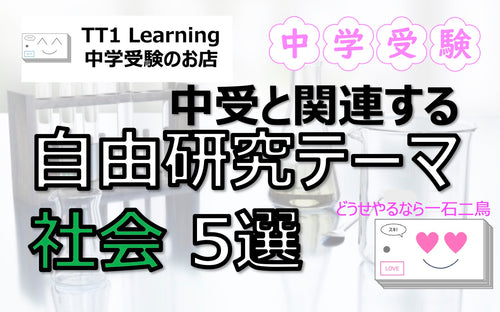
中学受験と関連する おすすめ「自由研究テーマ」社会編
夏休みの宿題といえば、自由研究!!
受験期はなるべく短時間で終わらせて、受験勉強に時間をさきたいところ。
でも、小学生の夏休み、この時期に自由研究をちゃんと体験しておくのも良い経験になると思います!
そう考えると、せっかくな...
-
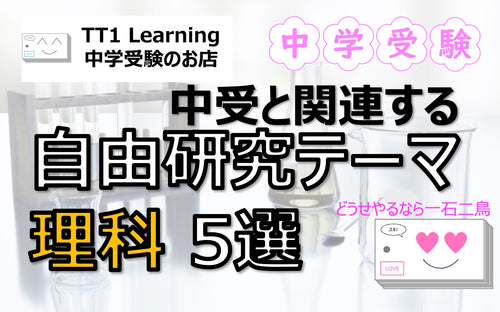
中学受験と関連する おすすめ「自由研究テーマ」理科編
夏休みの宿題といえば、自由研究!!
受験期はなるべく短時間で終わらせて、受験勉強に時間をさきたいところ。
でも、小学生の夏休み、この時期に自由研究をちゃんと体験しておくのも良い経験になると思います!
そう考えると、せっかくなら...
-
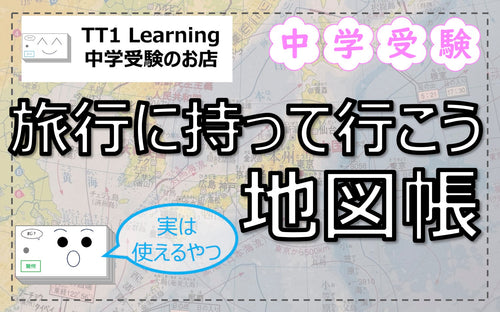
旅行に持って行こう 地図帳!
受験生といえども夏休みに少しは旅行に行きたいですよね!!!
そして、せっかく旅行に行くのであれば、中学受験に少しでも資するようなことをしておきたい!!!
そこで今回ご紹介するのは、意外にも結構勉強に使える教材を使ったものです!
それは...
-
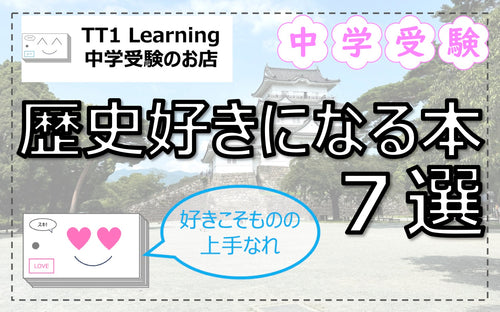
歴史が好きになるオススメの本7冊
5年生下期の社会は歴史一色です!
地理は4年生から5年生前半にかけて、1年半の時間をかけて勉強する一方で歴史は5年生後半のわずか半年で一気にかけぬけていきます。
結構のボリュームがある内容を、かなり短い時間でマスターしていく必要があ...
-
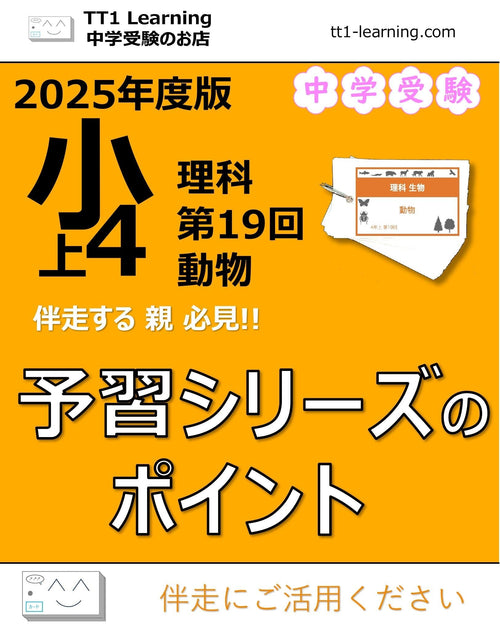
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 理科 第19回「動物」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
小4理科予習シリーズ第19回「動物」では、動物を「背骨があるかどうか」で分類するというシンプルながら重要な考え方を学びます。分類ごとの特徴を理解し、観察眼を養うことがこの単元の目的です。
ただ丸暗記するのではなく、「なぜこのグループに...
-
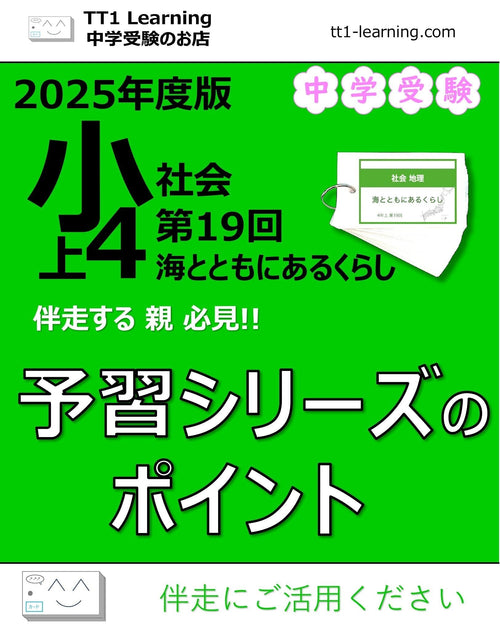
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 社会 第19回「海とともにあるくらし」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
小4社会予習シリーズのポイントをまとめるブログシリーズも上期は今回が最後です!
第19回の単元は「海とともにあるくらし」
この単元では、日本が海とどのように関わり、生活や産業を築いてきたかがポイント。海岸線の種類、漁業や観光、津波対策...
-
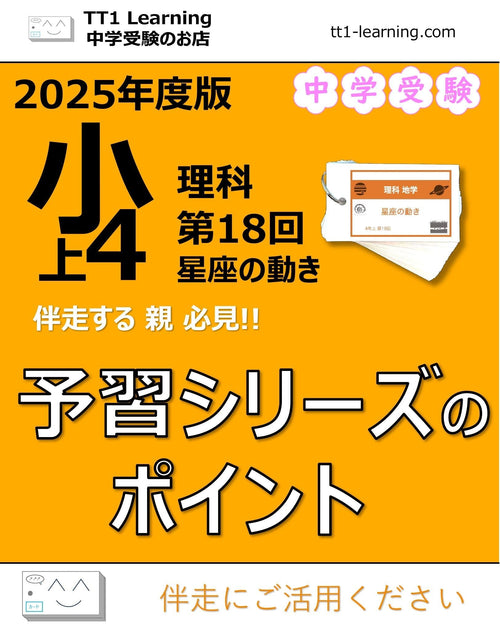
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 理科 第18回「星座の動き」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
18回理科は17回に続いて天体です!!
18回のテーマは「星座の動き」
夜空を見上げるとき、星座がどのように動いているのかを理解すると、星の見え方がもっと面白くなります。星はただそこに輝いているだけではなく、地球の動きによって毎日...
-
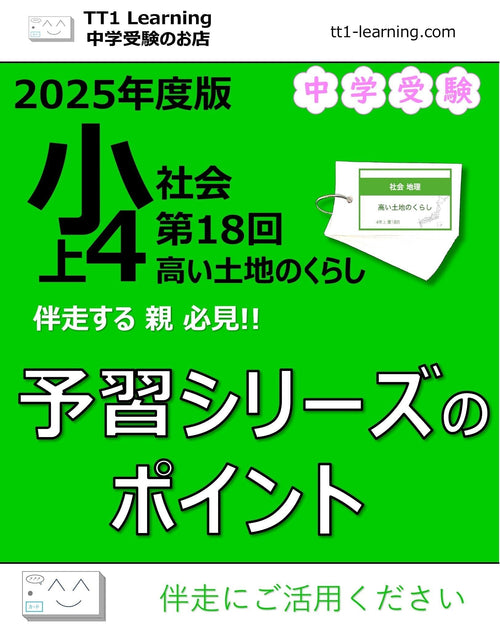
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 社会 第18回「高い土地のくらし(野辺山原)」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
4年生社会予習シリーズ18回のテーマは「高い土地のくらし」。特に、長野県にある野辺山原(のべやまはら)を中心に学んでいきます。
標高が高い土地ならではの気候や自然条件、そしてそこに暮らす人々の工夫が詰まった単元です。高原野菜、酪農、観...
-
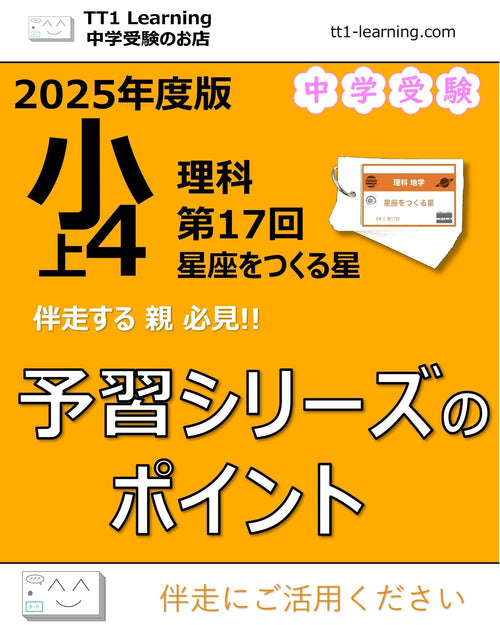
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 理科 第17回「星座をつくる星」攻略ガイド 親子で押さえたいポイントまとめ
17回のテーマは「星座をつくる星」
夜空を見上げる楽しさを学べる、理科の中でも人気の単元です。
ただし、名前を覚えるだけではなく、恒星の特徴、季節との関わり、星座早見表の使い方など幅広い理解が求められます。
親子で一緒に夜空を観察...
-
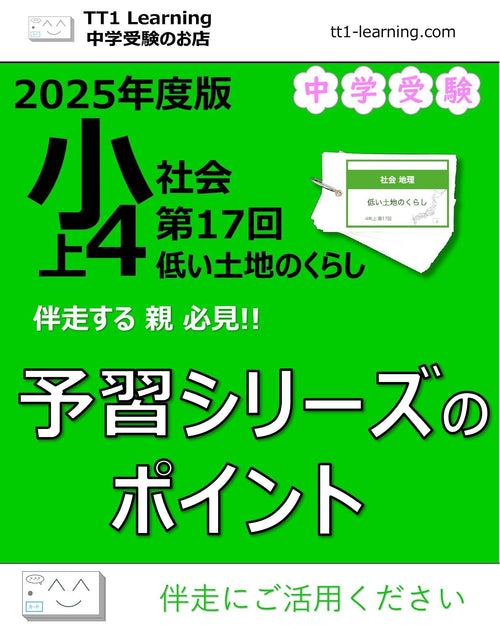
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 社会 第17回「低い土地のくらし(濃尾平野)」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
今回は「低い土地のくらし(濃尾平野)」がテーマです。
濃尾平野は、愛知県・岐阜県を中心に広がる、日本で有数の低湿地帯。
「輪中」という独特の暮らし方や、洪水との闘い、近郊農業の発展など、都市に近いのに自然との共生が色濃く残る地域です。...
-
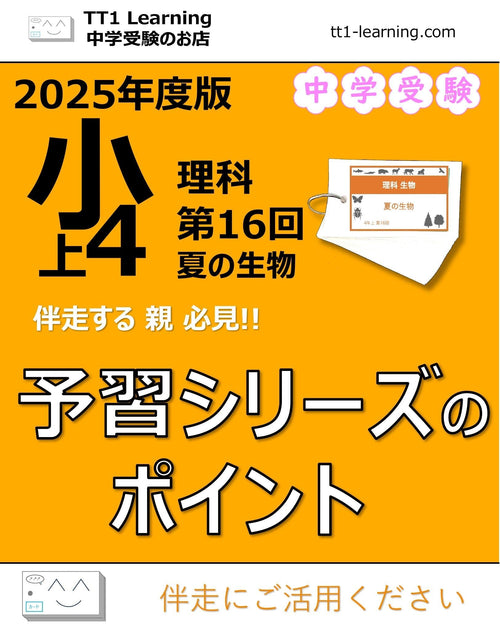
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 理科 第16回「夏の生物」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
理科の 生物単元は、とにかく覚えることが多いですよね。
とくに 夏の生物は、植物・昆虫・セミ・いろいろな動物と範囲が広く、「なにをどう覚えたらいいの?」と迷いやすい単元でもあります。
でも、ただ丸暗記するだけだと 定着しにくく、テス...
-
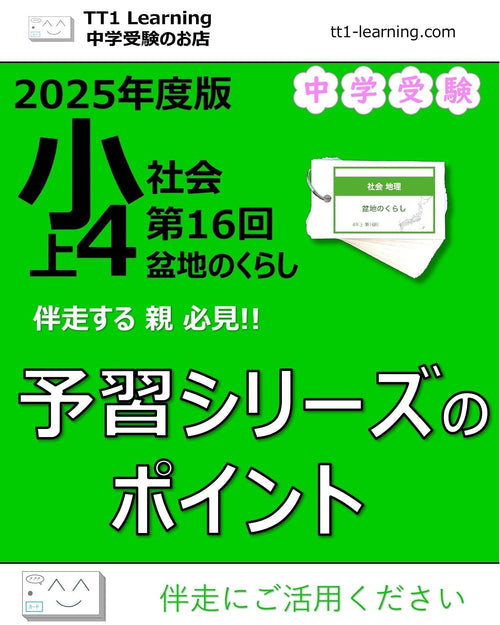
【2025年版 小4】予習シリーズ 上期 社会 第16回「盆地のくらし」攻略ガイド 親子で押さえておきたいポイントまとめ
4年生の社会も後半に入り、地理の内容がだんだんと深まってきましたね。今回の単元「盆地のくらし」は、地形と気候・農業の関係を理解する重要なテーマです。
地図や気候データを見ながら、「なぜその土地でこの産業が発達しているのか?」 を考える...
-
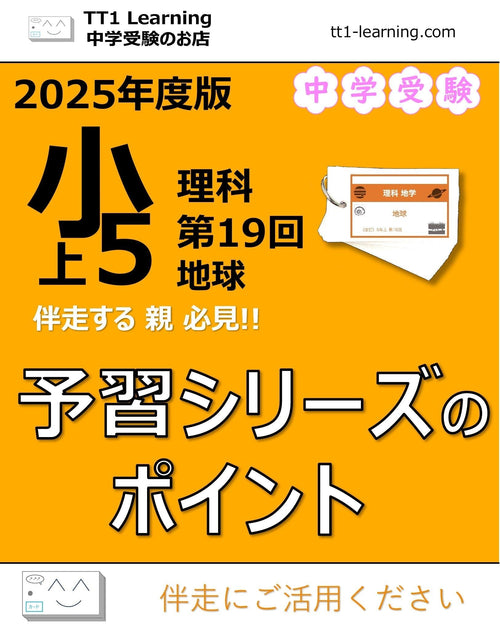
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第19回「地球」ポイントまとめ
上期最後!第19回は「地球」の単元です。
地球は私たちが住む場所ですが、その内部構造、歴史、動きなど、知れば知るほど面白いポイントがたくさんあります。しかし、用語が多く図的理解や計算も絡むので、「覚えることが多い」「混乱する」と感じる...
-
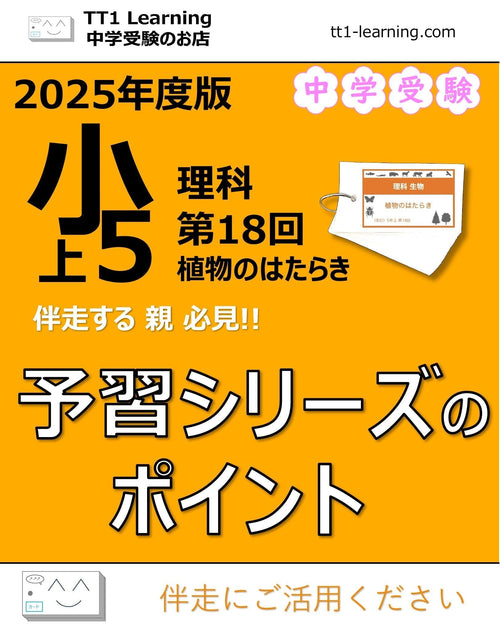
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第18回「植物のはたらき」ポイントまとめ
今回は「植物のはたらき」をテーマにまとめていきます。
植物といえば、普段私たちの周りにある当たり前の存在ですが、その中で行われている活動はとても奥深いです。小学生の理科では、特に「光合成」「呼吸」「蒸散」という3つのはたらきが重要ポイ...
-
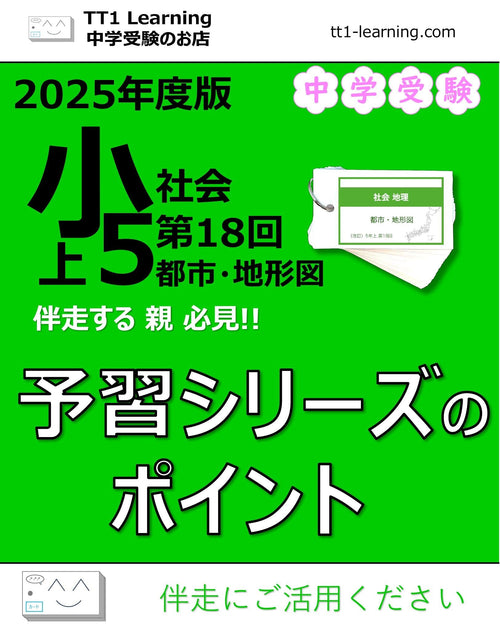
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 社会 第18回「都市・地形図」ポイントまとめ
小5社会予習シリーズ第18回は「都市・地形図」この単元では、都市の人口や特徴と地形図を正確に読み解くことが求められます。
都市ごとの特色や地図記号の理解は、中学受験でよく問われるポイントです。保護者の方が伴走しやすいように、ポイン...
-
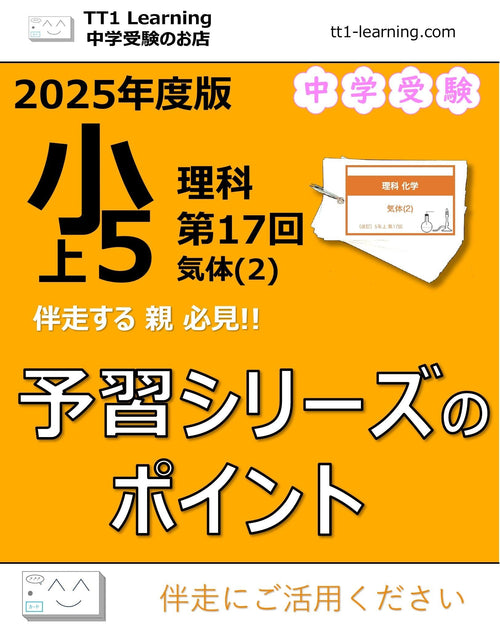
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第17回「気体(2)」ポイントまとめ
理科17回の単元は、前回に続き「気体(2)」です。前回の単元をまだ見ていない方はこちら(16回理科 気体(1))から
ここでは主に、水素と金属の反応、二酸化炭素の発生、酸素の発生と触媒の役割、そしてこれらのグラフの読み取りが大切なポイ...
-
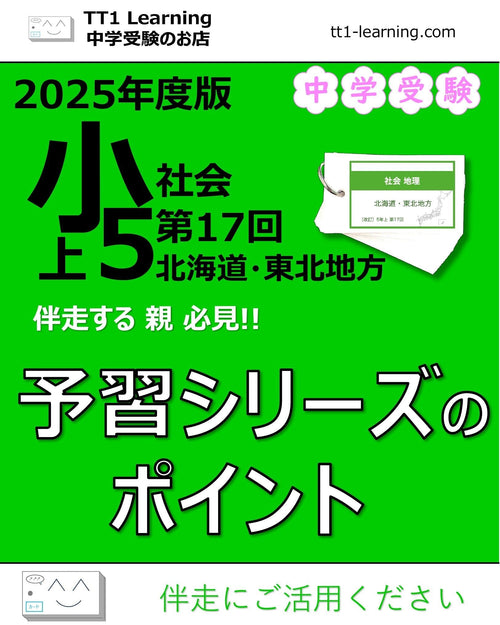
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 社会 第17回「北海道・東北地方」ポイントまとめ
小5社会の予習シリーズ第17回では、北海道・東北地方を学習します。この単元は地理的な特徴だけでなく、農業や伝統工芸、世界遺産など幅広い内容が含まれています。特に北海道はアイヌ語由来の地名が多く、漢字が難しいため、しっかりと確認しておき...
-
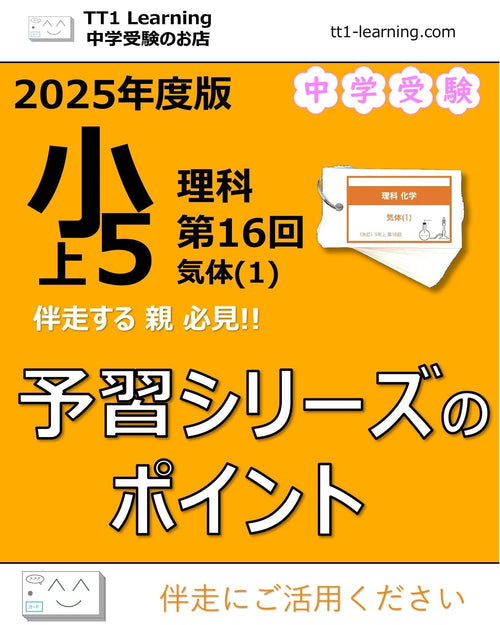
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第16回「気体(1)」ポイントまとめ
今回のテーマは理科「気体(1)」の単元です。
気体は中学受験理科の中でも、出題頻度が高く、苦手意識を持つお子さんも多い分野です。しかし、一度「なぜそうなるのか」を理解して整理しておくと、化学の似たような単元は同じ考え方でクリアでき...
-
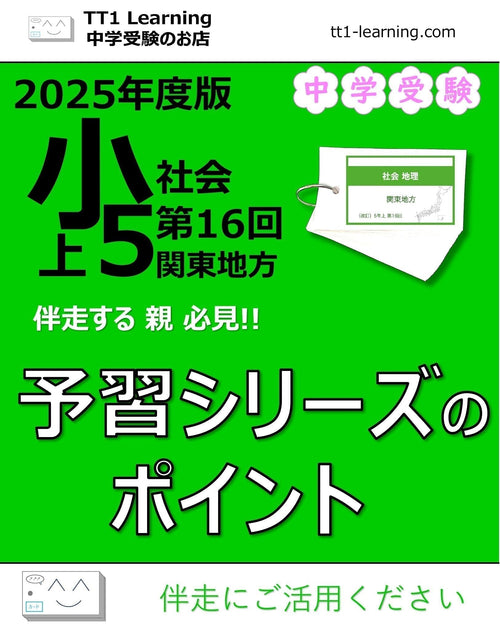
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 社会 第16回「関東地方」ポイントまとめ
今回は、予習シリーズ小5・上巻の第16回「関東地方」についてのまとめです。
関東地方は、地理・産業・交通など幅広く出題される頻出エリア。
暗記に頼るだけでなく、地形や産業の特徴がどのように結びついているかまで意識すると理解が深まります...