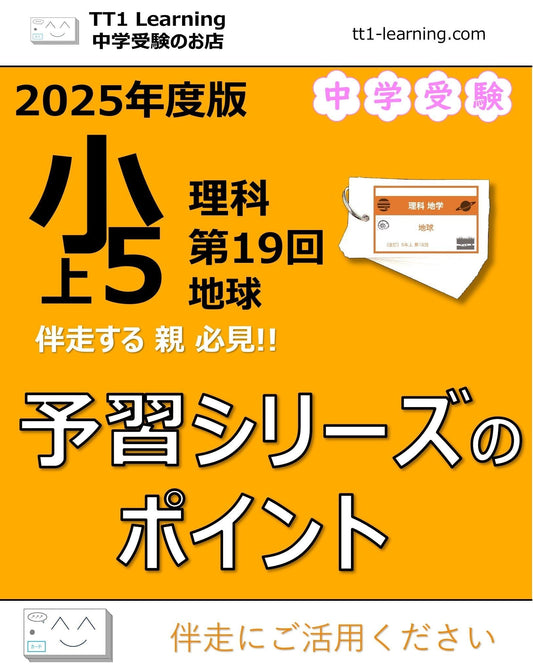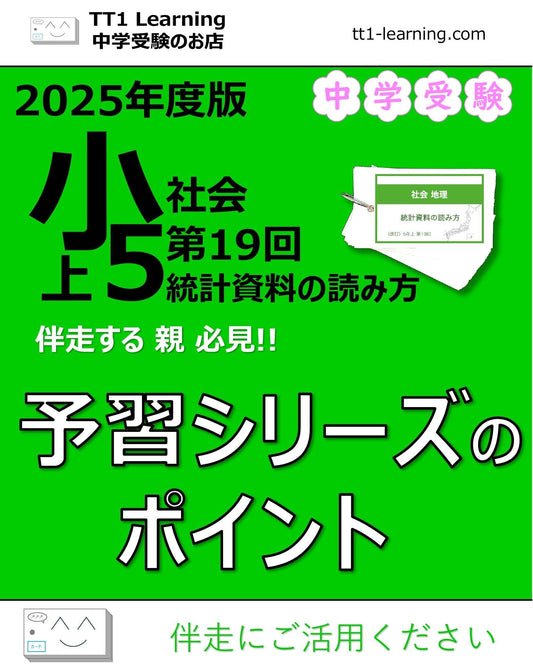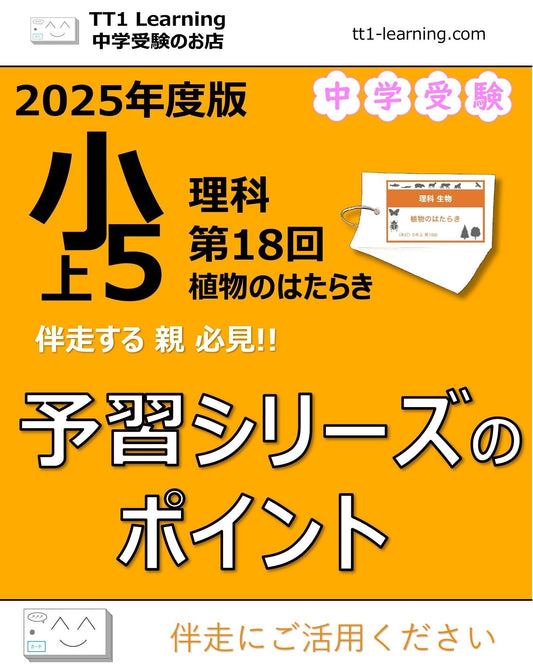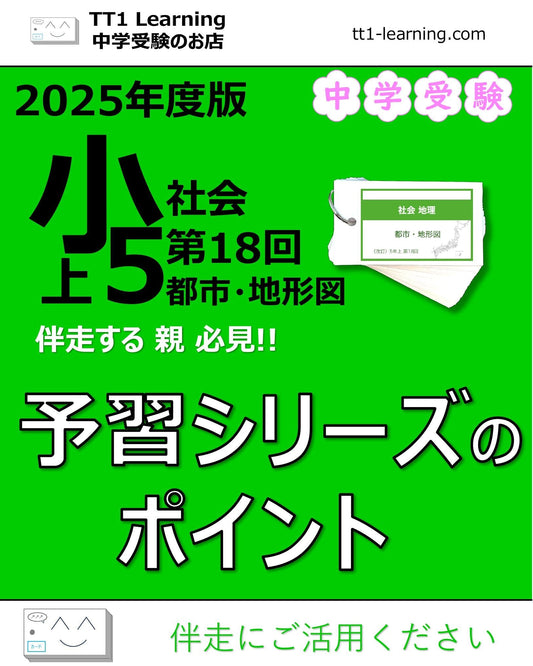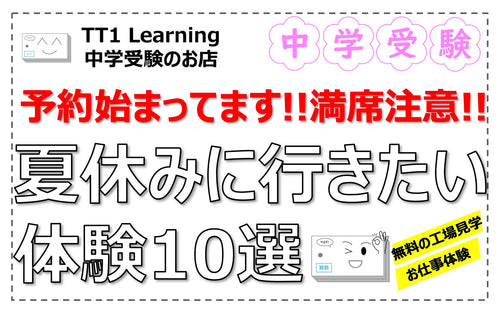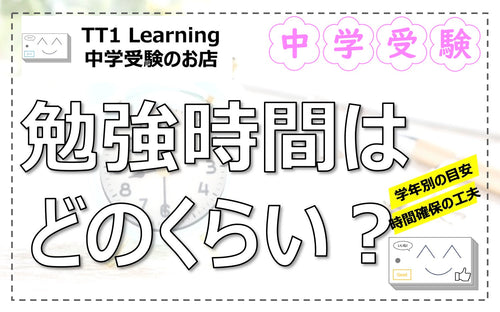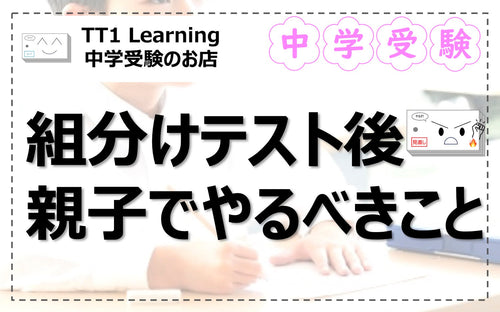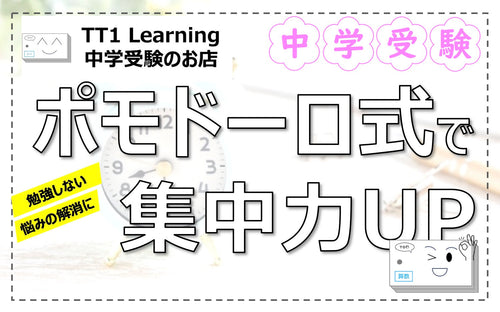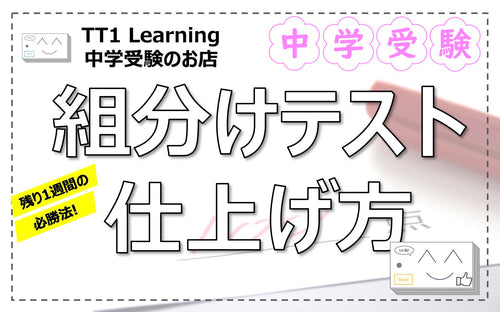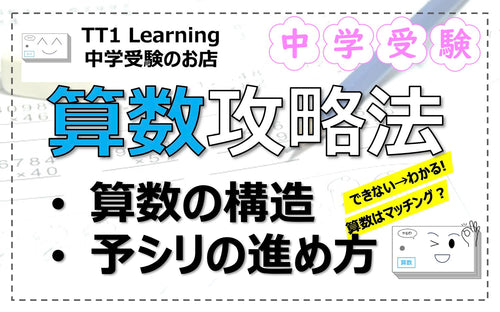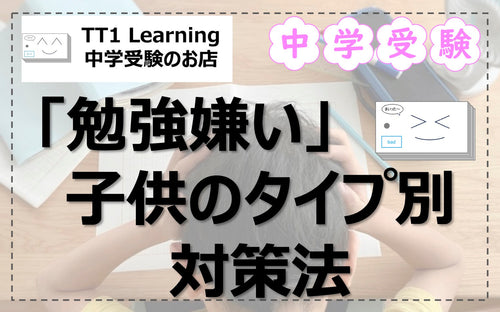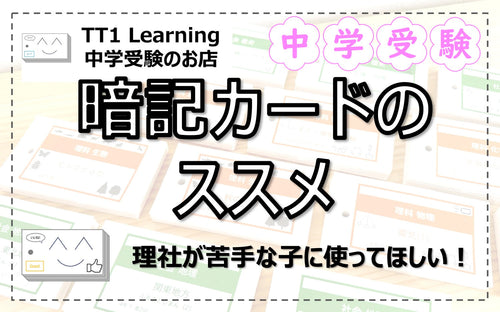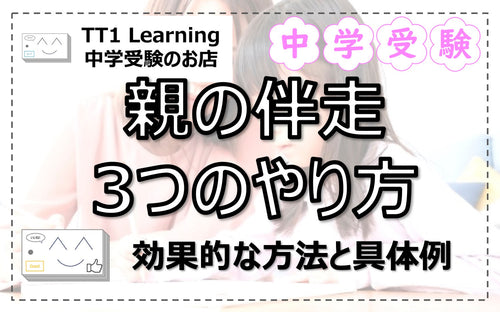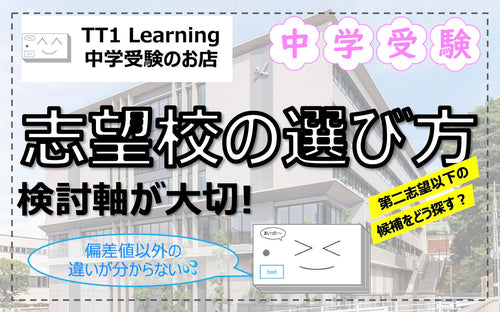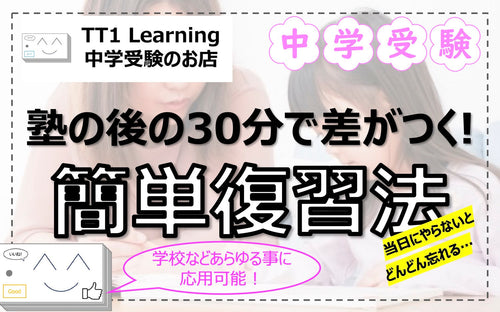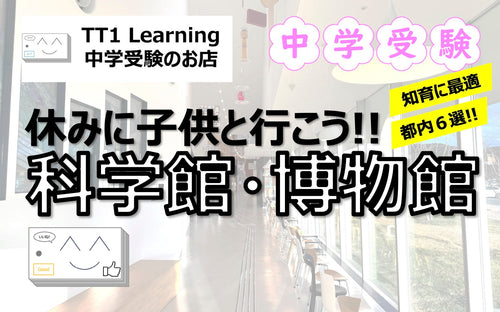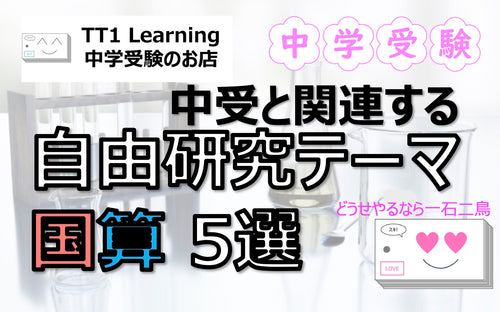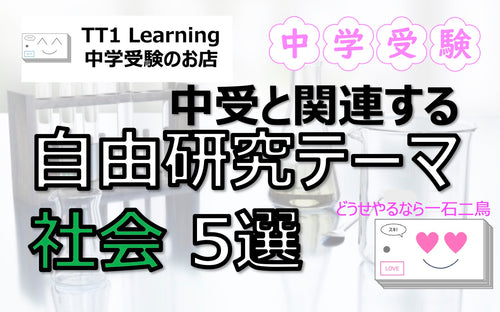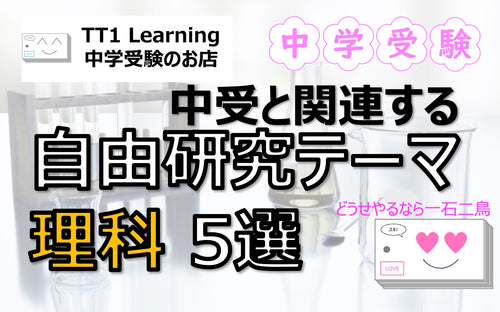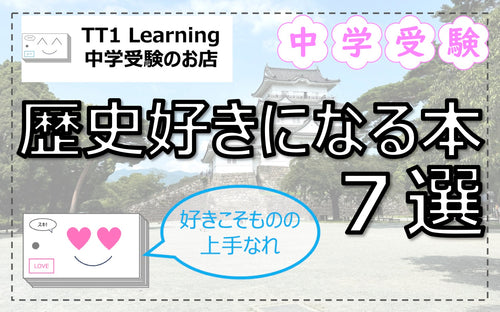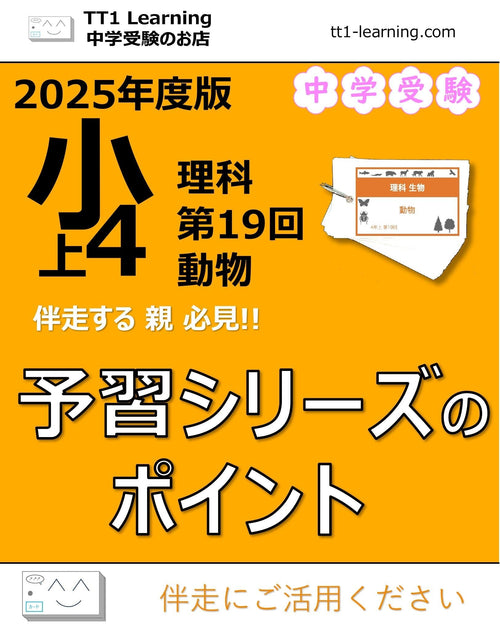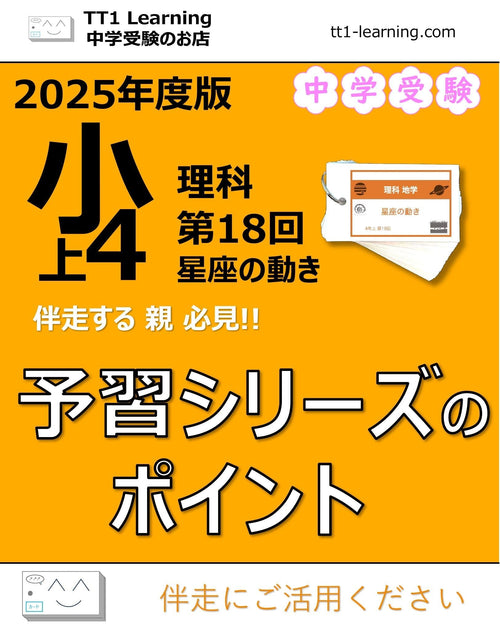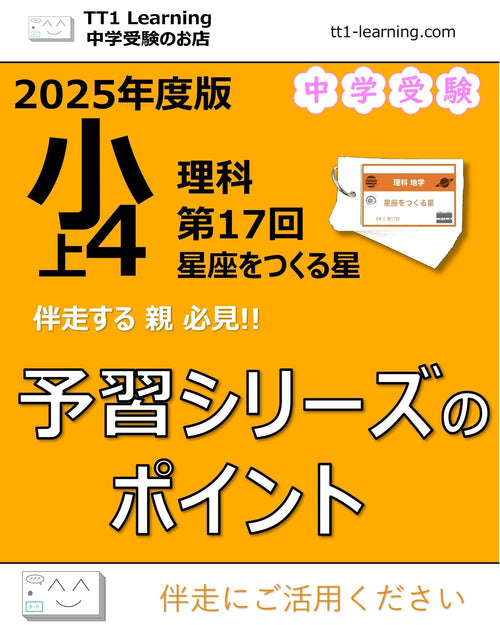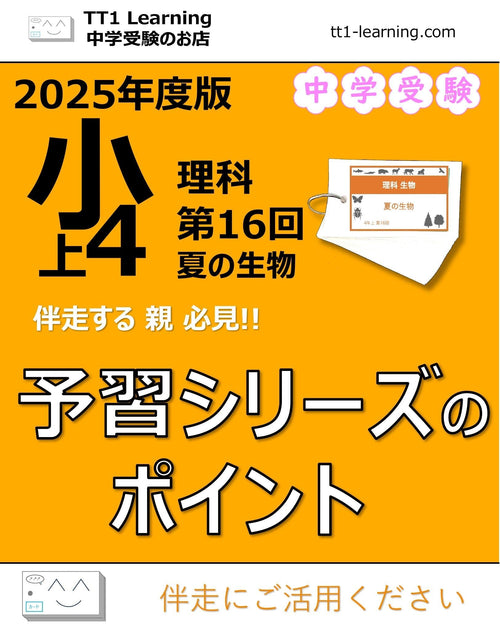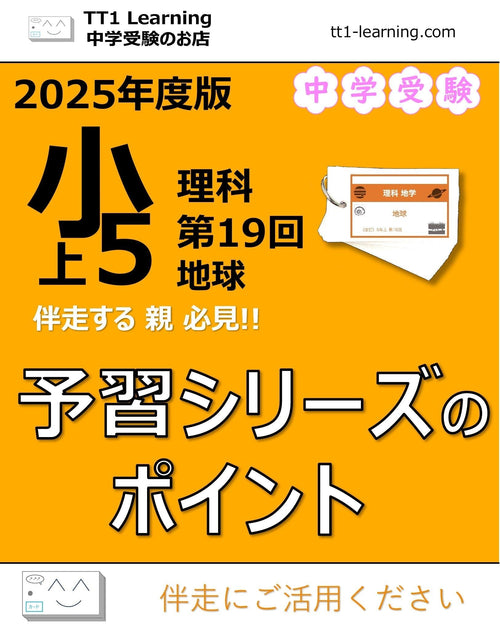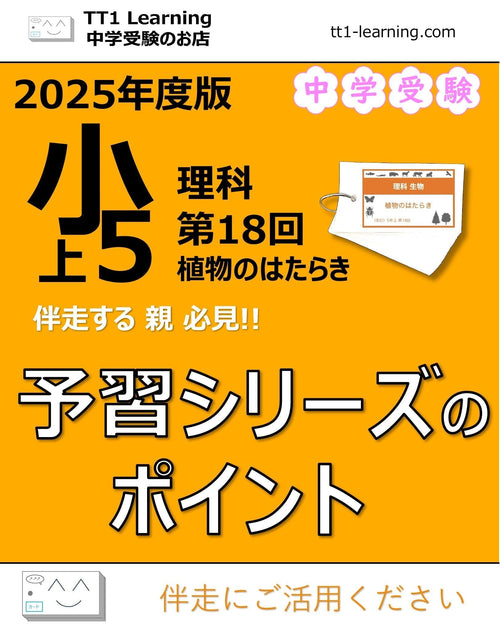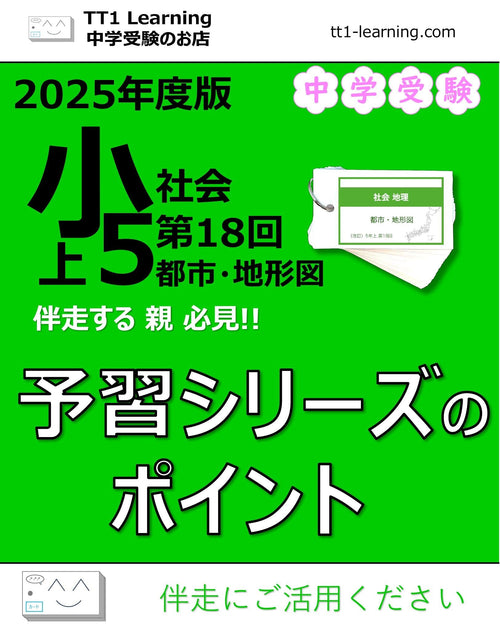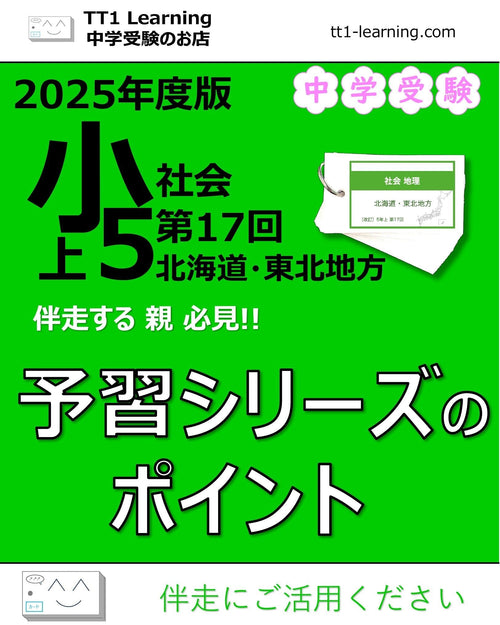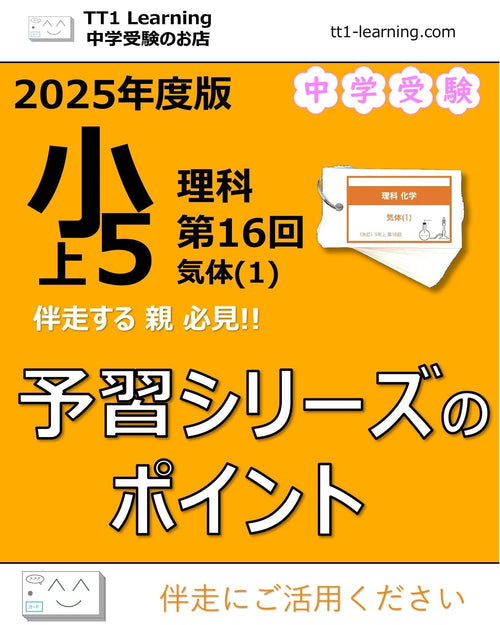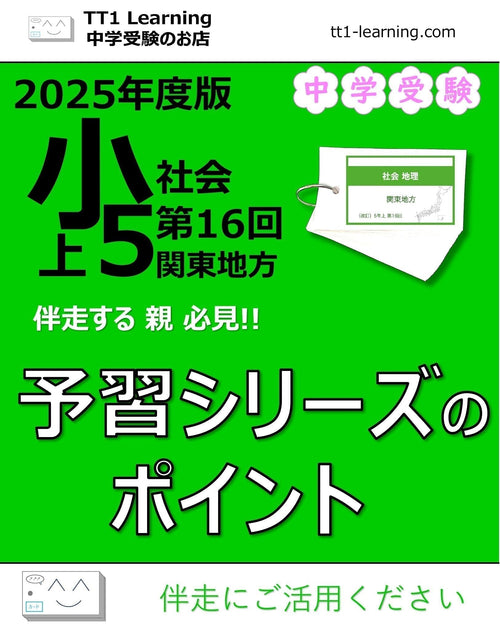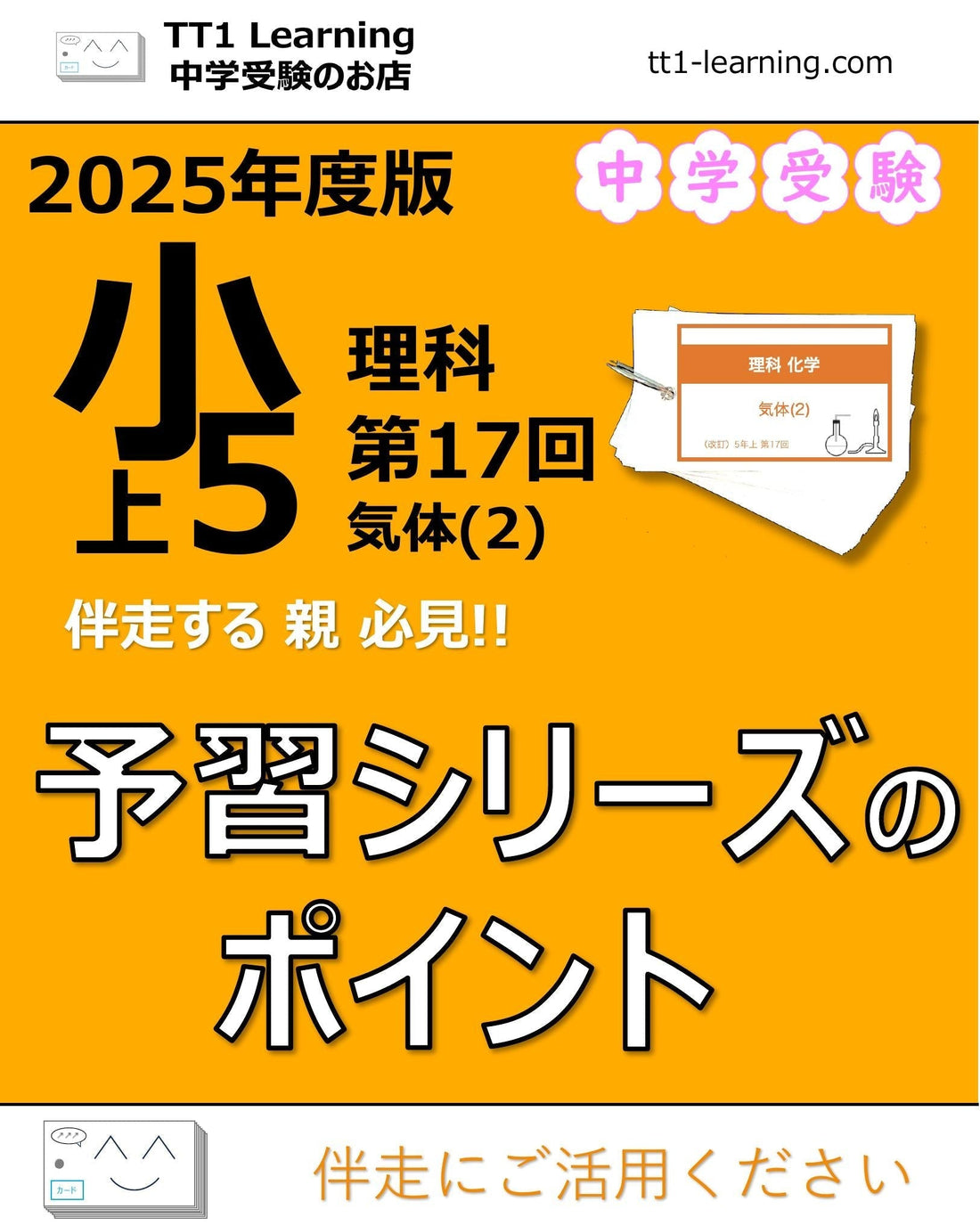
【2025年版 小5】予習シリーズ 上期 理科 第17回「気体(2)」ポイントまとめ
共有
理科17回の単元は、前回に続き「気体(2)」です。
前回の単元をまだ見ていない方はこちら(16回理科 気体(1))から
ここでは主に、水素と金属の反応、二酸化炭素の発生、酸素の発生と触媒の役割、そしてこれらのグラフの読み取りが大切なポイントになります。
計算やグラフ問題は苦手に感じるお子さんも多いですが、ポイントを整理して理解していけば必ず得点源にできます。親御さんと一緒に確認しながら進めることで、お子さんの理解度と自信が大きくアップすると思います!!
頑張ってください!
単元の概要
この単元では、以下の内容をしっかり押さえましょう。
-
水素の発生:水溶液と金属の反応で水素が発生します。組み合わせや副生成物、反応後に残るものを把握することが大事です。
-
二酸化炭素の発生:水に溶けやすい二酸化炭素の発生量の測り方、反応後に残る固体の種類、グラフの読み取りを理解します。
-
酸素の発生:二酸化マンガンが触媒として使われる意味を学びます。触媒は反応を助けますが、自身は変化しません。
これらを整理しておくと、複雑に見える問題もスムーズに解けるようになります。
1. 水素の発生と金属の関係を理解する
まずは水素の発生について確認しましょう。水素は金属と酸やアルカリ性の水溶液が反応すると発生します。
-
塩酸 + アルミニウム → 水素 + 塩化アルミニウム
-
塩酸 + 鉄 → 水素 + 塩化鉄
-
水酸化ナトリウム + 亜鉛 → 水素 + 四水酸化亜鉛ナトリウム
ここで重要なのは、どの金属がどの水溶液と反応して水素を発生させるのかを整理することです。また、反応後にできる塩(副生成物)も把握しておきましょう。
さらに、金属の種類によって反応のしやすさが異なることもポイントです。例えば、銅は反応しないため、問題に出てきても「水素が発生しない」と判断できます。このように「反応する・しない」を一瞬で判断できると、計算問題や選択問題で大きな武器になります。
2. 水素の発生量グラフの読み取り
次に、グラフの読み取りです。例えば、一定量の塩酸に対してアルミニウムの量を変えて水素の発生量を調べたグラフがよく出題されます。

グラフには「加えたアルミニウムの量」と「発生した水素の量」が描かれており、ある点で最大値に達します。ここを境に、それ以上金属を加えても水素の量は増えません。このポイントは「塩酸が全て使い切られた」という意味を持っています。
逆に、もしアルミニウムが残っている場合は、塩酸が不足していると考えられます。こうした読み取りは、問題文をよく読んで軸の意味を正確に理解することが大切です。
一見難しそうですが、「何が余っているのか」「どこで反応が終わるのか」という視点で整理すると、理解が深まりスムーズに解答できます。
3. 二酸化炭素の発生と残った固体の確認
二酸化炭素は、炭酸カルシウムと塩酸の反応で発生します。
-
炭酸カルシウム + 塩酸 → 二酸化炭素 + 水 + 塩化カルシウム
発生した二酸化炭素の量はどのように測るべきでしょうか?
下の図のような装置で測ります。

なぜ、②の三角フラスコが必要なのか?
ここを正しく理解しましょう。
・発生した気体の量を正確に測るには水上置換法が必要
・二酸化炭素は水に溶けやすい
・二酸化炭素は空気よりも重い
この三つからこの図の形が導き出せます。
①の三角フラスコで発生した二酸化炭素は②の三角フラスコの下にたまります。
②のフラスコ上部の空気が押し出され空気なので水には溶けずに③のメスシリンダーに二酸化炭素が発生した分だけたまります。
次にこの反応で反応後に残る固体が重要です。塩酸が過剰な場合、炭酸カルシウムはすべて反応し、残る固体はありません。一方、炭酸カルシウムが過剰な場合には、反応後に炭酸カルシウムが残ります。この「残るか、残らないか」の判断は、グラフ問題や計算問題で頻出です。

例えば、グラフの縦軸が「残った固体の量」、横軸が「加えた炭酸カルシウムの量」になっていることが多いです。縦軸の読み取りを間違えると、全ての計算がずれてしまいますので、必ず「何を表している軸か」をお子さんと一緒に確認しましょう。
また、問題によっては「塩化カルシウムの量」を問われることもあるので、副生成物の理解も欠かせません。
4. 酸素の発生と触媒の役割
酸素は、過酸化水素水に二酸化マンガンを加えることで発生します。
-
過酸化水素水 + (触媒)二酸化マンガン → 酸素 + 水
ここで重要なのが「触媒」の理解です。触媒は化学反応を助ける役割をしますが、最終的には変化せずに残ります。二酸化マンガンを多くしても、生成する酸素の量は増えませんが、反応速度は速くなります。

グラフにおいては、二酸化マンガンの量を増やすと反応の曲線が急になりますが、最終的に到達する酸素の量は変わりません。この点は記述問題でも問われやすいため、しっかり理解しておきたいポイントです。
「触媒は助けるだけで、反応に使われない」というイメージをお子さんと一緒に確認し、理解を深めましょう。
5. 暗記カード&確認テストの活用法
一通り学習が終わったら、アウトプットを重ねて理解を定着させましょう。暗記カードを使えば、反応式やグラフの意味をスキマ時間に確認できます。
例えば、親御さんが問題を出して、お子さんがカードを見ずに答える「クイズ形式」にするのもおすすめです。間違えたところはその場で再確認することで、「わかったつもり」を防げます。
当サイトの単元別暗記カードは、予習シリーズに沿った内容で作られているため、効率よく要点を抑えられます。反応式や生成物、副生成物など、細かいところまでカバーされているので、復習にも最適です。
まとめ
「気体(2)」の単元は、計算問題やグラフ問題が多く、一見難しく感じるかもしれません。しかし、ポイントを整理して理解することで、確実に解けるようになります。
「どこがわからないのか」を一緒に話し合いながら進めると、お子さんの理解度が大きく変わります。最初は時間がかかっても、慣れてくるとスムーズに解けるようになりますよ。
小さな「できた!」の積み重ねが自信につながり、テスト本番でも力を発揮できます。親御さんとお子さんが一緒に取り組む時間が、成績アップだけでなく、大切なコミュニケーションの機会にもなります。
今回の記事は以上です!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
お役に立てましたら嬉しいです!
小5上期の予習シリーズのポイントの記事
社会
理科
さらに読みたい関連記事
- 「暗記カード」のススメ 〜理社が苦手な子にこそ使ってほしい!→ 子供が自らやりたい!と言って動き始めた!キーは暗記カードその理由とは!
- 塾の復習法|塾のあと30分で差がつく!効率的な家庭復習 → 毎日の学びをしっかり定着させる時短復習法を紹介。
- 国公立中高一貫校に受かる子の特徴→ 合格を勝ち取る5つの要素とは。